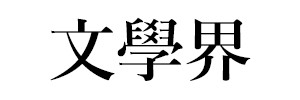書評
『批評メディア論――戦前期日本の論壇と文壇』(岩波書店)
荒野から始まる
本誌二月号の匿名コラム欄「鳥の眼・虫の眼」で相馬悠々が、実名書評は「作家同士の友情の証し、儀礼の交換」ばかりになったと慨嘆している。『群像』の匿名欄「侃侃諤諤」の消滅がトピックで、同誌に書評の匿名化を促す内容である。匿名なら「本音」が忌憚なくいえるから書評の質は向上するというわけだ。まず自誌で試みるのが筋だろうという突っ込みは措く。現況の書評欄はたしかに相馬のいうとおりのものだ。だが暗黙の了解事項で問題にされることはまずない。したがって相馬の指摘はスキャンダラスであるはずである。
相馬の告発はしかし何ら波紋を呼んでいない。匿名で「本音」を漏らしたところで効果がないことが自己言及的に示された皮肉な例となっただけだ。なぜ波紋は生じないのか?
メディア史研究者である大澤聡が七年半かけてまとめ上げた本書は、その疑問に対する解の一端を提出するだろう。
この本の目的は、批評(あるいは言論、思想)という営為はいかにして組成されるのか、そのメカニズムを解析することにある。解析対象は一九三〇年前後の言論空間だ。ここで「日本の文学場はひそかな、しかし決定的な転形期をむかえ」「現在もこの時点で構築されたパラダイムの只中に批評はあり続けている」からというのが理由とされる。
一九三〇年の「決定的な転形」とは何か。円本ブーム以後、出版市場の拡大と読者の開拓が爆発的に起こり、「文学」が「商品」であることを余儀なくされるようになった事態を指す。むろん文芸批評も同様だ。商品として流通するにはパッケージが要る。雑誌や新聞がその機能を担い始める。読者=消費者の嗜好と興味を惹き続けるために、雑誌・新聞はパッケージを刷新し続けなければならない。
このダイナミズムの中で批評は存立の様態を決定されていく。解析作業は徹底して「形式」に注目して行われる。「メディアこそがメッセージ」(マクルーハン)だからだ。そしてこれまでは「内容」の低いものと顧みられなかった、読み捨てが前提の時評の類こそ「言論生成の現場を浮かびあがらせる」ものとして執念深く渉猟され分析され引用される。
「論壇時評」「文芸時評」「座談会」「人物批評」「匿名批評」の五つの形態がこの順で取り上げられていくのだが、宣言どおり、現在の言説空間に対する分析として敷衍してもまったく通用してしまう。
読後に残るのは寒々とした光景だ。批評など書くことに意味はあるのか? という問いがきっと浮かぶだろう。だがその荒野こそが、新たな批評に用意された土壌なのである。
ALL REVIEWSをフォローする