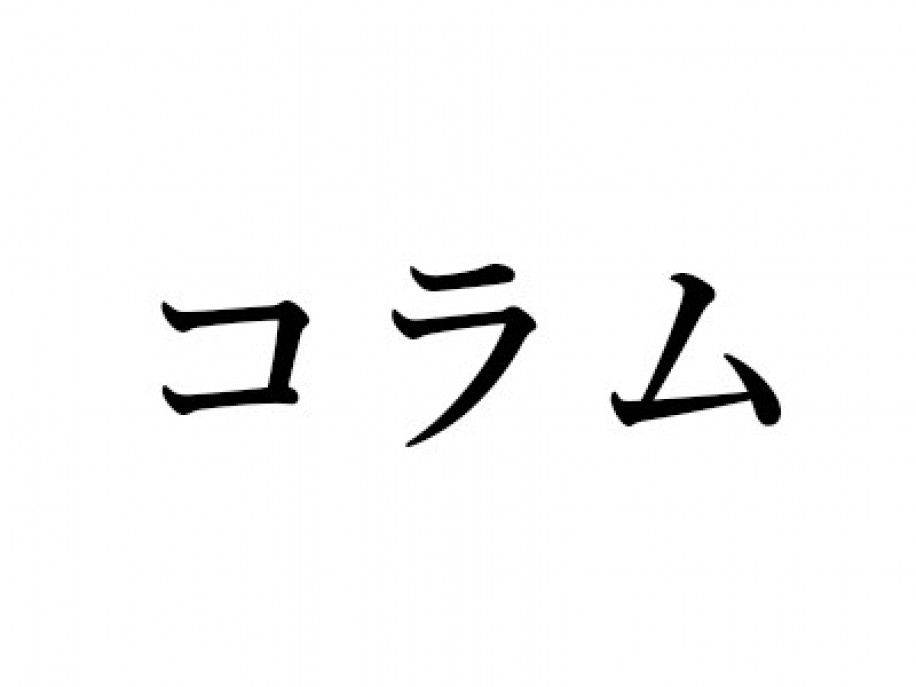書評
『江藤淳と大江健三郎: 戦後日本の政治と文学』(筑摩書房)
私小説的手法で描く戦後文学史
文学史不在の時代だ。そんな状況にあって文学の新規性はどう確保すればよいのか。私は文芸誌の月評で、小谷野敦の小説をこの課題に応えうる優れた解答の一例と評したことがある。私小説が衰退して久しい。小谷野の一連の小説はその系譜を現代に甦(よみがえ)らせるきわめて批評的な試みであり、そうした振舞いがかえって新しさを産んでいる。反転させて評価したわけだ。しかも、大量の随筆や論考を発表しているから、ちょっと詳しい読者であればそれらの関連箇所と繋(つな)ぎながら小説を読むことになる。実際、私がそうだ。だから、「読書行為を複層化する総合創作」と表現した。その「総合」は小谷野敦という固有名のもとに実現するだろう。
前置きが長くなった。が、ゆえなきことではない。というのも、本書もこれと全く同じ枠組で評価されるべきだからである。評論の世界で評伝が流行(はや)らなくなって久しい。小谷野はそれを一連の作品によって復活させようと試みてきた(『谷崎潤一郎伝』『川端康成伝』など)。やはりそこが古くて新しい。
宿敵関係にあった江藤淳と大江健三郎――。二人の文学者の履歴が同時並行的に進む。「同年、江藤は……」「その頃、大江は……」といった具合にシャッフルしながら。両者の軌跡は一時的に交差し(蜜月時代)、また離れる。堅実な資料探査と豊富な読書経験によって確定してゆく行文には面白エピソードやゴシップの類がひっきりなしに投入され、その探偵的な手つきは作品をエンターテインメントとしても通用させる(例えば、江藤の学問コンプレックスの暴露)。あくなきヒューマンインタレスト(=人間への興味)が一貫して記述を支える。斬新な解釈や発見の他にも、周辺知識が遠近容赦なくどんどん織り込まれてゆくから、どのページも端的に勉強になる。
それだけではない。著者自身の履歴や読書史も随時混入されてゆく。「さて私はといえば……」といった具合に。一般的な伝記のスタンスとはだいぶ異なる。インタレストの対象に「私」も含まれているのだ。当然、読者は江藤淳と大江健三郎を読む小谷野敦を読むことにもなろう。かくして、私小説的な読書の円環がぐるりと結ばれる。
小谷野は多彩なジャンルの著書を続々発表する。それらを総合した地点に、新たな文学ジャンルが立ちあがりつつあるように、私には見える。その上でやはりこういおう。本書は戦後文学史再考のための必読の書である。伸縮する二者(三者)の間隙に全てが凝縮されている。
ALL REVIEWSをフォローする