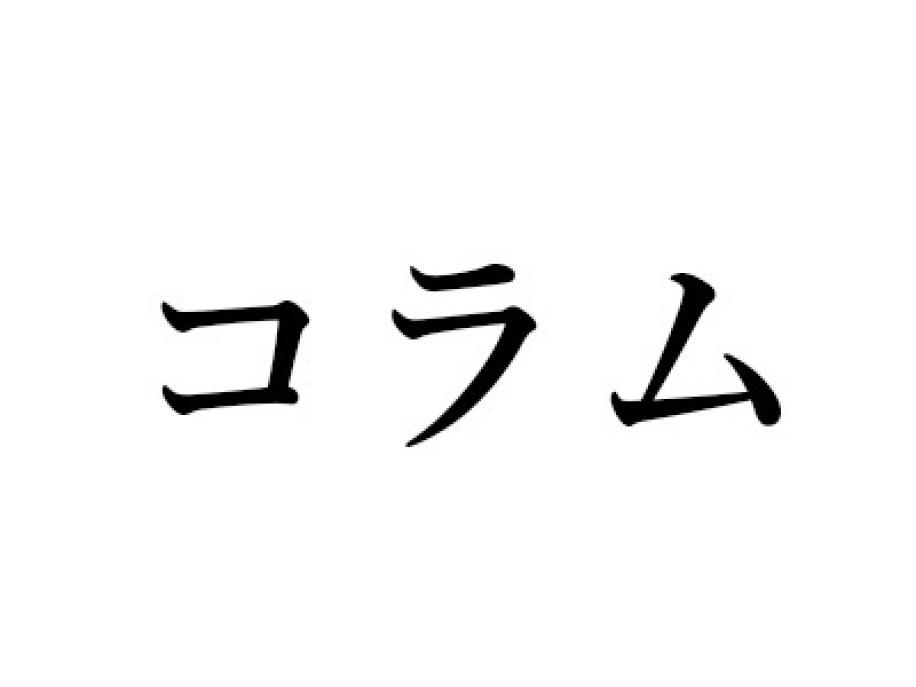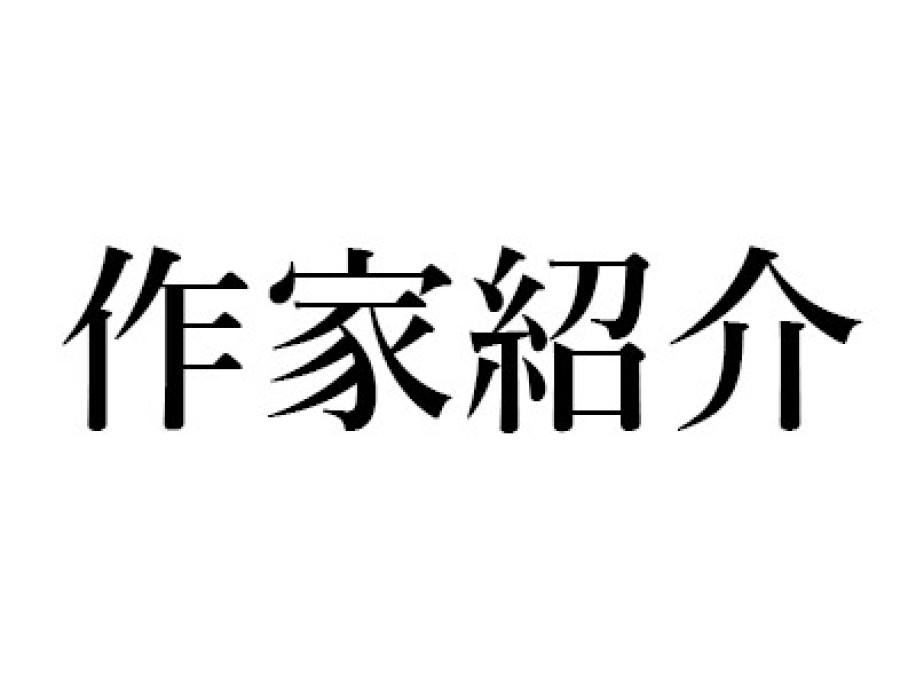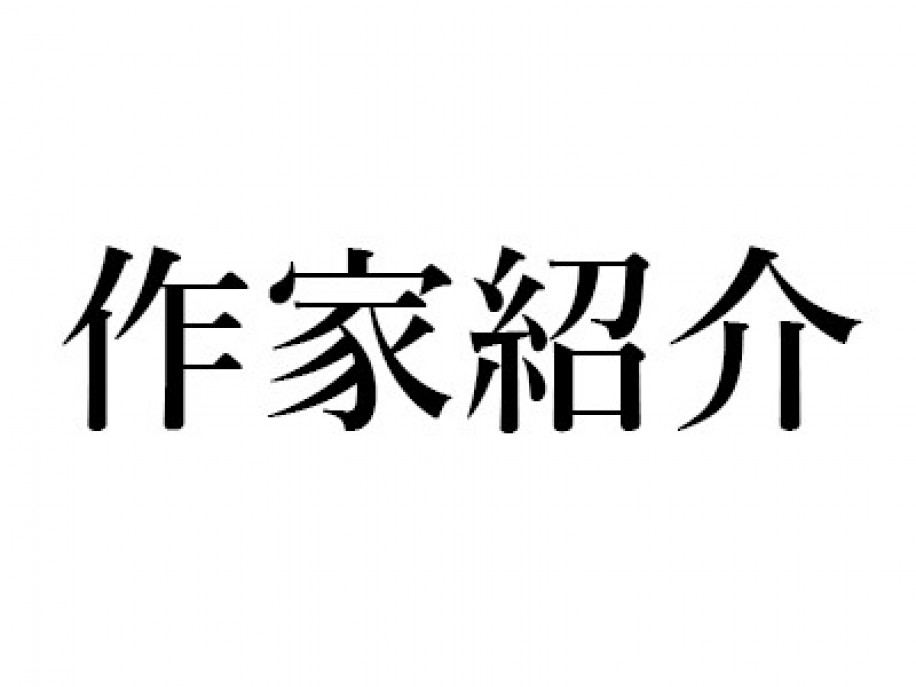書評
『チリ夜想曲』(白水社)
文学の罪深さに焦点
ボラーニョは早世したこともあって、この十五年ほど、一番話題になることの多いスペイン語圏の作家だった。それだけに、僕はけっこう警戒していたのだ。だから、この本もあまり本気にしないように気をつけながら読み始めたのだが、いつしか蟻(あり)地獄のように引きずりこまれ、途中でやめられなくなった。死の床に横たわる老人が、ふと意識がはっきりした瞬間に起き上がり、ベッドの上に片肘(ひじ)をついて自分の人生を検証する。その一瞬のうちに回帰してきた人生のいくつもの場面が、妄想とも現実ともわからぬまま語り継がれていくのがこの作品の構造をなす。ひとつの記憶から次の記憶への推移には何の根拠もないように見え、いつの間にか次のエピソードに移っているので、読者は道筋を見失い、作者が何をやろうとしているのかわからずに困惑する。語り手はわざと一般読者からは嫌われそうなカトリックの神父、しかも、毀誉褒貶(きよほうへん)のある特異な組織オプス・デイのメンバーと設定されている。にもかかわらず、文人としても名をなしたこの人物の語りの渦の中に読者は巻きこまれていく。最後の一ページまで一度も改行のない奇怪な文体の中に、ボラーニョは実に巧みに読者を導いていくなと思った。そして翻訳もけっこう読ませるのだ。
チリと言えば一九七三年の軍事クーデタと、その後九〇年代まで続いた長い独裁政権を問題にせざるをえないが、その扱いもここでは実に皮肉で、定型的ではない。主人公は年齢的にも思想的にも、軍政下の時代にこそ社会的地位を揺るぎなくしていくが、そのあたりから物語はぐいぐいと核心に入っていく。そして、それまで散乱しているように見えた多様なエピソードが実は文学そのものと関わっていたことが最後になって急激に浮かび上がってきて、くっきりとした焦点を結ぶ。不幸や抑圧がある場所でこそ生まれてくる文学の罪深さこそが問題にされていたことに呆然(ぼうぜん)となる。野谷文昭訳。
ALL REVIEWSをフォローする