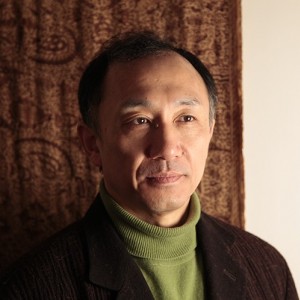書評
『ネクスト―善き社会への道』(麗沢大学出版会)
対話を通じ内面からの秩序づけ目指す
コミュニティーを社会の基盤とみなすコミュニタリアニズムは90年代以降のアメリカで、自由放任の市場原理にもとづく新保守主義と、福祉や権利を国家によって保障しようとするリベラリズムの双方を批判する思想として脚光を浴びた。アメリカでは建国時に、市場や連邦よりも地域共同体や自発的結社が社会を支えたという経緯があるから、中道を行く「第三の道」を標榜(ひょうぼう)してはいるものの、考え方としてはむしろなじみ深いはずだ。とはいえ、家族や地縁・信仰などを中心とする伝統的な共同体の再興を目指す社会保守主義とは異なる。職業や性的指向、趣味などを通じて社交する多様なコミュニティーも含める点が現在形だ。
コミュニタリアニズムは当初、哲学畑でリベラリズムの非歴史的な人間観を痛烈に批判して注目されたが、社会学者であるエツィオーニは具体的な公共政策を打ち出している。以前の『新しい黄金律』は学術的大著だったが、今回は「同胞市民に向けて」書かれたパンフレットだけあって、内容は簡潔である。
人々を自由放任や国の強制によって外面的につなぐのでなく、対話を通じて内面から秩序づけようとする点が重要だ。吸わない人に煙を吹きかけてはならないという配慮が共有されているならば、喫煙は法で禁止されなくてすむ。そして社交や対話は人として互いに敬意を払うところに始まるから、衣食住で「尊厳」を確保しうるだけの「ベーシックミニマム」が必要になり、そこから権利と責任の均衡をめぐって警察や公衆衛生、サイバースペースなどについての各論が展開される。
近年、経済競争に勝つための高等教育が整備されつつあるが、学力よりも対話能力を養う初等・中等教育こそが重要だとエツィオーニは指摘する。これには感銘を受けた。学者は学者言葉、会社人間は会社言葉に染まる日本では、対話能力の低さこそが懸念される。「ゆとり教育」は、そこに焦点を当てるべきだった。
監訳者解説はアメリカの政治潮流も踏まえて有益だが、字句表記などで自己宣伝の気配があり、戸惑う。
朝日新聞 2005年5月29日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする