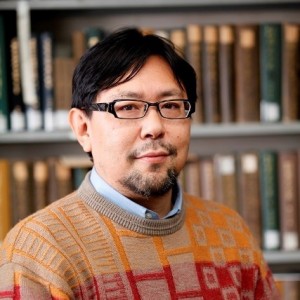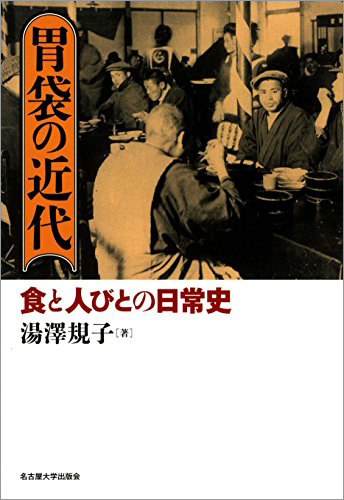書評
『本懐』(光文社)
切腹は“達成”であり次の歴史を作っていく
あれ?と首をかしげた。本書には「まえがき」がある。小説にしては珍しいと思いながら読んでみると、切腹について説明してくれる。意味、歴史、それに種類。まず1「普通の切腹」、2「追い腹」、3「詰め腹」、4「諫言(かんげん)腹」、5「無念腹」。なるほど。でもその真意って……?本編には6人の切腹が描かれる。トップバッターは大石内蔵助でまさに傑作。著者は出し惜しみなしで勝負を決めるつもりらしい。次に織田信長。人間くさい信長の造形は新鮮。3番が狩野融川(ゆうせん)。幕府お抱え絵師の世界。知識欲も満たされる。次が堀直虎。初めて納得できる直虎解釈に出会った。5番目は西郷隆盛。短編ながら、伏線がみごと。最後に今川義元。
読んだ後で、再びあれ?と首をかしげた。書名である。『本懐』?「本懐を遂げる」などと用いて、成就とか喜びと親和性の高い言葉である。けれども本書は切腹の話であるから、失敗や無念・残念という感情の支配下にあるはず。真逆ではないか。著者の意図は何なのだ?
暫(しばら)く考えて、少しだけ分かったような気がした。本編の人々は腹を切ることで、何らかの達成を果たしているのだ。彼らの死は先のない「おしまい」ではない。影響に大小の差はあれ、次に繋(つな)がっていく。これは歴史小説家たる著者の神髄に属する、死生観の発露ではないか。
それを思ったとき「まえがき」の位置づけが漸(ようや)く得心できた。著者は6人の切腹にタイトルを付けている。たとえば大石の「親心腹」のように。それは「まえがき」を継承し、書名の『本懐』に集約されていく。何と見事な構成なのだ! 私は感嘆した。
蛇足。今川義元は腹を切っていない。彼の死に本懐はあるのかな? あ、本懐を遂げたかったのは玄広恵探(げんこうえたん)の方なのかな。
ALL REVIEWSをフォローする