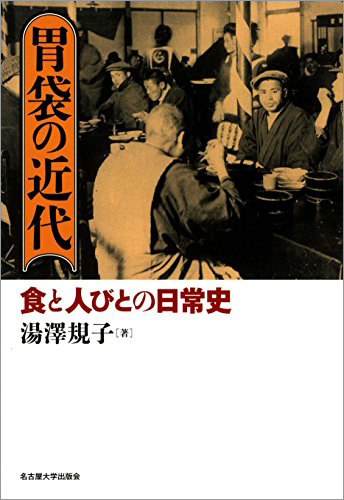書評
『世紀の小説『レ・ミゼラブル』の誕生』(白水社)
細部に宿った「神」を明るみに出す
いまから三二年前の秋、私は翌年に『「レ・ミゼラブル」百六景』というタイトルで世に出る最初の本を書いていたが、そのとき痛感したのは『レ・ミゼラブル』はフランス本国では通俗小説として扱われ、まともな研究の対象になっていないということだった。かくいう私もその影響下にあったため、『レ・ミゼラブル』を完読したのはその三年前でしかなかった。そのとき、もしかすると『レ・ミゼラブル』をフランス語で完読したフランス文学者というのは世界中でも珍しいHAPPY FEWかもしれないという不思議な孤独感を感じたことを記憶している。イギリス生まれのフランス文学者でプリンストン大学教授のデイヴィッド・ベロスもどうやらそうしたHAPPY FEWの一人だったようである。というのもフランス語教師になってからかなり後に山歩きのテントで読む本を探して『レ・ミゼラブル』に行き当たり、「これほど多様な事柄を扱いながら、主題をめぐってこれほど緻密に織り上げられた作品は読んだことがなかった」と感動して、この例外的な作品の徹底研究に乗り出したからである。本書の読み所は後半の作品成立史にあるが、前半の細部への蘊蓄(うんちく)やエピソードも非常におもしろい。
たとえば、元徒刑囚のジャン・ヴァルジャンを善の道へと導いたミリエル司教についての創作エピソード。ユゴーの息子で共和主義者のシャルルが、カトリックの聖職者ではなく「たとえば医者のような目立たない専門職の人物」を配したらいいのではと疑問を呈したのに対して、ユゴーは「わたしの本の純粋で、偉大な、真の聖職者は、今日の生身の司祭どもに対するもっとも痛烈な諷刺(ふうし)ではないか」と答えたが、結果はまさにユゴーの予言通りになった。「一八六二年に『レ・ミゼラブル』初版を読んだカトリックの読者は、ほかの何よりミリエル司教の人物像に激昂(げきこう)した。本物のミオリス司教の甥(おい)は新聞に抗議の手紙を書いている」
今日のわれわれにとっては意外な反応だが、著者によると、それはユゴーがミリエル司教を高潔な人ではなく、公正な人として描いたことから来ているという。「ミリエル司教は、聖職者とはいかなる存在かではなく、正しい人――公正な人間――が、十九世紀フランスの社会慣習のせいで他者がこうむった不公正をどのように軽減しうるのか、というひとつの例なのである」
さすがはベロス教授、これぞ『レ・ミゼラブル』という作品にたいする最も「公正な」批評である。いつの時代もそうだが「公正である」ことほど難しいことはない。ユゴーは『レ・ミゼラブル』を以(もっ)てこの最難題に挑み、なんとか答えを出そうとつとめたのである。
これ以外にも、感心したところは山ほどあるが、その一つがミリエル司教と出会って改悛(かいしゅん)し、マドレーヌ氏となったジャン・ヴァルジャンが模造黒玉(黒ガラス)製造の工場をつくり、地域に奉仕すると同時に巨万の富を築けたのはなぜかという謎。一つはマドレーヌ氏が国産の樹脂に代えて植民地産のシェラックを、人工溶剤のアルコールに代えて天然溶剤のテレビン油を用いてコスト・ダウンに成功したこと、もう一つは元手が一グロス一〇フランなのに六〇フランで卸すことができたこと。ではなにゆえにこれだけの粗利益が確保できたのか? 教授はマドレーヌ氏の工場はスペインが得意先だったと見なして推論する。スペインの港は黒人奴隷の三角貿易の基地だったが、アフリカとの取引に使われた通貨はなんだったのかというと、「じつは、ほとんどがブラックビーズだったのである。またの名をトレードビーズ、あるいは奴隷ビーズともいう」。
もう一つマドレーヌ氏についての疑問は、六三万フランという巨額の貯金をなぜ長期国債に投資しなかったのかというものだが、これについての答えも明快だ。長期国債は非償還債務だったゆえに、投資家は自分の名前を登記簿に書き込み、引き換えに、年金を支給される仕組みになっていたから、身分証明書を持たないマドレーヌ氏はお金をラフィット銀行に預けざるをえなかったのだ。では、逃亡前に銀行からお金を引き出すとき使いにくい紙幣にしたのはなぜか? 六三万フランは銀貨だと三トン以上もの重さになるのに対し、紙幣だと千フラン札で六三〇枚で、大辞典くらいの大きさになるため、地面に簡単に埋められるからである。しかし、ジャン・ヴァルジャンは財産を紙幣で所持していたため隠れ家で門番役の老女にフロックコートの裏地に隠した千フラン札を目撃されてしまい、修道院にコゼットとともに逃げ込まざるをえなくなる。「高額の紙幣――および、それにまつわるうさんくささ――が、『レ・ミゼラブル』の筋を大きく転換させる小説の仕掛けになっているのである」
ことほどさように『レ・ミゼラブル』の細部に宿った「神」を明るみに出した傑作評論。レミゼ・ファン必読の一冊。
ALL REVIEWSをフォローする