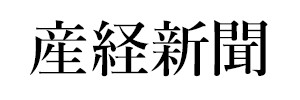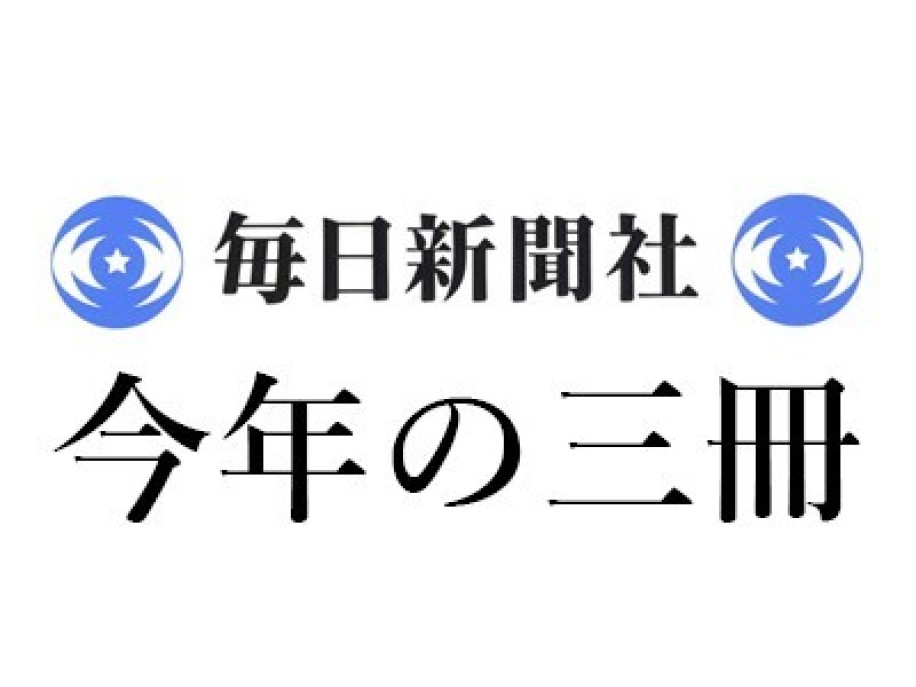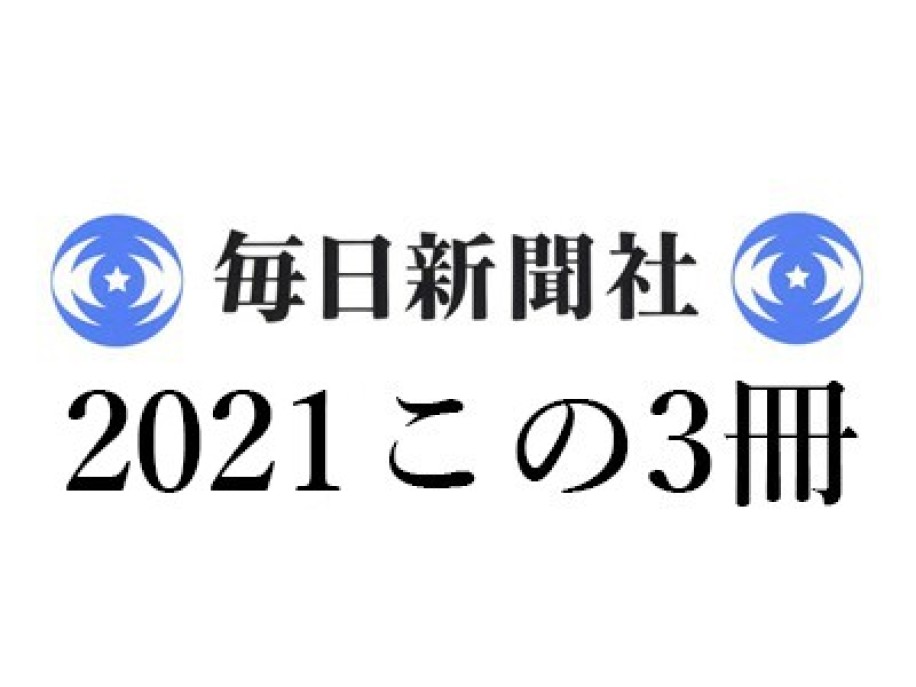書評
『パリの福澤諭吉 - 謎の肖像写真をたずねて』(中央公論新社)
西欧文明との遭遇を活写
明治維新を数年後に控えた文久元(1862)年、徳川幕府はヨーロッパへ使節団を派遣する。支倉常長以来250年ぶりの日本人の欧州訪問である。使節団の目的は、開国派や外国人への攘夷派のテロが横行するなか、安政の条約で約束した江戸と大坂の開市、新潟と兵庫の開港を延期してもらうよう、英仏など6カ国と交渉することだった。この「文久遣欧使節団」36人のなかに、当時27歳の福澤諭吉が含まれていた。諭吉はすでに咸臨丸で訪米していたが、その外国経験はサンフランシスコの風俗や食物などに局限されていた。諭吉が西洋文明の実態と本質に触れ、のちに主著『西洋事情』を書くのは、このときの欧州での実地見聞のおかげなのだ。
本書は、文久遣欧使節としての諭吉のパリにおける一挙手一投足を、膨大な文献調査と実地検証によって跡づけ、『西洋事情』に結晶する近代文明および民主主義との最初の遭遇経験を、きわめて具体的に浮き彫りにしている。
福澤諭吉の慶応義塾創設と並ぶ最大の業績は、日刊紙「時事新報」を創刊したことだ。諭吉の思想の根源には、ジャーナリズムの発達が民主主義を保証するという確信がある。本書の著者もまたパリで20年以上にわたって国際報道に従事した筋金入りの新聞記者である。遠い先輩・福澤諭吉のパリでの日々の経験を生々しく描きだすその筆には、熱いジャーナリスト魂が脈打っている。
鉄道、病院、新聞、国会、株式会社、図書館、すべてが未知の世界で、諭吉は比類なき好奇心に駆られて、西洋文明を丸ごと自分の頭脳と肉体に刻みつけていく。福澤諭吉こそ、精神的にも物質的にも開国を一身に体現した稀有(けう)な日本人であった。その決定的な事実を本書は飽くことなく論証していく。
さらに本書にはミステリー的な謎解きの興味もある。諭吉はパリで3枚の肖像写真を残している。この写真が辿(たど)った波瀾(はらん)万丈の運命も、本書の読み応えを増している。その行方をどこまでも執拗(しつよう)に追う著者の姿勢は、まさに歴史探偵というにふさわしい。
ALL REVIEWSをフォローする