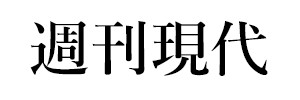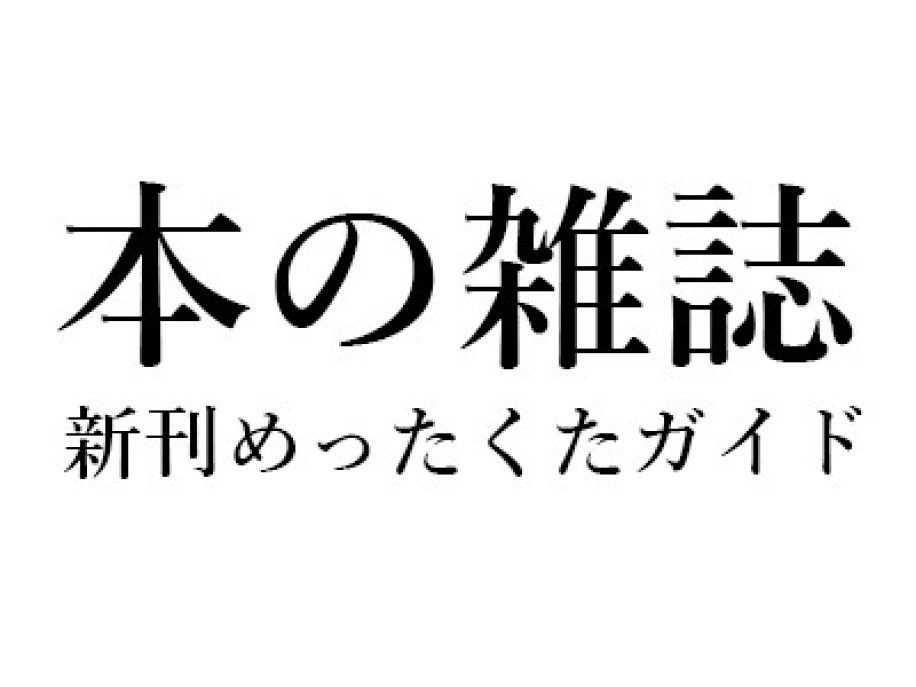書評
『ヒトでなし 金剛界の章』(新潮社)
家族も職も失った男が追いつめられた人々を惹きつけ始める――。世界の本質を抉る長編
京極夏彦の小説は絵解に似ている。中世の僧侶が経典の内容を大衆に説くために絵を代用したことから始まった芸能である。京極作品には文章が見開きに必ず収まるという特徴があるが、これも絵だからだ。絵はぺージをまたぐことができない。その京極の新しい絵解が『ヒトでなし 金剛界の章』である。主人公は、――俺は、ヒトでなしなんだそうだ。
という呟きと共に姿を現す。妻だった人にそう言われたのだ。娘が不慮の死を遂げ、そのために妻との関係も壊れた。職場にも戻れなくなり、辞めさせられた。つまりすべてを失ったのである。そんな〈俺〉が雨の中、とある鉄道の跨線橋(こせんきょう)を渡るところから物語は動き始める。そこで彼は一人の女を見るのだ。女は、橋のフェンスにしがみついていた。金網を乗り越え、今まさに眼下の線路に身を投げようとしている。
〈俺〉はすべてを失って空虚であり、尾田慎吾という名前すらなかなか名乗ろうとしない。ヒトでなしになってしまったからだろう。娘の死を契機として起きたもろもろの出来事によってヒトでなしになったのではなく、自分が最初からヒトでなしだったのだ、ということに尾田は気づく。そして、ヒトでなしとして存在し始めるのである。
自殺志願者の女の次は、旧友の荻野と彼は再会する。荻野もまた多額の負債のため、座して死を待つばかりになっていた。その旧友の思いつきから事態は動き出すが、それは尾田の関知するところではない。ヒトでなしだから関係ないのだ。
このように無となった男の視点から世界を見直す小説である。彼を中心として物事は動く。人死(ひとじ)にまで出るのだが尾田自身は動かない。そこが小説としてはおもしろいのである。ただ漂っているだけなので物語は出発点とはまったく別の場所に行き着く。意外なほど遠くまで連れて行かれるので、読者は驚くはずだ。
冒頭に書いたように京極作品の本質は絵なので、読者に直観の機会を与えることが多い。直感ではなく直観、すなわち物事の本質を発見させるのである。小説の随所で、そうかもしれない、と手を打ちたくなる瞬間が訪れるだろう。それをぜひ、楽しんでもらいたい。
ところで、両界曼荼羅という言葉があるように金剛界は胎蔵界と対になっている。次は胎蔵界の章なのだろうか。金剛界曼荼羅とは世の理を絵図として表したものだが、では次の章では、と今から続刊が楽しみである。
ALL REVIEWSをフォローする