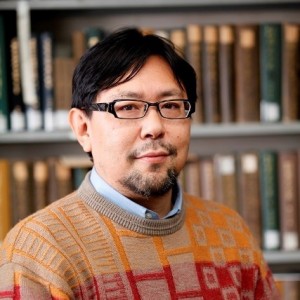書評
『三国志名臣列伝 後漢篇』(文藝春秋)
時代による言葉の差異を物語に生かす手腕が光る
同じ言葉で表記していても、時代が変われば中味は大きく変わる。たとえば鎌倉「幕府」と江戸「幕府」。後者は日本列島全体を支配下に収めていたが、前者が成立したとき、西国への影響力は微弱であった。だが凡庸な歴史研究者は同じ「幕府だから」両者を一括(ひとくく)りにし、その認識を疑わない。中国史でもそう。同じ中国大陸の「王朝」でも、春秋戦国時代の「周」王朝と「漢」とはまるで違う。その差異を物語に生かす方法(海音寺潮五郎や陳舜臣のような大家にも、これはない)こそが、この著者のすごみである。本書はタイトルこそ三国志だが、後漢に仕えた名臣たちの伝記である。全体を通じて「宦官(かんがん)勢力vs.清流派」の対立が軸をなし、採録された人々は清流派の名士である。彼らはさまざまな官職を歴任し、地方で実績を上げながら、中央に登用される。ここが「世襲」の力がとくに強く作用する日本とは異なる。日本の貴族は国司(その第一位の守(かみ)は現在の知事)のような地方官ですら、遙任(ようにん)といって京都に居座った。だから地方の歴史は資料に乏しく、よく分からない。これに対して中国では地方がそれぞれの発展を見せるので、歴史の動きが多様多彩である。
それから「武事有る者は必ず文備有り」(司馬遷『史記』)。本書に描かれる人は、武勲で名を馳(は)せた将帥であっても、みな教養あふれる読書人である。まず文が人の基礎を作り、文に強き者が武でも才能を顕(あらわ)す。ここがわが国と根本的に異なる。日本は文は文、武は武。かつ文より武を上位に置く傾向がある。
天候まで変える軍師が活躍する“ファンタジー三国志”に物足りなくなった人、中国を通じて日本の特徴に思いを致したい人にはぜひ読んでもらいたい。滋味あふれる一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする