書評
『フォックスファイア』(DHC)
ジョイス・キャロル・オーツという作家について考える時、『オン・ボクシング』(中央公論新社)は無視できない一冊だと思う。「殴り合いもしたことのない女にボクシングの何がわかる」、そんないかにも頭と感性の鈍い発言をするオヤジが、この評論集が翻訳された八八年、日本にはうじゃうじゃ存在していたものだ。実際、わたしも当時足繁く通っていた後楽園ホールで、高名なスポーツライター氏に面と向かってそう毒づかれたことがある。しかし、彼はオーツのこの著作を知らなかった。"何かについて語る"という行為で問われるべきは体験ではなく眼力であるという自明の理が、格闘技にも適応されることすら知らなかった。オーツはそういうバカげた状況に常に冷静な怒りを表明する作家なのである。そこで九歳の頃から観戦してきた、男たちの神聖なるスポーツのことを書いてみた。そして、殴り合いの経験を持つ凡百の男性ライターよりも素晴らしいボクシング論をものしたというわけだ。ご苦労なことではある。
怒り。オーツの創作意欲の源泉はそこにある。少女だけで構成された不良集団の生成から消滅までを描いた『フォックスファイア』もその産物。心ない男の悪行や、表面的にしか物事を見ない大人の愚かしさや、貧しい者を踏みつけにする資本家の横暴に、不良少女たちは知性と教養に欠けるがゆえの真っ直ぐな怒りをもって立ち向かっていく。「フォックスファイアは反省しない」 「フォックスファイアは火の玉だ」といったスローガンにふさわしい過激な復讐行為や常軌を逸した冒険の数々。カリスマ的な魅力をまとったリーダーのレッグスを筆頭に、チームの語り部であるマディ、元いじめられっ子、大女、ものすごい美人など、多種多様の少女が結集したフォックスファイアの所行を小気味よく思うと同時に、不安も覚えずにはいられない。人間関係の濃い集団が陥る罠に、彼女たちも早晩つかまってしまうのではないか、と。
自動車を盗んで警察とカーチェイスした挙げ句、レッグスが女子矯正施設に入れらてしまうあたりから雲行きはいよいよ怪しくなってくる。そして、その不安は的中する。フォックスファイアとて、集団の理からは逃れ得ないのだ。集まったものはいつか離散する、集団の求心力が強ければ強いほど離散時の悲劇の度合いは高まる、という理からは。作中、レッグスが心の師と仰ぐ浮浪者のような神父がこう眩く。「個人の怒りでは世の不正を取り除くことは不可能だ」と。では作者は、説明のつかない怒りに突き動かされて面倒ばかりを引き起こすレッグスを、否定的に見ているのだろうか。もちろん、違う。神父の考えは事実かもしれないが、真実はレッグスの側にあるというのがオーツの想いなのだ。それは終章、レッグスにまつわる後日譚にも明らか。あらゆる不正や心ない仕打ちに対して率直な怒りを表明する者の美しさと自由な精神を描いて、この小説は素晴らしい。怒らなくなったら、人間お終いなのである。
怒り。オーツの創作意欲の源泉はそこにある。少女だけで構成された不良集団の生成から消滅までを描いた『フォックスファイア』もその産物。心ない男の悪行や、表面的にしか物事を見ない大人の愚かしさや、貧しい者を踏みつけにする資本家の横暴に、不良少女たちは知性と教養に欠けるがゆえの真っ直ぐな怒りをもって立ち向かっていく。「フォックスファイアは反省しない」 「フォックスファイアは火の玉だ」といったスローガンにふさわしい過激な復讐行為や常軌を逸した冒険の数々。カリスマ的な魅力をまとったリーダーのレッグスを筆頭に、チームの語り部であるマディ、元いじめられっ子、大女、ものすごい美人など、多種多様の少女が結集したフォックスファイアの所行を小気味よく思うと同時に、不安も覚えずにはいられない。人間関係の濃い集団が陥る罠に、彼女たちも早晩つかまってしまうのではないか、と。
自動車を盗んで警察とカーチェイスした挙げ句、レッグスが女子矯正施設に入れらてしまうあたりから雲行きはいよいよ怪しくなってくる。そして、その不安は的中する。フォックスファイアとて、集団の理からは逃れ得ないのだ。集まったものはいつか離散する、集団の求心力が強ければ強いほど離散時の悲劇の度合いは高まる、という理からは。作中、レッグスが心の師と仰ぐ浮浪者のような神父がこう眩く。「個人の怒りでは世の不正を取り除くことは不可能だ」と。では作者は、説明のつかない怒りに突き動かされて面倒ばかりを引き起こすレッグスを、否定的に見ているのだろうか。もちろん、違う。神父の考えは事実かもしれないが、真実はレッグスの側にあるというのがオーツの想いなのだ。それは終章、レッグスにまつわる後日譚にも明らか。あらゆる不正や心ない仕打ちに対して率直な怒りを表明する者の美しさと自由な精神を描いて、この小説は素晴らしい。怒らなくなったら、人間お終いなのである。
初出メディア
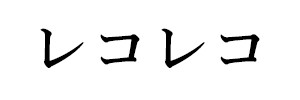
レコレコ(終刊) 2002年10-11月号
ALL REVIEWSをフォローする

































