書評
『馬車の歴史』(平凡社)
以前、大学の保守的体質を皮肉ったつもりらしく、「大学では、とうの昔に馬車というものがこの世から姿を消していても、馬車学の教授がいる限り、馬車学の講座はなくならないだろう」という論説が某新聞に載ったことがあったが、そのころ馬車について調べていた私は、この記事を読んで、そうした無償の研究姿勢こそが本来の大学の姿ではないか、もし本当にそんな素晴らしい教授がいるなら是非とも教えを乞いたいと思ったものである。ところがヨーロッパというのはまったく端倪(たんげい)すべからざる文明圏であり、なんと現実にそうした馬車学の教授が存在していたのだ。近代的な馬車発祥の国、ハンガリーの学者ラスロー・タールがその人で、『馬車の歴史』は世界でもめずらしい広大な視野を持った馬車の通史である。
評者は、日本人の中では比較的馬車に詳しいほうだと自負していたが、本書を通読して自らの無知を思い知らされ、あらためて、古代文明から十九世紀にいたる西欧の歴史のなかで馬車の占める位置の重大さを認識せざるを得なくなった。とりわけ、評者の関心を引いたのは、一般の予想に反して、馬車は、いつの時代でも重量物運搬の道具であるよりも、権力者や富者のステータス・シンボルであったという事実である。太古の昔から人間は自分の足で歩かないということを階級差別化の最大の象徴として考えていたのである。そしてテクノロジーはこの優越意識のためにひたすら奉仕してきたというわけだ。
厄介な技術用語の頻出にもかかわらず、訳文はいたって明快で読みやすい。乗物という人類最大の発明の意味を問いたい人には必読の文献となるだろう。
【この書評が収録されている書籍】
評者は、日本人の中では比較的馬車に詳しいほうだと自負していたが、本書を通読して自らの無知を思い知らされ、あらためて、古代文明から十九世紀にいたる西欧の歴史のなかで馬車の占める位置の重大さを認識せざるを得なくなった。とりわけ、評者の関心を引いたのは、一般の予想に反して、馬車は、いつの時代でも重量物運搬の道具であるよりも、権力者や富者のステータス・シンボルであったという事実である。太古の昔から人間は自分の足で歩かないということを階級差別化の最大の象徴として考えていたのである。そしてテクノロジーはこの優越意識のためにひたすら奉仕してきたというわけだ。
厄介な技術用語の頻出にもかかわらず、訳文はいたって明快で読みやすい。乗物という人類最大の発明の意味を問いたい人には必読の文献となるだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする



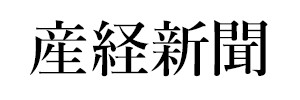












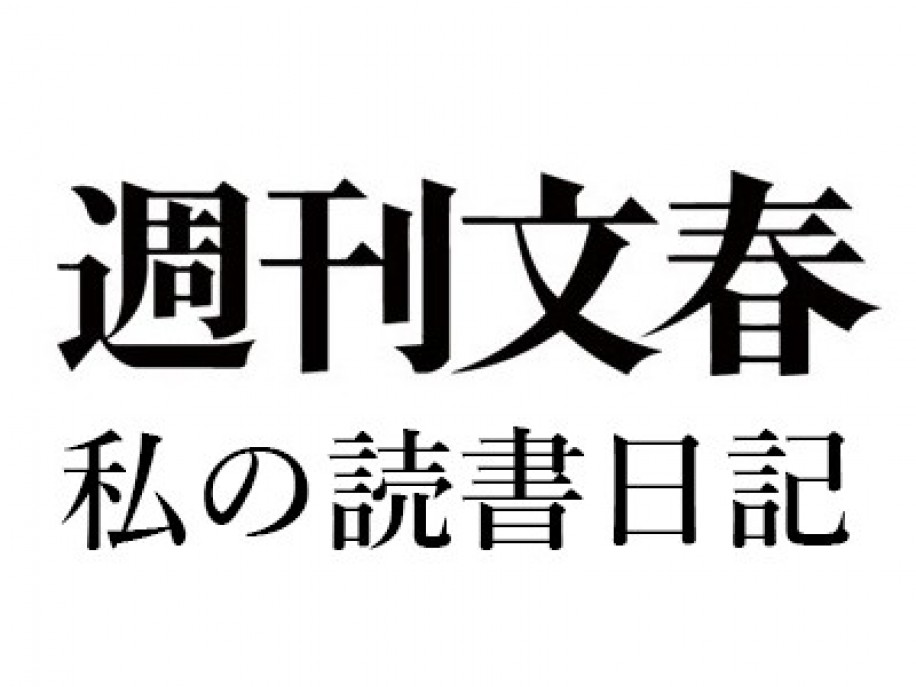
![図書館 愛書家の楽園[新装版]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/5175%2BseB-gL.jpg)





















