後書き
『ピカソとの日々』(白水社)
本書は、二十世紀を代表する芸術家パブロ・ピカソとおよそ十年にわたって人生をともにし、二人の子供をもうけたフランソワーズ・ジローの回想録(カールトン・レイクとの共著)である。原著が出版されたのは一九六四年、最初の邦訳は一九六五年、瀬木慎一氏の訳により『ピカソとの生活』として新潮社から刊行された。この本が世に出てから半世紀以上たったいま、新訳を送り出すには、おもに三つの理由がある。
まずひとつめは、芸術家としてのピカソを知るにあたって他に類のない最良の一次資料であること。
ピカソの身近に暮らした女性は何人かいるが、この本に登場するのは、オルガ、マリー=テレーズ、ドラ、フランソワーズ、ジャクリーヌの五人である。そのなかでも、ピカソの創作活動について深く理解していたという点でフランソワーズにまさる存在はない。
知識偏重の実業家の父のもとで男の子に負けないようスパルタ教育を受けた一人娘のフランソワーズは、法律家をめざしてソルボンヌ大学に進んだが、十代後半から画家を志していた。興味のもてない学科でも苦労なしによい成績を収めてきたが、絵だけはそうはいかなかった、と当人はいう。困難にぶつかったとき、どんなに泣いて頼んでも逃げることを許さず、自ら克服するまで何度でも挑戦させたという父親の教育がそこにも活きたのだろうか、一九四三年五月、占領下のパリでピカソと出会った彼女は、大学を辞めて画家の道に進むと宣言し、家を出て父親と決別する。やがて、一九四六年五月からピカソと暮らしはじめた。
フランソワーズは美術史に通じ、文学や政治についての知識も豊富で、ピカソと親しかったマティス、ブラック、シャガール、ジャコメッティなどの画家や彫刻家、エリュアール、アラゴン、プレヴェール、コクトー、ブルトンといった詩人たちの仕事についてもよく知っていた。さらに、アトリエでは制作を手伝い、創作のアイデアや技法上の工夫について助言し、ときにはモデルを務め、描いている途中の絵を模写するなど、助手としての役割を果たした。芸術以外の面では、画商との交渉や金銭の管理、郵便物の処理など秘書代わりにもなった。《泣く女》のモデルになったドラ・マールも知的な女性ではあったが、ピカソとともに暮らしたことはない。
ピカソが自分の芸術観や技法上のこつ、同時代の画家や彫刻家への評価を語って聞かせるのに彼女はうってつけの存在だった。〈洗濯船〉に住んでいたころの若く貧しい日々、キュビスム時代のブラックとの緊密な共同作業、フランソワーズも交えて親しく交際したマティスへの敬愛の念。ピカソ自身、彼女を自分の生涯の記録者にしようとした気配もあり、過去に暮らした家やアトリエを案内しては懐かしむように思い出を語っている。フランソワーズの優れた記憶力によって再現されるピカソの言葉は、ほかの誰にもなしえない貴重な記録であり、ピカソ研究に欠かせない一級の資料である。
本書のふたつめの価値は、ピカソの私生活がうかがい知れることだ。
フランソワーズとピカソはパリと南仏を行き来しながらともに暮らし、クロードとパロマという二人の子供を育てた。ピカソにとって、家庭らしい家庭を持ったのはフランソワーズと暮らした日々だけだったといってよい。マリー=テレーズはマヤという娘を産んだが同居はせず、絵のモデルとして創作のインスピレーションを与えはしたが、私生活でのピカソは母娘の保護者以上の存在ではなかった。最初の妻となったオルガとのあいだには息子のパウロがいたが、オルガはピカソの芸術を理解しようとせず、上流社会への憧れだけで結びついた結婚生活は早々に破綻した。
フランソワーズとピカソは、同居を始めてから彼が一九四八年の平和会議に出席するためポーランドへ旅行するまで一日も離れたことがないほど身近に暮らしたが、出会いからおよそ十年が過ぎたころ、ピカソは彼女に生活のすべてを乗っ取られ、主導権を握られたという恐怖を感じた。フランソワーズが苦心して築いた家庭という檻に囲い込まれたと感じたピカソが、それを自分の敗北と受け取ったのが二人の別れの一因でもあった。
ピカソは、友人も含めて相手への期待が大きいほど厳しい試練を与え、それに耐えることが自分への愛の証だと考えた。迷信深く、頑固で、人の意見を聞かず、自分の芸術だけを大事にするピカソとの生活はさぞかし苦労が多かったはずだ。
そんな苦労の数々でさえユーモラスに綴られているのは、四十歳も年下だったフランソワーズの若さゆえだろう。彼女の知性とユーモア、自立心がピカソとの年の差を埋め、多くの障害にもめげずに二人が気持ちを通わせ合った日々の暮らしが、ここには生き生きと描かれている。だからこそ、この本の出版にあたってピカソは激しく怒り、世に出させまいとして妨害した。だが、何度訴訟を起こしても、プライバシーの侵害にはあたらないという裁定が出た。そもそも、ピカソの味方をした人たちでさえ、この本の内容が事実に反するとは思わず、ただピカソを不快にさせたくなかっただけなのだ。
「くり返される歴史」とフランソワーズ自身も書いているように、やがて二人に別離が訪れる。
祖母の死をきっかけに、他者への思いやりが決定的に欠けるピカソとの将来に義務以上のものを感じられなくなったフランソワーズはついに別れを決意する。大勢の見知らぬ乗客が行き来するパリの鉄道駅のカフェでたった一人、過去と現在に思いを馳せ、ピカソにとっての自分の存在価値をはかり、この先、二人にどんな生活が待っているかを考える。「大衆」とひとくくりに呼ばれる人びとも、多かれ少なかれ、それぞれの問題を抱え、悩み、苦しんでいる。そのつらさと向き合い、人生という苦杯を飲み干さなければいけない、それが人間の条件だ──そんなふうに他者への共感に気づかされたフランソワーズの姿は読者の胸を打つことと思う。これこそ、あの天才ピカソがなしえなかった、人としての成熟ではないだろうか。
ここに至って、本書は二十世紀を代表する芸術家とその愛人の物語というありがちな枠組みからはずれて、親しい友から聞かされる率直な打ち明け話となり、さらにいえば、読者自身が経験してきた「愛」の話へと変換される。それこそが、新訳を送り出す理由の三つめである。
人を愛したことのある人ならわかるはずだが、欠点や許しがたいところも含めて相手を受け入れるのが愛だといえるかもしれない。フランソワーズが本書の献辞に「パブロへ」と記し、末尾に彼への「感謝の念は尽きることがない」と書いているのは、そんな愛のひとつの形ではないだろうか。
とはいえ、そこできれいに終わるわけではなく、前述のとおり、この本の出版に激怒したピカソは、友人知人、影響力のあるお偉方などを巻き込んで出版の差し止めを求め、フランソワーズと全面対決になった。現在、ピカソの評伝の決定版といえばジョン・リチャードソンの『ピカソ』(全四巻、白水社)である。その著者で、ピカソの友人だったリチャードソンも、最初は巨匠の素顔を暴いたといってフランソワーズを非難したが、のちに意見を変え、評伝の執筆にあたって彼女の文章の多くを引用し、とても役立ったと述べている。
さらに、別離後のピカソは、古い友人のリュック・シモンと結婚していたフランソワーズに復縁を持ちかけ、相手と別れるなら、正式に結婚して子供たちを認知すると約束した。子供たちの将来を考えて申し出を受け入れ、シモンとの離婚手続きを進めていたさなか、ピカソはフランソワーズの後釜にすわったジャクリーヌと極秘のうちに再婚していたという。なんとも腹立たしいピカソの行状である。
それでも、フランソワーズは子供たちがピカソの姓を名乗る権利を裁判で勝ちとった(ジュエリーデザイナーのパロマ・ピカソがそう名乗れるのは母親のフランソワーズがその権利を認めさせたからである。一方、マリー=テレーズの娘のマヤは認知を得られず、ピカソの生前はついに父の姓を名乗ることができなかった)。フランソワーズは自身も画家として成功し、小児麻痺のワクチン開発で有名なジョナス・ソーク博士と再婚して、アメリカに移り住んだ。ピカソと別れてからの暮らしや本書の出版をめぐる争いについては、アリアーナ・S・ハフィントン『ピカソ偽りの伝説』(草思社、一九九一年)にくわしく書かれている。この本もピカソの崇拝者にとってはスキャンダラスで腹立たしい内容に思われたらしく、批判の猛攻撃を浴びた。その『偽りの伝説』によれば、出版禁止の要求が裁判で退けられたあとのある日、ピカソはフランソワーズに電話をかけてきて「きみの勝ちだ」と告げたという。相手を全力で叩きのめそうとしながら、それに打ち勝つ強さをもった相手だけを愛するというピカソの天邪鬼ぶりがここにも表われている。
精神を病んだ最初の妻オルガは一九五五年に病死、ピカソは一九七三年に九十一歳で死去、ドラはピカソより長生きしたものの、死ぬまでピカソのミューズとしての自分を捨てきれず、ほとんど引きこもりのような状態で孤独な晩年を送った(ジェームズ・ロード『ピカソと恋人ドラ』平凡社、一九九九年)。ピカソの死後、マリー=テレーズは首吊り自殺をし、ジャクリーヌは拳銃による自死を選んだ。
こうした事実を見ると、フランソワーズがピカソを「生き延びた」といわれるのにも納得がいく。本書を脚色したジェームズ・アイヴォリー監督の映画『サバイビング・ピカソ』(アンソニー・ホプキンスがピカソを演じている)もおすすめである。サバイブどころか、ピカソよりはるかにアウトリブ(長生き)したフランソワーズは二〇一〇年には日本でも回顧展を開き、あと二年で百歳を迎える(二〇一九年現在)。フランソワーズの著作には、本書のほかに『マティスとピカソ芸術家の友情』(河出書房新社、一九九三年)もある。
プライバシーの侵害だとピカソがあれほど忌避したこの本の存在こそが、ピカソの芸術と人間性を理解するうえでこのうえない手がかりになっているという皮肉──ピカソにまつわるすべてにつきまとうその皮肉さえも包みこむフランソワーズの大きな愛を感じずにいられない。
[書き手]野中邦子(翻訳家)
まずひとつめは、芸術家としてのピカソを知るにあたって他に類のない最良の一次資料であること。
ピカソの身近に暮らした女性は何人かいるが、この本に登場するのは、オルガ、マリー=テレーズ、ドラ、フランソワーズ、ジャクリーヌの五人である。そのなかでも、ピカソの創作活動について深く理解していたという点でフランソワーズにまさる存在はない。
知識偏重の実業家の父のもとで男の子に負けないようスパルタ教育を受けた一人娘のフランソワーズは、法律家をめざしてソルボンヌ大学に進んだが、十代後半から画家を志していた。興味のもてない学科でも苦労なしによい成績を収めてきたが、絵だけはそうはいかなかった、と当人はいう。困難にぶつかったとき、どんなに泣いて頼んでも逃げることを許さず、自ら克服するまで何度でも挑戦させたという父親の教育がそこにも活きたのだろうか、一九四三年五月、占領下のパリでピカソと出会った彼女は、大学を辞めて画家の道に進むと宣言し、家を出て父親と決別する。やがて、一九四六年五月からピカソと暮らしはじめた。
フランソワーズは美術史に通じ、文学や政治についての知識も豊富で、ピカソと親しかったマティス、ブラック、シャガール、ジャコメッティなどの画家や彫刻家、エリュアール、アラゴン、プレヴェール、コクトー、ブルトンといった詩人たちの仕事についてもよく知っていた。さらに、アトリエでは制作を手伝い、創作のアイデアや技法上の工夫について助言し、ときにはモデルを務め、描いている途中の絵を模写するなど、助手としての役割を果たした。芸術以外の面では、画商との交渉や金銭の管理、郵便物の処理など秘書代わりにもなった。《泣く女》のモデルになったドラ・マールも知的な女性ではあったが、ピカソとともに暮らしたことはない。
ピカソが自分の芸術観や技法上のこつ、同時代の画家や彫刻家への評価を語って聞かせるのに彼女はうってつけの存在だった。〈洗濯船〉に住んでいたころの若く貧しい日々、キュビスム時代のブラックとの緊密な共同作業、フランソワーズも交えて親しく交際したマティスへの敬愛の念。ピカソ自身、彼女を自分の生涯の記録者にしようとした気配もあり、過去に暮らした家やアトリエを案内しては懐かしむように思い出を語っている。フランソワーズの優れた記憶力によって再現されるピカソの言葉は、ほかの誰にもなしえない貴重な記録であり、ピカソ研究に欠かせない一級の資料である。
本書のふたつめの価値は、ピカソの私生活がうかがい知れることだ。
フランソワーズとピカソはパリと南仏を行き来しながらともに暮らし、クロードとパロマという二人の子供を育てた。ピカソにとって、家庭らしい家庭を持ったのはフランソワーズと暮らした日々だけだったといってよい。マリー=テレーズはマヤという娘を産んだが同居はせず、絵のモデルとして創作のインスピレーションを与えはしたが、私生活でのピカソは母娘の保護者以上の存在ではなかった。最初の妻となったオルガとのあいだには息子のパウロがいたが、オルガはピカソの芸術を理解しようとせず、上流社会への憧れだけで結びついた結婚生活は早々に破綻した。
フランソワーズとピカソは、同居を始めてから彼が一九四八年の平和会議に出席するためポーランドへ旅行するまで一日も離れたことがないほど身近に暮らしたが、出会いからおよそ十年が過ぎたころ、ピカソは彼女に生活のすべてを乗っ取られ、主導権を握られたという恐怖を感じた。フランソワーズが苦心して築いた家庭という檻に囲い込まれたと感じたピカソが、それを自分の敗北と受け取ったのが二人の別れの一因でもあった。
ピカソは、友人も含めて相手への期待が大きいほど厳しい試練を与え、それに耐えることが自分への愛の証だと考えた。迷信深く、頑固で、人の意見を聞かず、自分の芸術だけを大事にするピカソとの生活はさぞかし苦労が多かったはずだ。
そんな苦労の数々でさえユーモラスに綴られているのは、四十歳も年下だったフランソワーズの若さゆえだろう。彼女の知性とユーモア、自立心がピカソとの年の差を埋め、多くの障害にもめげずに二人が気持ちを通わせ合った日々の暮らしが、ここには生き生きと描かれている。だからこそ、この本の出版にあたってピカソは激しく怒り、世に出させまいとして妨害した。だが、何度訴訟を起こしても、プライバシーの侵害にはあたらないという裁定が出た。そもそも、ピカソの味方をした人たちでさえ、この本の内容が事実に反するとは思わず、ただピカソを不快にさせたくなかっただけなのだ。
「くり返される歴史」とフランソワーズ自身も書いているように、やがて二人に別離が訪れる。
祖母の死をきっかけに、他者への思いやりが決定的に欠けるピカソとの将来に義務以上のものを感じられなくなったフランソワーズはついに別れを決意する。大勢の見知らぬ乗客が行き来するパリの鉄道駅のカフェでたった一人、過去と現在に思いを馳せ、ピカソにとっての自分の存在価値をはかり、この先、二人にどんな生活が待っているかを考える。「大衆」とひとくくりに呼ばれる人びとも、多かれ少なかれ、それぞれの問題を抱え、悩み、苦しんでいる。そのつらさと向き合い、人生という苦杯を飲み干さなければいけない、それが人間の条件だ──そんなふうに他者への共感に気づかされたフランソワーズの姿は読者の胸を打つことと思う。これこそ、あの天才ピカソがなしえなかった、人としての成熟ではないだろうか。
ここに至って、本書は二十世紀を代表する芸術家とその愛人の物語というありがちな枠組みからはずれて、親しい友から聞かされる率直な打ち明け話となり、さらにいえば、読者自身が経験してきた「愛」の話へと変換される。それこそが、新訳を送り出す理由の三つめである。
人を愛したことのある人ならわかるはずだが、欠点や許しがたいところも含めて相手を受け入れるのが愛だといえるかもしれない。フランソワーズが本書の献辞に「パブロへ」と記し、末尾に彼への「感謝の念は尽きることがない」と書いているのは、そんな愛のひとつの形ではないだろうか。
とはいえ、そこできれいに終わるわけではなく、前述のとおり、この本の出版に激怒したピカソは、友人知人、影響力のあるお偉方などを巻き込んで出版の差し止めを求め、フランソワーズと全面対決になった。現在、ピカソの評伝の決定版といえばジョン・リチャードソンの『ピカソ』(全四巻、白水社)である。その著者で、ピカソの友人だったリチャードソンも、最初は巨匠の素顔を暴いたといってフランソワーズを非難したが、のちに意見を変え、評伝の執筆にあたって彼女の文章の多くを引用し、とても役立ったと述べている。
さらに、別離後のピカソは、古い友人のリュック・シモンと結婚していたフランソワーズに復縁を持ちかけ、相手と別れるなら、正式に結婚して子供たちを認知すると約束した。子供たちの将来を考えて申し出を受け入れ、シモンとの離婚手続きを進めていたさなか、ピカソはフランソワーズの後釜にすわったジャクリーヌと極秘のうちに再婚していたという。なんとも腹立たしいピカソの行状である。
それでも、フランソワーズは子供たちがピカソの姓を名乗る権利を裁判で勝ちとった(ジュエリーデザイナーのパロマ・ピカソがそう名乗れるのは母親のフランソワーズがその権利を認めさせたからである。一方、マリー=テレーズの娘のマヤは認知を得られず、ピカソの生前はついに父の姓を名乗ることができなかった)。フランソワーズは自身も画家として成功し、小児麻痺のワクチン開発で有名なジョナス・ソーク博士と再婚して、アメリカに移り住んだ。ピカソと別れてからの暮らしや本書の出版をめぐる争いについては、アリアーナ・S・ハフィントン『ピカソ偽りの伝説』(草思社、一九九一年)にくわしく書かれている。この本もピカソの崇拝者にとってはスキャンダラスで腹立たしい内容に思われたらしく、批判の猛攻撃を浴びた。その『偽りの伝説』によれば、出版禁止の要求が裁判で退けられたあとのある日、ピカソはフランソワーズに電話をかけてきて「きみの勝ちだ」と告げたという。相手を全力で叩きのめそうとしながら、それに打ち勝つ強さをもった相手だけを愛するというピカソの天邪鬼ぶりがここにも表われている。
精神を病んだ最初の妻オルガは一九五五年に病死、ピカソは一九七三年に九十一歳で死去、ドラはピカソより長生きしたものの、死ぬまでピカソのミューズとしての自分を捨てきれず、ほとんど引きこもりのような状態で孤独な晩年を送った(ジェームズ・ロード『ピカソと恋人ドラ』平凡社、一九九九年)。ピカソの死後、マリー=テレーズは首吊り自殺をし、ジャクリーヌは拳銃による自死を選んだ。
こうした事実を見ると、フランソワーズがピカソを「生き延びた」といわれるのにも納得がいく。本書を脚色したジェームズ・アイヴォリー監督の映画『サバイビング・ピカソ』(アンソニー・ホプキンスがピカソを演じている)もおすすめである。サバイブどころか、ピカソよりはるかにアウトリブ(長生き)したフランソワーズは二〇一〇年には日本でも回顧展を開き、あと二年で百歳を迎える(二〇一九年現在)。フランソワーズの著作には、本書のほかに『マティスとピカソ芸術家の友情』(河出書房新社、一九九三年)もある。
プライバシーの侵害だとピカソがあれほど忌避したこの本の存在こそが、ピカソの芸術と人間性を理解するうえでこのうえない手がかりになっているという皮肉──ピカソにまつわるすべてにつきまとうその皮肉さえも包みこむフランソワーズの大きな愛を感じずにいられない。
[書き手]野中邦子(翻訳家)
ALL REVIEWSをフォローする












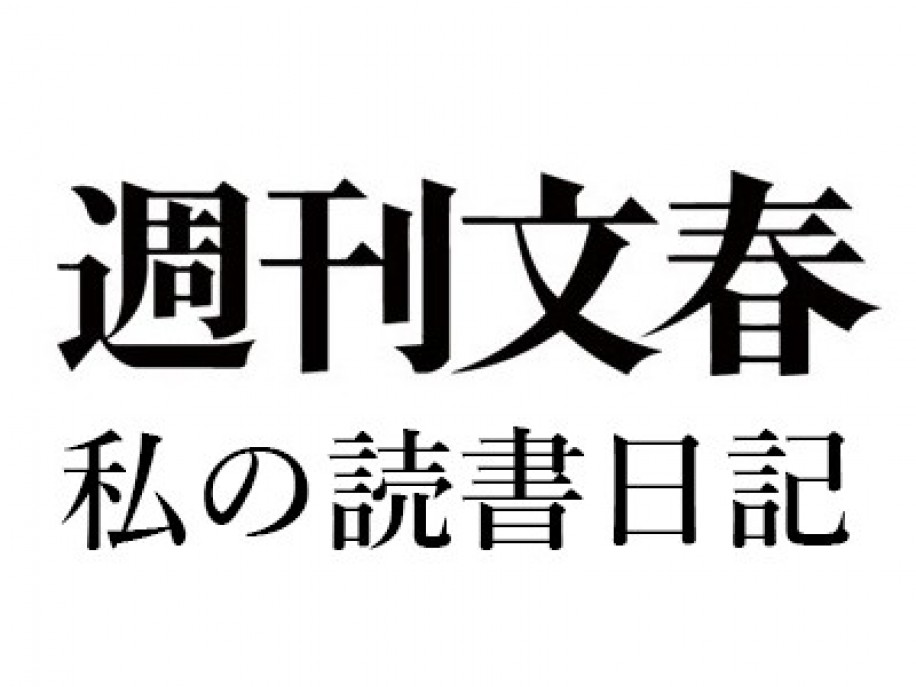
![図書館 愛書家の楽園[新装版]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/5175%2BseB-gL.jpg)



























