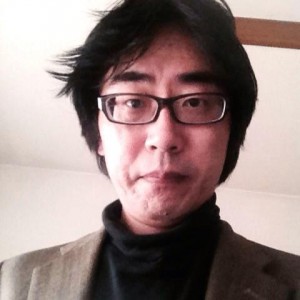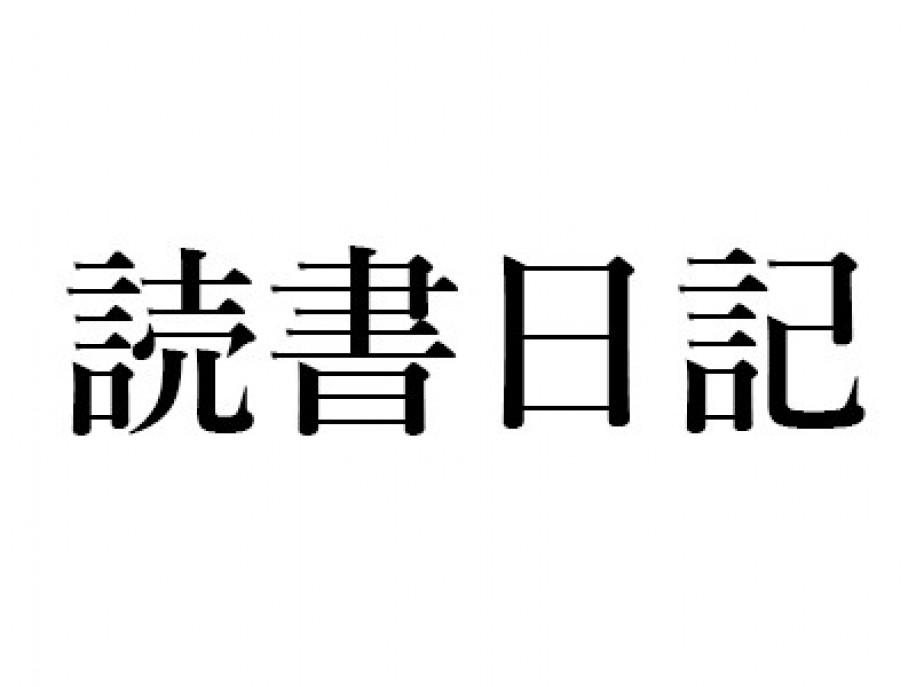書評
『渡良瀬』(新潮社)
歴史の地層と見事な対照
東京での暮らしに見切りをつけ、幼い子供3人を抱えた若い夫婦が、北関東の古河(こが)という町に引っ越してくる。長女は会話がいっさいできなくなる緘黙(かんもく)症に苦しんでおり、長男も川崎病と診断されている。主人公である父親の拓は、長く続けた電気工の仕事で体を弱めている。電気工の仕事のかたわら、家族の陥った困難な状況を題材にして小説を書く作家志望の夫に、妻は不満を募らせている。古河への転居には、そんな家族の立て直しへの期待も掛けられていた。
昭和天皇の危篤が報じられる慌ただしい世相のなか、拓は工業団地での電源切替盤の製造という職を得る。職人肌のベテラン工員がもつ配線の美学を知り、拓はこのあらたな仕事に、次第にやりがいを感じていく。
この小説の背後には、渡良瀬川がゆったりと流れている。万葉集に「許我」として歌われ、室町・戦国時代にかけては古河公方(くぼう)が在所したこの地は、近代には足尾銅山鉱毒事件の舞台となった。渡良瀬川にのぞむ土地が抱える幾重もの歴史の地層は、人体における血管の比喩としても捉えられそうな電気回路というミクロコスモスと、見事な対照をなしている。
佐伯一麦は、デビュー時から実体験を文学作品に刻み込んできた「私小説」の作家である。作家自身にとっても、古河で過ごした時代は大きな過渡期だったようだ。
佐伯は初期の掌編「古河」で、この地を一度描いている。そのときは粗いスケッチにとどまっていたモチーフを、こまやかな筆致で長編として描き直したのが本作である。1993年から96年まで文芸誌「海燕」に連載され、その休刊にともない未完のまま残されていたが、約20年の時を経て完結したのはよろこばしい。
期せずして四半世紀近くを経たことで、この小説は、その間に流れた平成という時代の意味を起源から問い直す作品になった。
初出メディア
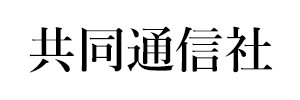
共同通信社 2014年2月13日
ALL REVIEWSをフォローする