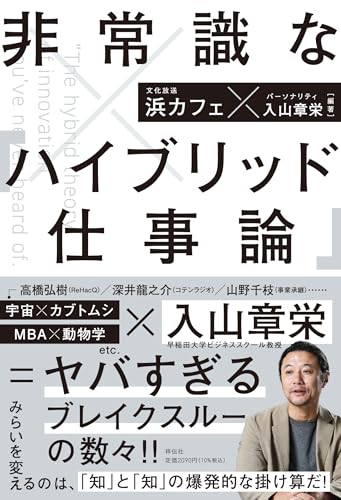前書き
『「お菓子中毒」を抜け出す方法~あの超加工食品があなたを蝕む~』(祥伝社)
超加工食品の危険性に改めて注目が集まっている。
そのなかでも、超加工のお菓子は、
マイルドドラッグのリスクの高さが指摘されている。
超加工のお菓子の、いったい何が問題なのか?
正しい知識と、その依存性から抜け出す正しい方法とは?
これらをまとめた書籍『「お菓子中毒」を抜け出す方法』より、
今回、特別に一部を抜粋して紹介する。
当時、アメリカで話題になっていたマイルドドラッグ(精製度が高く、中毒性のある食品)のリスクは、日本ではほとんど知られていませんでした。
しかし、ふだん口にする食品のなかには、薬物ほどではないものの、たしかに依存症をもたらすものがあり、それによる肥満や生活習慣病の急増が、世界的に問題視され始めていたのです。
私は、日本人もそのリスクを無視できないと、書籍で紹介しました。このときは、数あるマイルドドラッグのなかでも、当時もっとも問題となっていた「砂糖」に焦点を絞り、そのリスクについて紹介したこの本はベストセラーとなりました。
あれから数年。それほど時が経ったわけではありませんが、それでも食品がもたらす中毒性については、さらなる新事実が明らかになってきています。
小麦は麻薬と同等の中毒性を指摘され、私のなかでは「健康のためにはできるだけ避けたほうがいい食品」になりました。白砂糖や果糖、人工甘味料も同様です。
これらほど明確ではありませんが、食塩や油も中毒をもたらします。また、何より、中毒からの脱却にはストレス対策が必須であることも明らかになっています。
今回、「お菓子」をテーマにしたのは、お菓子のほとんどを占めているのが、マイルドドラッグが複数入っている超加工食品で、中毒性が極めて高いからです。もしあなたが「お菓子を食べるのをやめられない」と悩んでいるのであれば、それは意志が強いか、弱いかの問題ではなく、お菓子の中毒に蝕まれているためです。
中毒から脱却するにはコツがあります。本書では、中毒をもたらす犯人(要因)を7つに絞り、それぞれについて、なぜ中毒をもたらすのか、どんなダメージがあるのか、どのように抜け出すのかを紹介しています。
ヒトは発酵食品、塩漬け、燻製、乾燥など、食品を加工して保存食をつくってきました。縄文時代には木の実を加工する技術があったそうですから、飢餓に備えて食品を保存するために、人類は工夫をこらしてきたのでしょう。
こうした加工はシンプルで、自然なものばかりです。こうしてつくられる加工食品は体に害を与えません。発酵食品などはむしろ健康に役立ちます。
ところが、ある時期から高度に加工された食品が急増しました。私は、その境は1970年だと感じています。1971年にはマクドナルドが銀座に第一号店を出店しましたし、カップヌードルもこの年に登場しました。スーパーマーケットの登場、普及もちょうど同じ頃です。
大量生産、薄利多売が求められるようになり、保存性が高く、コストが抑えられる加工食品が次々と開発されました。安価で保存が効き、調理をしなくても食べられる加工食品の便利さは、大衆に受け入れられ、どんどん消費が拡大していったのです。
たしかに、加工食品の登場で私たちの食生活は豊かになりました。ただ、その一方で高度に精製された食品による弊害が、ジワジワと忍び寄っていたのです。
生活習慣病の増加は間違いなく食生活の変化が大きな要因を占めていますし、認知症にも食事が関わっています。加工された不自然な食べ物が増えたことで、こうした病気のリスクが上がりました。
超加工食品のなかでもお菓子は、マイルドドラッグである白砂糖や果糖、人工甘味料、小麦、食塩、油がたっぷりと使われた危険な食べ物です。健康のことを考えるなら、できるだけ食べないほうがいいと私は思っています。どうしてもやめられないのであれば、せめて量を減らして欲しい、そう願ってやみません。
本書がお菓子中毒の危険性について知っていただくきっかけになれば幸いです。
[書き手]白澤卓二(お茶の水健康長寿クリニック院長)
本稿は『「お菓子中毒」を抜け出す方法』(祥伝社)「はじめに」「おわりに」の一部を変更して作成
そのなかでも、超加工のお菓子は、
マイルドドラッグのリスクの高さが指摘されている。
超加工のお菓子の、いったい何が問題なのか?
正しい知識と、その依存性から抜け出す正しい方法とは?
これらをまとめた書籍『「お菓子中毒」を抜け出す方法』より、
今回、特別に一部を抜粋して紹介する。
健康にいいイメージのあのお菓子も、じつは超加工お菓子!
本書のきっかけになったのは、いまから約6年前、2012年に出版された『「砂糖」をやめれば10歳若返る!』(KKベストセラーズ)という書籍です。当時、アメリカで話題になっていたマイルドドラッグ(精製度が高く、中毒性のある食品)のリスクは、日本ではほとんど知られていませんでした。
しかし、ふだん口にする食品のなかには、薬物ほどではないものの、たしかに依存症をもたらすものがあり、それによる肥満や生活習慣病の急増が、世界的に問題視され始めていたのです。
私は、日本人もそのリスクを無視できないと、書籍で紹介しました。このときは、数あるマイルドドラッグのなかでも、当時もっとも問題となっていた「砂糖」に焦点を絞り、そのリスクについて紹介したこの本はベストセラーとなりました。
あれから数年。それほど時が経ったわけではありませんが、それでも食品がもたらす中毒性については、さらなる新事実が明らかになってきています。
小麦は麻薬と同等の中毒性を指摘され、私のなかでは「健康のためにはできるだけ避けたほうがいい食品」になりました。白砂糖や果糖、人工甘味料も同様です。
これらほど明確ではありませんが、食塩や油も中毒をもたらします。また、何より、中毒からの脱却にはストレス対策が必須であることも明らかになっています。
今回、「お菓子」をテーマにしたのは、お菓子のほとんどを占めているのが、マイルドドラッグが複数入っている超加工食品で、中毒性が極めて高いからです。もしあなたが「お菓子を食べるのをやめられない」と悩んでいるのであれば、それは意志が強いか、弱いかの問題ではなく、お菓子の中毒に蝕まれているためです。
中毒から脱却するにはコツがあります。本書では、中毒をもたらす犯人(要因)を7つに絞り、それぞれについて、なぜ中毒をもたらすのか、どんなダメージがあるのか、どのように抜け出すのかを紹介しています。
ヒトは発酵食品、塩漬け、燻製、乾燥など、食品を加工して保存食をつくってきました。縄文時代には木の実を加工する技術があったそうですから、飢餓に備えて食品を保存するために、人類は工夫をこらしてきたのでしょう。
こうした加工はシンプルで、自然なものばかりです。こうしてつくられる加工食品は体に害を与えません。発酵食品などはむしろ健康に役立ちます。
ところが、ある時期から高度に加工された食品が急増しました。私は、その境は1970年だと感じています。1971年にはマクドナルドが銀座に第一号店を出店しましたし、カップヌードルもこの年に登場しました。スーパーマーケットの登場、普及もちょうど同じ頃です。
大量生産、薄利多売が求められるようになり、保存性が高く、コストが抑えられる加工食品が次々と開発されました。安価で保存が効き、調理をしなくても食べられる加工食品の便利さは、大衆に受け入れられ、どんどん消費が拡大していったのです。
たしかに、加工食品の登場で私たちの食生活は豊かになりました。ただ、その一方で高度に精製された食品による弊害が、ジワジワと忍び寄っていたのです。
生活習慣病の増加は間違いなく食生活の変化が大きな要因を占めていますし、認知症にも食事が関わっています。加工された不自然な食べ物が増えたことで、こうした病気のリスクが上がりました。
超加工食品のなかでもお菓子は、マイルドドラッグである白砂糖や果糖、人工甘味料、小麦、食塩、油がたっぷりと使われた危険な食べ物です。健康のことを考えるなら、できるだけ食べないほうがいいと私は思っています。どうしてもやめられないのであれば、せめて量を減らして欲しい、そう願ってやみません。
本書がお菓子中毒の危険性について知っていただくきっかけになれば幸いです。
[書き手]白澤卓二(お茶の水健康長寿クリニック院長)
本稿は『「お菓子中毒」を抜け出す方法』(祥伝社)「はじめに」「おわりに」の一部を変更して作成
ALL REVIEWSをフォローする














![[新版] アロマ調香レッスン:調香師が教えるオリジナル香水の作り方](https://m.media-amazon.com/images/I/4112AmGUBkS._SL500_.jpg)