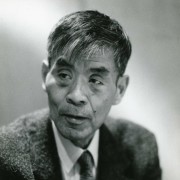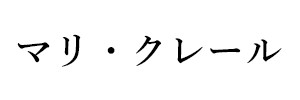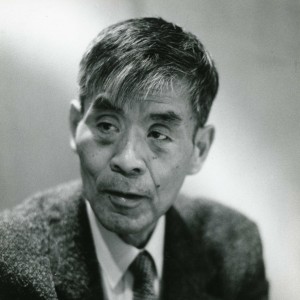書評
『意識の起源史』(紀伊國屋書店)
この本はユングの心理学を深層に向け、どこまでも忠実に掘りさげていって、それを神話の解釈の側からと、個人の乳胎児からの発達心理の側からと、強化し、微細に段階づけしていったものだ。著者自身がこの本の研究の目的が「個人と文化の治療である」と述べているように、あくまでユング派の心理療法の現場にあって治療にあたりながら、患者の精神の障害が神話の奥にある集合的な無意識の表現のどの段階に当っているか、また個人の心理の発達段階のどの辺に障害があったかを、できるかぎり微細に確定しようとするモチーフに貫かれている。この本から、集合的無意識と個人の心理発達の面とから作られた網状の図表を緻密に作りあげるのが、とても治療に大切だということがすぐに理解される。著者がやろうとしたのは、そういうことみたいな気がする。
そのばあいこの本の著者は、神話に記された物語は人間が集合体としてもっている無意識のそれぞれの段階を象徴するものだというユングの立場を前提にしている。そのうえいくつか興味深い著者の原則が見うけられる。まずひとつは太初に集合的な無意識の混沌とした暗い海があり、そこに差し込んでくる光の粒のように個人の意識が芽を出しはじめ、意識からみられた個々の人間が生誕し、成長していったという仮説である。これは仮説というよりイメージといった方がいいくらい鮮やかに感受される。もうひとつ興味深い原則をあげてみると、無意識は男性であれ女性の心理であれ〈女性的〉で、意識は男女を問わず〈男性的〉だという仮説だ。
まずどの民族の神話にも見つけられる天地創造の神話は、集合的な無意識がこの世界の人間の動きを圧倒的に支配している段階に対応しており、創造神話のなかの物語は、人間とその自我が、無意識の支配から生まれ、眼ざめようとして苦悩するさまざまな局面を象徴している。そして個人の心理史では最初期の乳胎児期にあたっている。このとき集合的な無意識の海をたたえた創造の天地は、完全な全体性を象徴する全円によって表示される。この円をめぐって胚芽したばかりの自我の象徴がせめぎあううちに、この全円の内実である子宮と両親は、それぞれお産の象徴を原父と原母の象徴とに解体する運動をはじめる。著者のいうこの段階は、フロイトのいう幼児期の考えられるかぎりのリビドーの変態性をはらんだ時期にあたっている。幼児は近親相姦、獣姦、同性愛などのあらゆる欲求の徴候をあらわす。神話はこの段階で近親相姦、自己射精愛のエピソードを包括すると著者は述べている。
この混沌のなかから、神話は種族の母(太母)の支配を象徴する物語を編みだすようになる。この段階で、まだまだ世界は無意識の圧倒的な力に支配されており、人間の社会では、母権制がしかれている。そして個人の発達史でいえば、母親の授乳によって生命を維持し、男児も女児も母親の乳房を男根とみなし、じぶんたちを、受動的な女性とみなしている時期にあたる。神話はこの段階を、息子=愛人と母神の関係を描いた物語として象徴させると、この本の著者は述べている。
この本のなかでいちばん優れた個所は、この種族の母神(太母)と息子である愛人との関係をあらわすいくつかの神話的な段階を記述しているところだ。はじめに「植物的段階」があって息子=愛人は母権に従順であるが、やがて、反抗者になり、逃亡、抵抗、自己去勢、自殺を企てるようになる。そしてやがて神話的種族の母神(太母)の抑圧をはねのけて自己を確立しようとしはじめる。太母は逆に転落を象徴するように、危険な不実な母となり、「娼婦」の役割を荷うようになる。神殿につかえる巫女、後宮の女性などが神話にあらわれるのは、そのヴァリエーションとしてだ。個人の発達心理のなかでは、良い母親像は意識のなかに、悪い母親像は無意識のなかに押しこめられ、はじめの自己形成期に入る。
この段階の最後に神話は敵対する双生児のエピソードをとどめることがあるが、これは幼小児のなかにある自己意識の分裂や対立を象徴している。
この段階が終ったあとで英雄神話がやってくる。神話の英雄は母権制にとってかわった父権制を制度的に象徴している。またすでに無意識の支配よりも意識的な自我を行動原理として、世界に立ちむかう人間の姿をあらわしている。この本の著者の創見にかかるとおもえるのは、神話の英雄が、父なし子か母なし子を象徴的に負っているという点である。英雄は龍(蛇)と戦って囚われの女性を解放した後に、これを妻とし、「母殺し」と「父殺し」を遂行したのち、つぎの段階の変容神話のなかに入り、内省する心の世界に眼覚める。個人発達心理史的にも、また神話的な段階としても。
【この書評が収録されている書籍】
そのばあいこの本の著者は、神話に記された物語は人間が集合体としてもっている無意識のそれぞれの段階を象徴するものだというユングの立場を前提にしている。そのうえいくつか興味深い著者の原則が見うけられる。まずひとつは太初に集合的な無意識の混沌とした暗い海があり、そこに差し込んでくる光の粒のように個人の意識が芽を出しはじめ、意識からみられた個々の人間が生誕し、成長していったという仮説である。これは仮説というよりイメージといった方がいいくらい鮮やかに感受される。もうひとつ興味深い原則をあげてみると、無意識は男性であれ女性の心理であれ〈女性的〉で、意識は男女を問わず〈男性的〉だという仮説だ。
まずどの民族の神話にも見つけられる天地創造の神話は、集合的な無意識がこの世界の人間の動きを圧倒的に支配している段階に対応しており、創造神話のなかの物語は、人間とその自我が、無意識の支配から生まれ、眼ざめようとして苦悩するさまざまな局面を象徴している。そして個人の心理史では最初期の乳胎児期にあたっている。このとき集合的な無意識の海をたたえた創造の天地は、完全な全体性を象徴する全円によって表示される。この円をめぐって胚芽したばかりの自我の象徴がせめぎあううちに、この全円の内実である子宮と両親は、それぞれお産の象徴を原父と原母の象徴とに解体する運動をはじめる。著者のいうこの段階は、フロイトのいう幼児期の考えられるかぎりのリビドーの変態性をはらんだ時期にあたっている。幼児は近親相姦、獣姦、同性愛などのあらゆる欲求の徴候をあらわす。神話はこの段階で近親相姦、自己射精愛のエピソードを包括すると著者は述べている。
この混沌のなかから、神話は種族の母(太母)の支配を象徴する物語を編みだすようになる。この段階で、まだまだ世界は無意識の圧倒的な力に支配されており、人間の社会では、母権制がしかれている。そして個人の発達史でいえば、母親の授乳によって生命を維持し、男児も女児も母親の乳房を男根とみなし、じぶんたちを、受動的な女性とみなしている時期にあたる。神話はこの段階を、息子=愛人と母神の関係を描いた物語として象徴させると、この本の著者は述べている。
この本のなかでいちばん優れた個所は、この種族の母神(太母)と息子である愛人との関係をあらわすいくつかの神話的な段階を記述しているところだ。はじめに「植物的段階」があって息子=愛人は母権に従順であるが、やがて、反抗者になり、逃亡、抵抗、自己去勢、自殺を企てるようになる。そしてやがて神話的種族の母神(太母)の抑圧をはねのけて自己を確立しようとしはじめる。太母は逆に転落を象徴するように、危険な不実な母となり、「娼婦」の役割を荷うようになる。神殿につかえる巫女、後宮の女性などが神話にあらわれるのは、そのヴァリエーションとしてだ。個人の発達心理のなかでは、良い母親像は意識のなかに、悪い母親像は無意識のなかに押しこめられ、はじめの自己形成期に入る。
この段階の最後に神話は敵対する双生児のエピソードをとどめることがあるが、これは幼小児のなかにある自己意識の分裂や対立を象徴している。
この段階が終ったあとで英雄神話がやってくる。神話の英雄は母権制にとってかわった父権制を制度的に象徴している。またすでに無意識の支配よりも意識的な自我を行動原理として、世界に立ちむかう人間の姿をあらわしている。この本の著者の創見にかかるとおもえるのは、神話の英雄が、父なし子か母なし子を象徴的に負っているという点である。英雄は龍(蛇)と戦って囚われの女性を解放した後に、これを妻とし、「母殺し」と「父殺し」を遂行したのち、つぎの段階の変容神話のなかに入り、内省する心の世界に眼覚める。個人発達心理史的にも、また神話的な段階としても。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする