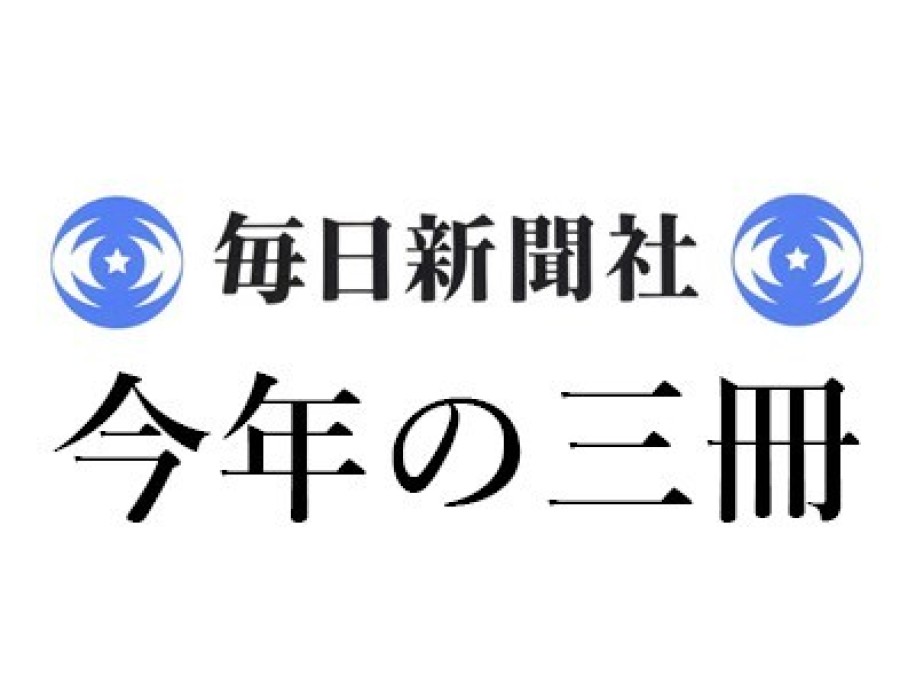書評
『ふつうの相談』(金剛出版)
複数の知を整理する球体の臨床学
東畑氏の著作は、ともかくタイトルが巧い。臨床心理の専門家が書く「ふつうの相談」。なんともそそる書名ではないか。心理療法の専門家は、精神分析なり認知行動療法なりといった専門性に特化した得意分野を持っている。ならば、臨床心理士はみな、それぞれが学んだ専門性(学派知)を常に現場で発揮しているのか。そんなことはない。実は心理士やカウンセラーの相談の多くは、専門性を脇に置いた――親切な素人でも可能な――「ふつうの相談」である。この意外な事実が、本書の発端となっている。
著者が目論むのは、専門的な治療とふつうの相談を架橋するような、大統一理論を作ろうという気宇壮大な試みだ。そのためには、臨床心理全体を俯瞰的に、メタに捉える視点が必要となる。ここで著者は医療人類学者クラインマンの説明モデル理論を援用する。この視点から「ふつうの相談0」の説明モデルを、中井久夫の「個人症候群」概念を例に分析する。それは素人による、友人などの熟知者に対する、世間知にもとづいた相談なのだ、と。
次いで著者は、学派的な心理療法を「カードA」としつつ、そのオルタナティブとして「カードB」、すなわち「ふつうの相談B」を置く。この分類は慧眼で、理解においては学派知に基づきながら、実践に際してはそれを世間知で補正するというスタイルの実践を指す。評者もかつて「理論は過激に、臨床は素朴に」を標榜していたが、発想は同根だ。
著者はさらに「ふつうの相談C」を想定する。ここで新たに提案されるのが「現場知」である。さまざまな制度の理解に加え、それぞれの現場で蓄積されてきたローカルな知を意味する。とあるデイケアがリハビリを標榜しつつ「居る」ことを目標にするような判断は、この現場知による。「ふつうの相談C」とは、「ふつうの相談0」を、現場知によってローカライズしたものを指す。
結論部分、ついに著者は総合的かつ宇宙的視点に到達する。それは「臨床知」の球体である。中心に「ふつうの相談0」があり、緯度に「学派知」を、経度にさまざまな「現場知」を配した球体。すべての臨床実践はこの球体上のどこかに位置づけられる。それが「ふつうの相談A」だ。
著者は書く。「専門知は世間知らずになりやすく、(中略)学派知は暴走しやすく、現場知は閉塞しやすい」と。臨床知は原理主義ではあり得ない。それは専門知、学派知、現場知の入り乱れる濁流だ。だからこそメタ視点からの整理が意味を持つ。球体の臨床学は、そうした複数の知を相対化し、多職種連携によるチーム支援を可能にし、「専門家と当事者を橋渡しする共同創造のための言語を生みだす」。
本書の最大の驚きは、心理臨床を串刺しにする大統一理論が、人間心理のミクロなメカニズムを掘り下げるような形ではなく、素朴とすら思えるような知の分類と、その折衷と総合で可能になってしまった点だ。対人支援に関わるすべての人が、自身の実践を「ふつうの相談A」として球体上にプロットし、それについて語りあうこと。そこから始まる連携こそが、従来よりも相互的で親密な「つながり」を現場にもたらすのではないだろうか。
ALL REVIEWSをフォローする