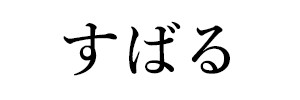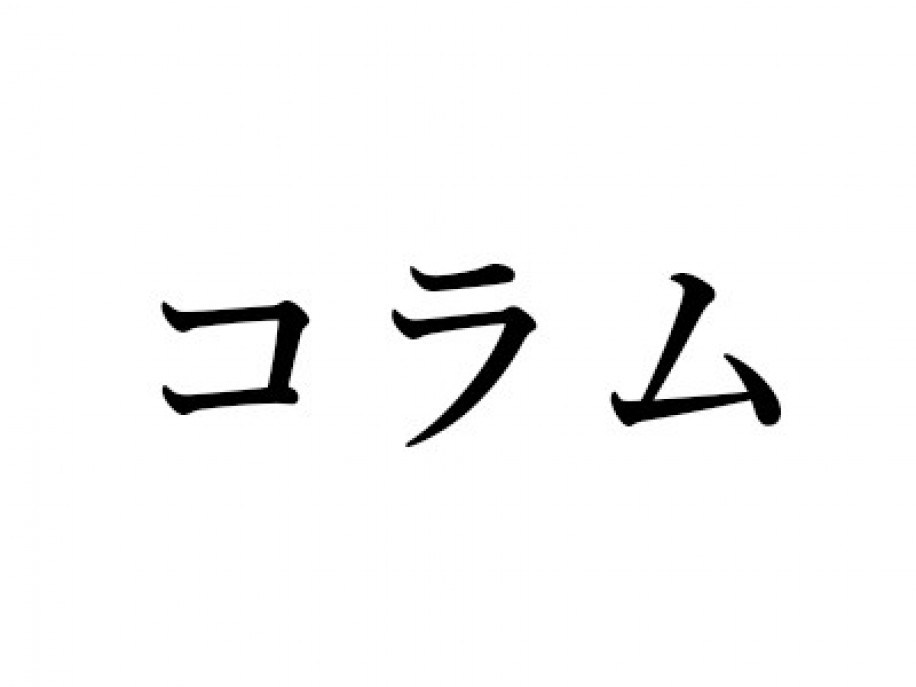書評
『国民のうた』(講談社)
「国民」の再定義
ブルックリン生まれのユダヤ人で国務省の極東課に勤務していた父親と、貧しいポーランド系移民の長女で大使館付きの翻訳士をしていた母親とのあいだに、「かれ」は生まれた。四歳のとき、父親の海外赴任にともなって、共産主義者に「占領」された中国大陸と向かいあう台湾に移住し、以前日本人が住んでいたらしい絨毯敷きの「洋間」と畳のある広壮な屋敷に落ちつくと、「かれ」は、父の周辺に飛びかう北京語や、塀の外から聞こえてくる現地語を耳に入れながら、和書やレコードを通じて「日本語」に触れていく。島で生まれた弟には先天的な障害があって、いっしょに遊ぶこともできなかったから、孤独な生活のなかでアメリカの記憶はますます薄らぎ、島の方が母国に近い存在となっていった。ところが、ここで「かれ」は、思わぬ壁に突き当たるのだ。自分にとって大切な土地がかりそめの滞在地にすぎず、けっして母国にはなりえないことを理解したのである。このときの違和感は、両親の離婚後、母親と弟と三人で暮らしはじめた国籍上の母国でいっそう強まり、日本語への親炙(しんしゃ)に比例して、「かれ」から帰るべき場所を永久に奪いつづける。リービ英雄の『国民のうた』は、そういう複雑な環境で少年期を送った主人公が、ふだんは「施設(ホーム)」に入っている弟と老いた母親が待つワシントンDCへ、クリスマスを過ごすため一年ぶりに帰国した際のほとんど生理的な居心地の悪さを描く表題作と、翻訳を通じて近づきを得た安部公房の、創造の源泉である満州時代の家をその遺族と訪ねる「満州エクスプレス」の二篇で構成された、自伝的作品集である。国籍ではなく言語を生きて「国民」となる以外に自己保全の道がなかった《ユダヤ系日本人》という特異な位置取りによって、また、住むべき場所と住みたい場所が無条件に一致していることを信じて疑わない私たちに自省を迫る消失のエネルギーによって、本書は日本語文学の系譜のなかでも、きわめて個性的な光を放っている。「おれには帰る家がない」との主調音には、捨て子的な吃音より、途方に暮れた子どもに救いの手を差しのべようとする慈しみの色が濃く、それが一分の隙もない日本語の統御と連動して、ときに作者を、広大な満州での自己解放からは遠い、島国的な「うた」への傾斜に向かわせている。しかし「うた」という単語に危険な収束を招きかねない響きがあることくらい作者は承知しているのであり、「国民」の一語に込められた強烈なアイロニーと再定義への意志は、日本語の富として積極的に受け入れなければならないだろう。本書の真の読者は、国籍に依拠する「国民」ではなく、言語を獲得することで「国民」となったすべての人間なのだから。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする