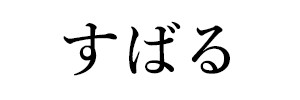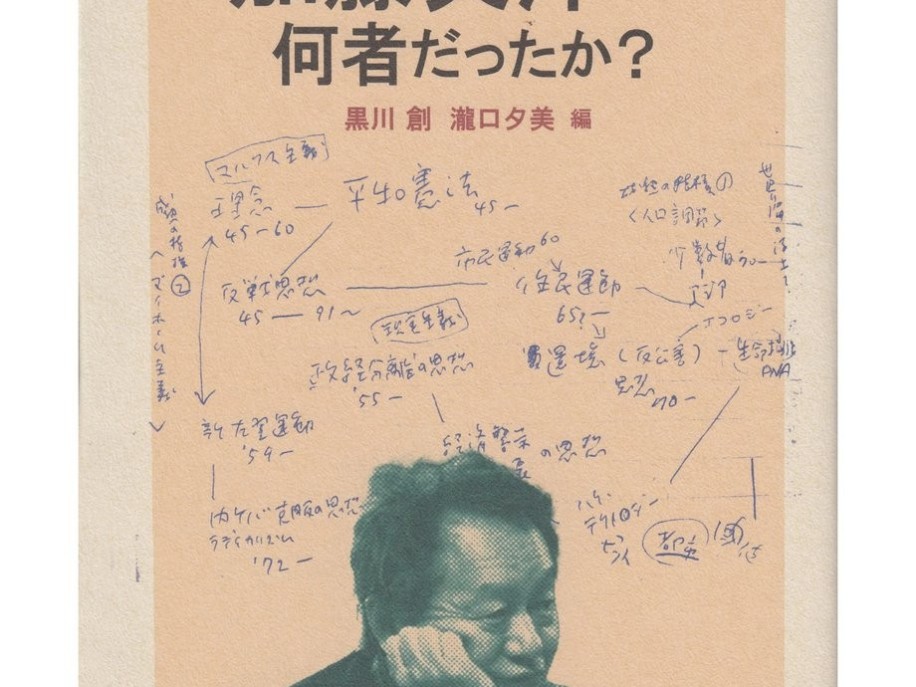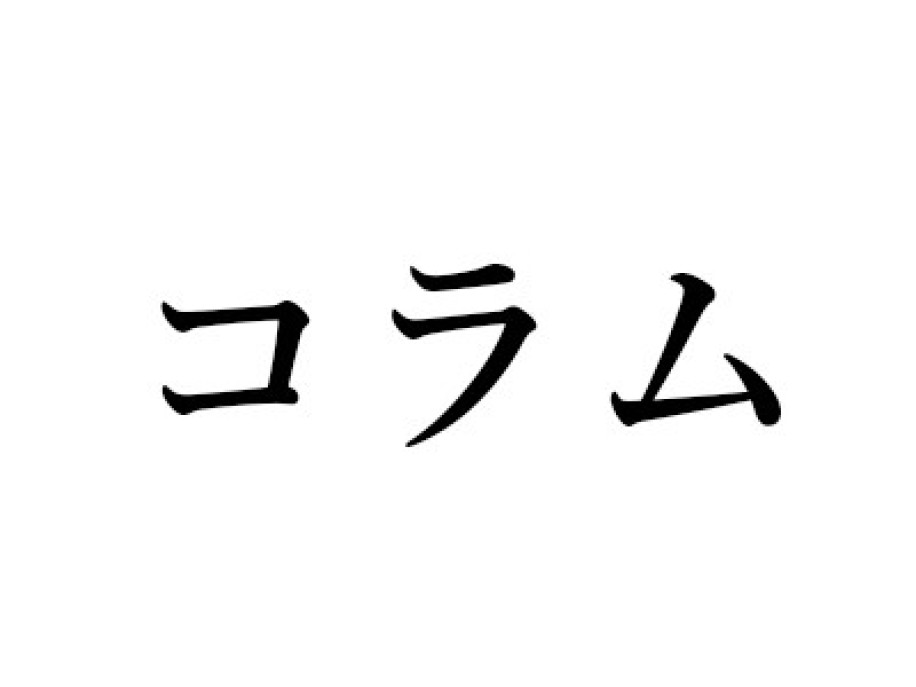書評
『月の家族』(角川書店)
外交としての幼年時代
島尾伸三はもはや写真家というよりひとりの稀有な書き手として強く意識されるべきだろう。物を観ること、考えること、悔いること、そして生きることの等価性を、これほど明度の高い文章で表現しうる人間にふさわしい呼称は、たぶん「作家」以外にないからだ。幼年時代を扱う『月の家族』は、帯にもあるとおり、父、島尾敏雄の代表作『死の棘』の背景をうっすらと感じさせる点でも興味尽きない一書だが、ここに刻みつけられているのは、さまざまな意味で特殊だった両親の存在を、傷を負いながらくぐり抜けてきたひとつのまぎれもない個性である。むろん自伝的な体裁を備えているのだから、親たちの姿は鮮明に映し出されている。小学生の息子が肺炎をこじらせて生死をさまよっているのに、「伸三は諦めた」と言い残して隣の部屋で寝てしまう父に対し、やがて一家を混沌に陥れるだろう母親は、冷たくなりかけた息子の身体を懸命にさすって夜を明かしたという。命の底から眺めた両親のあいだの溝をさりげなく提示し、不思議に屈折した形でしか示されない父親の愛をきちんと受け止めつつも、一方では「後になってからも、あの時に死んでいたら楽だったのにと思うことが幾度もありました」などと、息子は胸の張り裂けるような言葉で複雑な少年の立場を述懐してみせる。
島に移住した父親は、「母のすさんだ精神を穏やかにするため」に、またこの土地で生活するために「外交上」必要だとの理由でカトリックの洗礼を受けた。それとおなじように、ヤマト生まれの少年が島の友人たちとのあいだで見せる過度の明るさも、揺れ動く家庭のなかでみずからの精神の安定を保つために選択せざるをえなかった、ぎりぎりの外交手段ではなかったろうか。島尾伸三の筆は、どこかで無理を重ねていた過去の一瞬一瞬を、古切手の消印を確かめるような慈しみをもって再現する。ひとつの章でまとめられてもいい文章を小刻みに断片化していく独自のスタイルは、『季節風』(みすず書房)および『生活』(同)からさらに深化を遂げて、ここでは写真の助けを借りずに完壁に運用されている。子ども特有の残酷さとそれに倍する思慮の深さが、やわらかい息つぎでとらえられ、暗い予感を覆い隠してくれるのだ。
数ある逸話のなかで、ニワトリに水をやってほしいと妻に頼まれた父親が、コップに水を入れて台所と小屋を往復するという光景に私は感動した。バケツと柄杓があれば一度で済むことに思い至らなかった不器用なその姿は、なんと彼の小説に似ていることだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする