書評
『滞欧日記』(河出書房新社)
その昔、石川淳の『西游日録』を読んだとき、不思議な感じがしたのを覚えている。というのも、ソ連経由で初めてフランスに入った石川淳は、パリの地理など掌を指すごとくに頭に入っておるわいと言わんばかりに地図も案内書もなしにパリを散策してまわっていたからである。彼にとって、初めて見るはずの名所旧跡もすべて、「確認すべきもの」にすぎなかったのである。
こうした昔かたぎの旅行スタイルを、なんの予備知識もなく、ヒョイヒョイと気軽に海外にでかけていく現代の若者のそれと比較すると、昔の西洋文学者はなんとまあ、ブッキッシュな知識をたくさん詰め込んでから外国にでかけたことだろうと、ある種の感慨にひたらざるを得ないが、今回澁澤龍彥の『滞欧日記』を読みはじめて、まずはこの石川淳の旅行スタイルのことを思い出した。
澁澤龍彥は石川淳のような書斎派旅行者の系譜につながる最後の文学者だったから、最初のヨーロッパ旅行に出掛けるよりもはるか以前に、書物と図版を手掛かりにして、想像力だけでほぼ完全にヨーロッパの都市や美術館を「見て」しまっていたにちがいない。だから、のちに実際にその都市や美術館を訪れたときには、それは「確認」でしかなかったのである。
と、ここまで書いて、巻末の巖谷國士氏の解説に目をやったら、私が感じたのと、ほとんど同じ内容のことが書かれていたので驚いた。「確認」という言葉まで同じなので、一瞬絶句して、はて解説を先に読んでいたのかしらと思ったが、やはり絶対に、そんなことはない。どうやら澁澤龍彥の作品に親しんでいる人間は、公開を考えずに私的に書かれた、この『滞欧日記』を前にして、同じような感想を抱くものらしい。すなわち澁澤龍彥の旅先での日常の行動を記録したこの短いテクストに彼の思考法の典型的な現れ、つまりデジャ・ヴュ(既視感)を見てしまうのである。
たとえば一九七〇年の九月から十一月にかけて行われた一回目のヨーロッパ旅行の日記を読んでいくと、『夢の宇宙誌』や『幻想の画廊から』の愛読者ならホテルから美術館に直行した澁澤龍彥が眺めている絵が、彼の著作の中でどんなレフェランスをもっているのか、すぐに察しがつく。うんうん、澁澤さんはあの本で語っているあの画家のあの絵やあの城やあの部屋を見に行っているのだな、という具合である。クラナッハ、アルチンボルド、ルドルフ二世のヴンダー・カマー、そしてもちろんルートヴィッヒ二世のノイシュヴァンシュタインと、ボマルツォの怪物。とりわけノイシュヴァンシュタインについては、「のぼるにつれて城はその偉容を徐々にあらわす」「バスの窓から眺める真っ白な城は、夕日を受けて美しい」というように、またボマルツォの怪物のところでは「ボマルツォの村はまだか、まだか、と固唾をのむ」と、それまでのメモ風の日記に比べて、心の動きを教える文章が目につく。
といっても、澁澤龍彥が自分の本にある絵や庭園だけを見て回っていたかといえば、もちろんそんなことはない。それどころか、未知の画家や庭園を発見して、興奮している箇所も少なくない。クリヴェッリ、アルトドルファー、ロホナー、ストスコップフなど、のちに『幻想の肖像』に結晶する画家たちは、このときに見いだされている。
しかし、いずれにしても一回目の旅行、とりわけその前半は、長年憧れていた美術館や庭園のある都市を次々に遍歴しているという感じで、旅そのものを味わうという風ではない。ところが、一回目の旅行でも、後半、スペインへの旅あたりから少し様子がちがってくる。美術館目当ての旅にはちがいないが、「窓外の景色は異様なり。(……)スペインの夕焼、今日も感動す」「今日も夕焼は素晴らし。最後まで、細い帯のようになって光が残る」というように、自然美にたいする感動が書き記され、それと同時に、旅の中に「人間」もあらわれてくる。「乗合バス式の汽車にのる。最初は非常に混んでいる。しかしスペインの庶民たちの生態が見られて面白い。(……)二人の可愛らしい男の子をつれた、ちょっとゾラの小説の映画にでも出てきそうな人妻あり。こちらをちらちら見る」。あるいは、レストランで「中年のおばさん、ここの席へこい、と親切に言ってくれる。スペイン人の親切は、数え立てれば際限なし」。また、アルハンブラに隣接するジェネラリフェの庭園では、咲き乱れる草木や花々をいちいち書き留めている。「糸杉、夾竹桃(きょうちくとう)、杉、ザクロ、コスモス、シャクナゲ、シャクヤク、野菊、オシロイバナ、バラ、ダリヤ、それに柑橘(かんきつ)類など。細い水流、繊細な噴水、アーチの列柱、小生の好きなものばかり」。要するに、書物を介さない南欧の風物との直接の接触が生まれてきているということである。巖谷國士氏はこの箇所をとらえてこう言っている。「澁澤さんは最初の旅行中、ひょっとするとこのあたりで、いわば『南』を『発見』したのかもしれないな、と思われてくるのである。(……)もともと書斎のユートピストを自任し、一九六〇年代には『夢の宇宙誌』(一九六四年、美術出版社刊)というユートピア的な書物を書いていた澁澤さんは、この旅行中、そのような人工的空間の『確認』に飽きたあげくに、南の乱れさわぐ自然とめぐりあったのである。(……)澁澤龍彥の楽園は『南』にあった」。
巖谷氏はつづけて、南欧に触発されて現れたこうした南方志向がやがて『高丘親王航海記』へと通じていくことを指摘しているが、ここまで解説で言われてしまっては、書評で言うべきことはほとんどなくなってしまう。巖谷國士氏の解説自体が、まさにデジャ・ヴュの感覚を喚起する文章なのである。
だから、ここでは巖谷氏の言及していないこととして、わずかに次の点を指摘するにとどめたい。すなわち、澁澤龍彥と同じように、北方ロマンティスムあるいは古典主義的ユートピアから南方的楽園へという経路で変身をとげた人物が、この本には少なくとも三人登場していると。
一人は、澁澤龍彥の一回目の旅行の際、楯の会の制服を着て見送りにあらわれ、彼が帰国した数週間後に自刃した三島由紀夫である。『暁の寺』と『高丘親王航海記』は南洋一郎で育った世代の南方楽園幻想の二つのヴァージョンだったのかもしれない。
もう一人は、ルートヴィッヒ二世。澁澤龍彥はノイシュヴァンシュタインの内部を見て、「様式的に全く混乱していて、たしかにアラビヤン・ナイトの城を思わせる。東洋趣味(イスラム趣味)がかなり多い」と書いているが、パリ万国博覧会を見て、ワグネリスムからオリエント趣味に宗旨変えをしてしまったルートヴィッヒ二世の変身は、実は、澁澤龍彥自身のそれを予告していたのである。
そして最後の一人とはもちろん、『アジアの不思議な町』(筑摩書房)を上梓(じょうし)した巖谷國士氏そのひとである。『滞欧日記』と『高丘親王航海記』を読んでから、この本をひもとくと、デジャ・ヴュの旅はまさに円環を描いて完結する。澁澤龍彥はどこまでもデジャ・ヴュを誘発する人のようである。
【この書評が収録されている書籍】
こうした昔かたぎの旅行スタイルを、なんの予備知識もなく、ヒョイヒョイと気軽に海外にでかけていく現代の若者のそれと比較すると、昔の西洋文学者はなんとまあ、ブッキッシュな知識をたくさん詰め込んでから外国にでかけたことだろうと、ある種の感慨にひたらざるを得ないが、今回澁澤龍彥の『滞欧日記』を読みはじめて、まずはこの石川淳の旅行スタイルのことを思い出した。
澁澤龍彥は石川淳のような書斎派旅行者の系譜につながる最後の文学者だったから、最初のヨーロッパ旅行に出掛けるよりもはるか以前に、書物と図版を手掛かりにして、想像力だけでほぼ完全にヨーロッパの都市や美術館を「見て」しまっていたにちがいない。だから、のちに実際にその都市や美術館を訪れたときには、それは「確認」でしかなかったのである。
と、ここまで書いて、巻末の巖谷國士氏の解説に目をやったら、私が感じたのと、ほとんど同じ内容のことが書かれていたので驚いた。「確認」という言葉まで同じなので、一瞬絶句して、はて解説を先に読んでいたのかしらと思ったが、やはり絶対に、そんなことはない。どうやら澁澤龍彥の作品に親しんでいる人間は、公開を考えずに私的に書かれた、この『滞欧日記』を前にして、同じような感想を抱くものらしい。すなわち澁澤龍彥の旅先での日常の行動を記録したこの短いテクストに彼の思考法の典型的な現れ、つまりデジャ・ヴュ(既視感)を見てしまうのである。
たとえば一九七〇年の九月から十一月にかけて行われた一回目のヨーロッパ旅行の日記を読んでいくと、『夢の宇宙誌』や『幻想の画廊から』の愛読者ならホテルから美術館に直行した澁澤龍彥が眺めている絵が、彼の著作の中でどんなレフェランスをもっているのか、すぐに察しがつく。うんうん、澁澤さんはあの本で語っているあの画家のあの絵やあの城やあの部屋を見に行っているのだな、という具合である。クラナッハ、アルチンボルド、ルドルフ二世のヴンダー・カマー、そしてもちろんルートヴィッヒ二世のノイシュヴァンシュタインと、ボマルツォの怪物。とりわけノイシュヴァンシュタインについては、「のぼるにつれて城はその偉容を徐々にあらわす」「バスの窓から眺める真っ白な城は、夕日を受けて美しい」というように、またボマルツォの怪物のところでは「ボマルツォの村はまだか、まだか、と固唾をのむ」と、それまでのメモ風の日記に比べて、心の動きを教える文章が目につく。
といっても、澁澤龍彥が自分の本にある絵や庭園だけを見て回っていたかといえば、もちろんそんなことはない。それどころか、未知の画家や庭園を発見して、興奮している箇所も少なくない。クリヴェッリ、アルトドルファー、ロホナー、ストスコップフなど、のちに『幻想の肖像』に結晶する画家たちは、このときに見いだされている。
しかし、いずれにしても一回目の旅行、とりわけその前半は、長年憧れていた美術館や庭園のある都市を次々に遍歴しているという感じで、旅そのものを味わうという風ではない。ところが、一回目の旅行でも、後半、スペインへの旅あたりから少し様子がちがってくる。美術館目当ての旅にはちがいないが、「窓外の景色は異様なり。(……)スペインの夕焼、今日も感動す」「今日も夕焼は素晴らし。最後まで、細い帯のようになって光が残る」というように、自然美にたいする感動が書き記され、それと同時に、旅の中に「人間」もあらわれてくる。「乗合バス式の汽車にのる。最初は非常に混んでいる。しかしスペインの庶民たちの生態が見られて面白い。(……)二人の可愛らしい男の子をつれた、ちょっとゾラの小説の映画にでも出てきそうな人妻あり。こちらをちらちら見る」。あるいは、レストランで「中年のおばさん、ここの席へこい、と親切に言ってくれる。スペイン人の親切は、数え立てれば際限なし」。また、アルハンブラに隣接するジェネラリフェの庭園では、咲き乱れる草木や花々をいちいち書き留めている。「糸杉、夾竹桃(きょうちくとう)、杉、ザクロ、コスモス、シャクナゲ、シャクヤク、野菊、オシロイバナ、バラ、ダリヤ、それに柑橘(かんきつ)類など。細い水流、繊細な噴水、アーチの列柱、小生の好きなものばかり」。要するに、書物を介さない南欧の風物との直接の接触が生まれてきているということである。巖谷國士氏はこの箇所をとらえてこう言っている。「澁澤さんは最初の旅行中、ひょっとするとこのあたりで、いわば『南』を『発見』したのかもしれないな、と思われてくるのである。(……)もともと書斎のユートピストを自任し、一九六〇年代には『夢の宇宙誌』(一九六四年、美術出版社刊)というユートピア的な書物を書いていた澁澤さんは、この旅行中、そのような人工的空間の『確認』に飽きたあげくに、南の乱れさわぐ自然とめぐりあったのである。(……)澁澤龍彥の楽園は『南』にあった」。
巖谷氏はつづけて、南欧に触発されて現れたこうした南方志向がやがて『高丘親王航海記』へと通じていくことを指摘しているが、ここまで解説で言われてしまっては、書評で言うべきことはほとんどなくなってしまう。巖谷國士氏の解説自体が、まさにデジャ・ヴュの感覚を喚起する文章なのである。
だから、ここでは巖谷氏の言及していないこととして、わずかに次の点を指摘するにとどめたい。すなわち、澁澤龍彥と同じように、北方ロマンティスムあるいは古典主義的ユートピアから南方的楽園へという経路で変身をとげた人物が、この本には少なくとも三人登場していると。
一人は、澁澤龍彥の一回目の旅行の際、楯の会の制服を着て見送りにあらわれ、彼が帰国した数週間後に自刃した三島由紀夫である。『暁の寺』と『高丘親王航海記』は南洋一郎で育った世代の南方楽園幻想の二つのヴァージョンだったのかもしれない。
もう一人は、ルートヴィッヒ二世。澁澤龍彥はノイシュヴァンシュタインの内部を見て、「様式的に全く混乱していて、たしかにアラビヤン・ナイトの城を思わせる。東洋趣味(イスラム趣味)がかなり多い」と書いているが、パリ万国博覧会を見て、ワグネリスムからオリエント趣味に宗旨変えをしてしまったルートヴィッヒ二世の変身は、実は、澁澤龍彥自身のそれを予告していたのである。
そして最後の一人とはもちろん、『アジアの不思議な町』(筑摩書房)を上梓(じょうし)した巖谷國士氏そのひとである。『滞欧日記』と『高丘親王航海記』を読んでから、この本をひもとくと、デジャ・ヴュの旅はまさに円環を描いて完結する。澁澤龍彥はどこまでもデジャ・ヴュを誘発する人のようである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
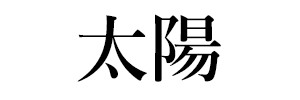
太陽(終刊) 1993年5月
ALL REVIEWSをフォローする









































