書評
『文明に抗した弥生の人びと』(吉川弘文館)
「文明に抗(こう)した」というタイトルに思わず反応した。とても刺激的なフレーズだ。
一般的に弥生文化は、大陸の稲作や金属器が取り入れられてできた新しい文化だと考えられてきた。著者は、そうしたこれまでの「常識」にいくつもの疑問を投げかける。
なぜ、近畿地方の弥生文化には縄文伝統の土偶(どぐう)や石棒(せきぼう)があったのだろう。なぜ、この地域では武器が非実用的な儀器に作り変えられたのか。もしかすると近畿地方の弥生人は、大陸の技術や思想を積極的には受け入れなかったのではないかと。
著者は、水田稲作の開始期における社会のあり方を二つの「生存戦略」として考えている。一つは北部九州にみる武器を中心とした大陸由来の階層化社会だ。これは誰もが理解できる。問題はもう一つの社会のあり方だ。
それは、近畿地方にみる土偶や石棒などの儀礼を介する平等な社会である。稲作が入ってきても土偶や石棒が使われているのは、農耕社会における新しい人間関係の構築には儀礼が欠かせないと考えられたからだという。
この地方には東日本の縄文遺跡に多くみられる定住集落が出現し、ダイズやアズキなどの雑穀の栽培も盛んになる。金属器の流入以降も作られた石器は非実用的で、どこか縄文的な象徴性が見え隠れする。
さらには、大陸由来の鉄製武器も非実用的な儀器に作り変えられる点に、階層化への抵抗や「文明に抗した」強い精神性が読み取れるという。じつに興味深い指摘だ。
そして、この西と東の二つの「生存戦略」が互いに影響し合って、弥生中期には金属器の文化が生まれるのだという。私たちの知っている弥生社会だ。
本書は、これまでの弥生文化の解釈とは異なる視点で論じられているが、多くの資料による分析や解釈には強い説得力を感じる。また文明や文化の背後に、それとせめぎ合う人々のいることを気付かせてくれる点がとても新鮮だ。
【第6回古代歴史文化賞優秀作品賞受賞】
[書き手] 大島 直行 (札幌医科大学客員教授)
一般的に弥生文化は、大陸の稲作や金属器が取り入れられてできた新しい文化だと考えられてきた。著者は、そうしたこれまでの「常識」にいくつもの疑問を投げかける。
なぜ、近畿地方の弥生文化には縄文伝統の土偶(どぐう)や石棒(せきぼう)があったのだろう。なぜ、この地域では武器が非実用的な儀器に作り変えられたのか。もしかすると近畿地方の弥生人は、大陸の技術や思想を積極的には受け入れなかったのではないかと。
著者は、水田稲作の開始期における社会のあり方を二つの「生存戦略」として考えている。一つは北部九州にみる武器を中心とした大陸由来の階層化社会だ。これは誰もが理解できる。問題はもう一つの社会のあり方だ。
それは、近畿地方にみる土偶や石棒などの儀礼を介する平等な社会である。稲作が入ってきても土偶や石棒が使われているのは、農耕社会における新しい人間関係の構築には儀礼が欠かせないと考えられたからだという。
この地方には東日本の縄文遺跡に多くみられる定住集落が出現し、ダイズやアズキなどの雑穀の栽培も盛んになる。金属器の流入以降も作られた石器は非実用的で、どこか縄文的な象徴性が見え隠れする。
さらには、大陸由来の鉄製武器も非実用的な儀器に作り変えられる点に、階層化への抵抗や「文明に抗した」強い精神性が読み取れるという。じつに興味深い指摘だ。
そして、この西と東の二つの「生存戦略」が互いに影響し合って、弥生中期には金属器の文化が生まれるのだという。私たちの知っている弥生社会だ。
本書は、これまでの弥生文化の解釈とは異なる視点で論じられているが、多くの資料による分析や解釈には強い説得力を感じる。また文明や文化の背後に、それとせめぎ合う人々のいることを気付かせてくれる点がとても新鮮だ。
【第6回古代歴史文化賞優秀作品賞受賞】
[書き手] 大島 直行 (札幌医科大学客員教授)
初出メディア
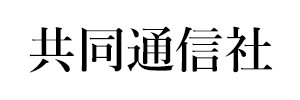
共同通信社 2017年8月
ALL REVIEWSをフォローする

































