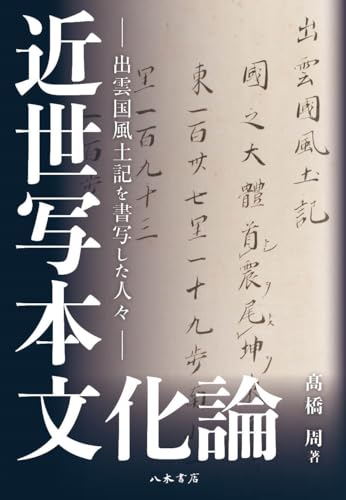書評
『横尾少年―横尾忠則昭和少年時代』(角川書店)
大衆文化(マス・カルチャー)は直接には先端文化(ハイ・カルチャー)を生まない。だが、ある特別の濾過器(ろかき)を通ったとき、前者は凝縮・純化され、一種の聖性を帯びて、突然後者へと変貌(へんぼう)を遂げる。その濾過器を、人は普通、「少年時代」と呼んでいる。
真に天才の名に値する、数少ない画家の一人である横尾忠則が、自らの少年時代を語った本書は、横尾アートの原点を解き明かすと同時に、人生において最も重要な時期である「少年時代」というものの本質を我々に教えてくれる。
二・二六事件の起こった昭和十一年に大阪に生まれた忠則少年は、幼い時、兵庫県西脇の横尾家の養子となる。実父の兄で、子供がなかった養父が、弟の次男を養子に迎え入れたのである。養父母に甘やかされて育った横尾少年は、一人っ子の常として絵本に親しむが、やがて絵本への尋常ならざるのめり込みを示すようになる。『宮本武蔵』などの講談社の絵本を丹念に写すのだが、五歳にして、その絵はすでに完璧な模写となっていた。少年は、絵を写すことで物語世界という異界に入り込み、そこに純粋な喜びを見いだしていたのだ。
こうした異界体験は、ドサ回りの芝居見物でも培われる。ライトで照らし出された書き割りの舞台を見た少年は「あの絵の向こう側になにか別の世界が」「自分の魂のふるさとみたいなものが」あるのではないかと夢想する。異界にこそ、自分の本源があって、「いずれまた向こうの水平線か地平線の彼方へ帰って行く」のではないかというこうした感覚には、ある種のエロティシズムが含まれていた。彼にとって、エロティシズムとは「人間が神に殉ずる一種の至福感」であり、異界感覚への憧(あこが)れにほかならなかった。
呉服屋を営む養父母の家は、この種の異界感覚を養う、キッチュな映像に事欠かなかった。すなわち、呉服の反物のサンプル帳に描かれた芝居絵、商標ラベル、また父親の写真帳にはさまれたフランスのポルノ写真などである。
明石市を爆撃するB29の銀色の機体は少年にSFのようなシュールな感覚を与えた。
しかし、サーベルを下げ、白い馬に乗って帰ってくる自分の姿を夢想していた軍国少年も、戦後になると、一転して『漫画少年』『野球少年』の読者となり、野球選手の写真や絵物語の模写に熱中する。なかでも憧れたのは『少年王者』の山川惣治と、南洋一郎の『新ターザン・バルーバの冒険』の挿絵画家鈴木御水だった。山川惣治の絵の欧亜混血のような美少女や鈴木御水描くジャングルの闇(やみ)に胸をときめかせる一方、郵便切手やスタンプを収集して、まだ見ぬ遠い町、遠い国への憧れを募らせる。画家か郵便配達になりたいと思う。
長ずるに及んでUFOやオカルトを体験した横尾忠則は、少年時代とは前世で体験したもの、つまり異界的なものをラッシュ・フィルムのように一時に「見せられる」期間だと悟るに至る。そして、大衆的で俗っぽいものを一瞬のうちに崇高なものへと変えるには、この少年時代に徹底してこだわることのほかにないと考えるようになる。
本書のタイトルと表紙は言うまでもなく『漫画少年』『野球少年』を模したものであるが、それは横尾忠則のすべての作品と同じようにパロディなどという域をはるかに越えて、「昭和少年時代」という時代の本質を露呈させている。まさに「神の掌にタッチ」したような摩訶(まか)不思議な異界感覚の本である。
【この書評が収録されている書籍】
真に天才の名に値する、数少ない画家の一人である横尾忠則が、自らの少年時代を語った本書は、横尾アートの原点を解き明かすと同時に、人生において最も重要な時期である「少年時代」というものの本質を我々に教えてくれる。
二・二六事件の起こった昭和十一年に大阪に生まれた忠則少年は、幼い時、兵庫県西脇の横尾家の養子となる。実父の兄で、子供がなかった養父が、弟の次男を養子に迎え入れたのである。養父母に甘やかされて育った横尾少年は、一人っ子の常として絵本に親しむが、やがて絵本への尋常ならざるのめり込みを示すようになる。『宮本武蔵』などの講談社の絵本を丹念に写すのだが、五歳にして、その絵はすでに完璧な模写となっていた。少年は、絵を写すことで物語世界という異界に入り込み、そこに純粋な喜びを見いだしていたのだ。
こうした異界体験は、ドサ回りの芝居見物でも培われる。ライトで照らし出された書き割りの舞台を見た少年は「あの絵の向こう側になにか別の世界が」「自分の魂のふるさとみたいなものが」あるのではないかと夢想する。異界にこそ、自分の本源があって、「いずれまた向こうの水平線か地平線の彼方へ帰って行く」のではないかというこうした感覚には、ある種のエロティシズムが含まれていた。彼にとって、エロティシズムとは「人間が神に殉ずる一種の至福感」であり、異界感覚への憧(あこが)れにほかならなかった。
呉服屋を営む養父母の家は、この種の異界感覚を養う、キッチュな映像に事欠かなかった。すなわち、呉服の反物のサンプル帳に描かれた芝居絵、商標ラベル、また父親の写真帳にはさまれたフランスのポルノ写真などである。
明石市を爆撃するB29の銀色の機体は少年にSFのようなシュールな感覚を与えた。
しかし、サーベルを下げ、白い馬に乗って帰ってくる自分の姿を夢想していた軍国少年も、戦後になると、一転して『漫画少年』『野球少年』の読者となり、野球選手の写真や絵物語の模写に熱中する。なかでも憧れたのは『少年王者』の山川惣治と、南洋一郎の『新ターザン・バルーバの冒険』の挿絵画家鈴木御水だった。山川惣治の絵の欧亜混血のような美少女や鈴木御水描くジャングルの闇(やみ)に胸をときめかせる一方、郵便切手やスタンプを収集して、まだ見ぬ遠い町、遠い国への憧れを募らせる。画家か郵便配達になりたいと思う。
長ずるに及んでUFOやオカルトを体験した横尾忠則は、少年時代とは前世で体験したもの、つまり異界的なものをラッシュ・フィルムのように一時に「見せられる」期間だと悟るに至る。そして、大衆的で俗っぽいものを一瞬のうちに崇高なものへと変えるには、この少年時代に徹底してこだわることのほかにないと考えるようになる。
本書のタイトルと表紙は言うまでもなく『漫画少年』『野球少年』を模したものであるが、それは横尾忠則のすべての作品と同じようにパロディなどという域をはるかに越えて、「昭和少年時代」という時代の本質を露呈させている。まさに「神の掌にタッチ」したような摩訶(まか)不思議な異界感覚の本である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする