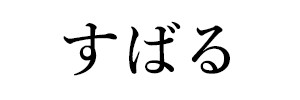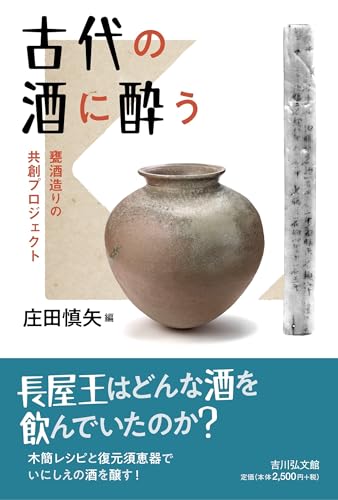書評
『ピカソ・ジャコメッティ・ベイコン』(人文書院)
現在形で息づく対話
闘牛のように激しく、熾火(おきび)のように静かなあの自伝的散文、『成熟の年齢』で知られる詩人ミシェル・レリスは、自身の創作と密接にかかわる少数の存在に寄りそって思考を熟成させていく優れた美術批評家でもあった。本書はレリスの「人と作品」にとりわけ甚大な影響を及ぼした芸術家のうちの三人、すなわちピカソ、ジャコメッティ、ベイコンに的をしぼって編まれた、日本版オリジナルの美術論集成である。偉大な芸術家と親交をむすぶには、いくつもの出会いの偶然が必要となる。レリスにとって幸運だったのは、妻のルイズがピカソの画商であるカーンワイラーの義理の娘で、しかも彼の後を継ぎ、今世紀を代表する芸術家を幅ひろく扱う画廊の経営にあたっていたことである。おかげで詩人は、これら得難い才能の持ち主たちと日々接する機会に恵まれていたのだが、すべてのつきあいが画廊を通じて生まれたわけではないし、そもそもレリスがこうした特権を無節操に行使するジャーナリスティックな駄文を書き連ねることはなかった。
三人の天才の仕事を前にレリスが賛嘆してやまないのは、作品が発している圧倒的な「存在感」である。一枚の絵画が、一体の塑像が、見る者に否応なく、即座に感じさせる強烈なリアリティ。画家の、彫刻家の手によって異化され、いままさにそこにあるという現在形の命を吹き込んでくる「現実」。ベイコンに寄せた言葉を借りるなら、「それは、無機物に限らず、私が眼前にする生き物の存在とも異なりながら、しかも私にとって生きているように思われる存在」であって、レリスはともすれば死に走りかねない――じっさい彼は自殺未遂を経験している――夢想、幻覚への傾斜から、作品だけに付与されたよりいっそう強固な「現実」にしがみつくことで逃れていたようだ。
もっともレリスの文章には、対象の個性に応じた微妙な振幅がある。ピカソに対しては、無条件の信頼と敬意にくわえてほとんど肉感的とも受け取れる言葉が、ジャコメッティに対しては、伴走する盟友ならではの適度な距離と、空間を切り裂く「鉱物」を思わせる断章風の評言が、そしてベイコンに対しては、画布の前で見舞われる途方もない緊張感をそのまま刻みつけた心の震えが。図式に則って綴られたのでも安手の共感に流されたのでもない、真摯な対話がここにはある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする