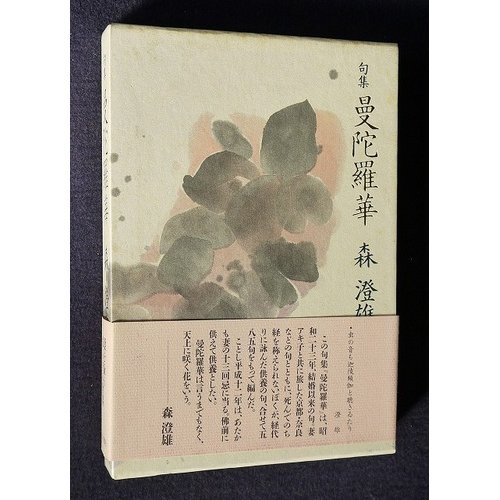解説
『式子内親王』(筑摩書房)
短歌についてあれこれと、インタビューを受けることがある。そういうとき、例外なくなされる質問があって「ああ、またか」と思ってしまう。たいていのインタビュアーは、それが最も重要な質問であるかのように、丁寧にタイミングをみはからって切り出してくる。
「ええっと、ところでですね、可能なかぎり正直に言っていただきたいのですが……」
「あの、最後にひとつよろしいですか。実は今日はこのことをうかがいたくて」
「大変失礼ですけれども……」
インタビューというものに慣れないころは、こういう言葉を聞くたびにドキッとしていた。何を聞かれるのだろう。
「あなたにとって短歌とは何ですか?」
そんなむずかしいことだったら、困るなあ。ひとことで言えないなあ。哲学者じゃないもんね……などと頭のなかで勝手に困っていると、相手は意を決したように質問をしてくる。
「あなたの作る恋の歌、あれ、全部ほんとうにあったことなんですか」
は?
「具体的にどうなんでしょう。やっぱり体験がモトになっているんでしょうか」
ほ?
「たとえばですね、実際にカンチューハイニ本飲んだ男にプロポーズされたとか」
ひええっ。
信じられないかもしれないが、つまり、そういうことなのである。いちばん聞きたいことというのは。
今では私も慣れてしまって、
「うーん、全部がほんとうではないし、全部が嘘ってわけでもないですね」という、わかったようなわからないような、もっともらしいようなもっともらしくないような、お決まりの答えで対応する。さらに丁寧に、
「ほんとうと嘘の混ざりぐあいっていうのも、一首ずつ違いますし」などと付け加えて、ますますわけをわからなくしてしまうこともある。それで不満げな顔をされたら、
「ただ、嘘一〇〇パーセントの歌っていうのは、ないように思います、私の場合は」というぐらいまでは答えられる。これも、お決まりのパターンではあるけれど。
が、慣れないころは、ほんとうに不思議に思って、インタビュアーと議論してしまったこともある。その人があまりにしつこく「嘘ほんと問題」にこだわり、「男が実在の人物なら、その人にもインタビューしたい」とまで言うので、私のほうが逆に尋ねてしまった。
「で、確かめてどうするんです? そのことと、歌のよしあしと、何か関係あるんでしょうか」
短歌にとって「嘘ほんと問題」が大切だとしたら、それは「事実か否か」ではなく「心がほんものか否か」という点においてではないだろうか。そしてそのことは、作者の身辺を見るのではなく、ただ作品を見ることによってしか確かめられない、と思う。
式子内親王は、数多くの恋の歌を残した。が、具体的な相手というのは、はっきりとは確かめられていない。そのことが、後の世にさまざまな憶測を呼び「定家葛伝説」という藤原定家との恋愛譚まで生まれた。相手がいたとかいないとか、誰それではないかとか言われるたびに、あの世で式子内親王はつぶやいているのではないだろうか。
「ああ、またか」と。
たとえば、絶唱といっていいこれらの歌を読んで、恋を知らない女性によって歌われたと思う人がいたら、ヘンである。
「よほどの内的真実が作用しない限り到底うみ出し得ない力がこもっている。」という馬場あき子の言葉に、つきるのではないだろうか。この言葉はまた、式子内親王の恋の歌への最大級の賛辞でもあるだろう。
もちろん、作者がどんな人生を歩んだかということは、知れば鑑賞のうえで大いに役立つ。が、それも「事実か否か」のレベルでとどまっていたのでは、何の意味もない。
評伝から何を読みとり、作品を感じる感じかたを、いかに深めるか。本書は、その鮮やかな実践例であるとも言える。
この一首を、「春の終わりをみつめると共に、一つの時代の終焉をもしみじみ感じていた」というところまで鑑賞するには、作者の生きた時代や、境遇を重ねあわせる必要があるだろう。
右の歌にも使われているが、式子内親王の歌にしばしば登場する〈詠(なが)め〉という語。それをキーワードにし、美意識や作歌姿勢、ひいては時代の中における生き方にまで広げてゆくくだりも、実に興味深い。
式子内親王にとって「その人生にも、作品にも深い影響の影を落している三つの夏のできごと」を、馬場あき子は指摘する。その上であらためて式子内親王の夏の歌を読むと、知らなかったとき以上の重みを、言葉が持ちはじめることに気づく。たとえば時鳥というのは、彼女にとっては辛い季節を思いださせる鳥であるのだなあ、と。すると「ながむる」の意味あいも、微妙に影を深くする。
評伝を通して、作者の「心のほんとう」の部分に迫ることが肝要なのだ。
「もしもし、このときほんとうに時鳥は鳴いたんでしょうか。どんな大きさでした?」と本人に尋ねたところで、何の収穫もない。
歌の内容と事実の関係を確かめることと、歌の心と人生の関係を読みとることとは、似ているようで、まるで違う。
この一首の心に触れて馬場あき子は「待つとなく待たれているものは、待つといいきる以上に切実に待つ思い」であると感じた。あきらかに自分が待っていておかしくない状況で待っているのと、待っていてよいのかさえわからない状況で待っているのとでは「待つ」ことの切実さは、確かに異なる。そしてそこから馬場あき子は「式子にとって、『待つ』ということは、生きるための方便であったかもしれない。もし、式子が待つ心の緊張を失ったなら、全く生きながらむくろと化してしまったろう。」と、彼女の人生を読みとる。
讃岐・小侍従といった一世代先輩の歌人や、宮内卿・俊成卿女ら一世代後輩の歌人たちとの比較も、大いにうなずかせられる。やはりここでも、源平争乱期に、昏い青春の谷間を持ったことが、作品理解に役立てられている。
このように第二部「式子内親王の歌について」で、次々と展開される、はっとするような鑑賞。これは、第一部「式子内親王とその周辺」を、じっくりくぐり抜けてきた読者にとって、まことに説得力のあるものだ。一部でしこまれた薬が、二部で効き目をいかんなく発揮するのである。
評伝と作品理解のとてもいい関係を、はからずも本書は教えてくれる。事実から先の真実を読みとることが、大切なのだ。
「ええっと、ところでですね、可能なかぎり正直に言っていただきたいのですが……」
「あの、最後にひとつよろしいですか。実は今日はこのことをうかがいたくて」
「大変失礼ですけれども……」
インタビューというものに慣れないころは、こういう言葉を聞くたびにドキッとしていた。何を聞かれるのだろう。
「あなたにとって短歌とは何ですか?」
そんなむずかしいことだったら、困るなあ。ひとことで言えないなあ。哲学者じゃないもんね……などと頭のなかで勝手に困っていると、相手は意を決したように質問をしてくる。
「あなたの作る恋の歌、あれ、全部ほんとうにあったことなんですか」
は?
「具体的にどうなんでしょう。やっぱり体験がモトになっているんでしょうか」
ほ?
「たとえばですね、実際にカンチューハイニ本飲んだ男にプロポーズされたとか」
ひええっ。
信じられないかもしれないが、つまり、そういうことなのである。いちばん聞きたいことというのは。
今では私も慣れてしまって、
「うーん、全部がほんとうではないし、全部が嘘ってわけでもないですね」という、わかったようなわからないような、もっともらしいようなもっともらしくないような、お決まりの答えで対応する。さらに丁寧に、
「ほんとうと嘘の混ざりぐあいっていうのも、一首ずつ違いますし」などと付け加えて、ますますわけをわからなくしてしまうこともある。それで不満げな顔をされたら、
「ただ、嘘一〇〇パーセントの歌っていうのは、ないように思います、私の場合は」というぐらいまでは答えられる。これも、お決まりのパターンではあるけれど。
が、慣れないころは、ほんとうに不思議に思って、インタビュアーと議論してしまったこともある。その人があまりにしつこく「嘘ほんと問題」にこだわり、「男が実在の人物なら、その人にもインタビューしたい」とまで言うので、私のほうが逆に尋ねてしまった。
「で、確かめてどうするんです? そのことと、歌のよしあしと、何か関係あるんでしょうか」
短歌にとって「嘘ほんと問題」が大切だとしたら、それは「事実か否か」ではなく「心がほんものか否か」という点においてではないだろうか。そしてそのことは、作者の身辺を見るのではなく、ただ作品を見ることによってしか確かめられない、と思う。
式子内親王は、数多くの恋の歌を残した。が、具体的な相手というのは、はっきりとは確かめられていない。そのことが、後の世にさまざまな憶測を呼び「定家葛伝説」という藤原定家との恋愛譚まで生まれた。相手がいたとかいないとか、誰それではないかとか言われるたびに、あの世で式子内親王はつぶやいているのではないだろうか。
「ああ、またか」と。
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする
忘れてはうちなげかるる夕べかな我れのみ知りて過ぐる月日を
恋ひ恋ひてそなたに靡く煙あらば云ひし契の果とながめよ
たとえば、絶唱といっていいこれらの歌を読んで、恋を知らない女性によって歌われたと思う人がいたら、ヘンである。
「よほどの内的真実が作用しない限り到底うみ出し得ない力がこもっている。」という馬場あき子の言葉に、つきるのではないだろうか。この言葉はまた、式子内親王の恋の歌への最大級の賛辞でもあるだろう。
もちろん、作者がどんな人生を歩んだかということは、知れば鑑賞のうえで大いに役立つ。が、それも「事実か否か」のレベルでとどまっていたのでは、何の意味もない。
評伝から何を読みとり、作品を感じる感じかたを、いかに深めるか。本書は、その鮮やかな実践例であるとも言える。
花は散りてその色となくながむればむなしき空に春雨ぞ降る
この一首を、「春の終わりをみつめると共に、一つの時代の終焉をもしみじみ感じていた」というところまで鑑賞するには、作者の生きた時代や、境遇を重ねあわせる必要があるだろう。
右の歌にも使われているが、式子内親王の歌にしばしば登場する〈詠(なが)め〉という語。それをキーワードにし、美意識や作歌姿勢、ひいては時代の中における生き方にまで広げてゆくくだりも、実に興味深い。
時鳥鳴つる雲をかたみにてやがてながむる有明の空
式子内親王にとって「その人生にも、作品にも深い影響の影を落している三つの夏のできごと」を、馬場あき子は指摘する。その上であらためて式子内親王の夏の歌を読むと、知らなかったとき以上の重みを、言葉が持ちはじめることに気づく。たとえば時鳥というのは、彼女にとっては辛い季節を思いださせる鳥であるのだなあ、と。すると「ながむる」の意味あいも、微妙に影を深くする。
評伝を通して、作者の「心のほんとう」の部分に迫ることが肝要なのだ。
「もしもし、このときほんとうに時鳥は鳴いたんでしょうか。どんな大きさでした?」と本人に尋ねたところで、何の収穫もない。
歌の内容と事実の関係を確かめることと、歌の心と人生の関係を読みとることとは、似ているようで、まるで違う。
桐の葉も踏み分けがたくなりにけりかならず人を待つとなけれど
この一首の心に触れて馬場あき子は「待つとなく待たれているものは、待つといいきる以上に切実に待つ思い」であると感じた。あきらかに自分が待っていておかしくない状況で待っているのと、待っていてよいのかさえわからない状況で待っているのとでは「待つ」ことの切実さは、確かに異なる。そしてそこから馬場あき子は「式子にとって、『待つ』ということは、生きるための方便であったかもしれない。もし、式子が待つ心の緊張を失ったなら、全く生きながらむくろと化してしまったろう。」と、彼女の人生を読みとる。
讃岐・小侍従といった一世代先輩の歌人や、宮内卿・俊成卿女ら一世代後輩の歌人たちとの比較も、大いにうなずかせられる。やはりここでも、源平争乱期に、昏い青春の谷間を持ったことが、作品理解に役立てられている。
このように第二部「式子内親王の歌について」で、次々と展開される、はっとするような鑑賞。これは、第一部「式子内親王とその周辺」を、じっくりくぐり抜けてきた読者にとって、まことに説得力のあるものだ。一部でしこまれた薬が、二部で効き目をいかんなく発揮するのである。
評伝と作品理解のとてもいい関係を、はからずも本書は教えてくれる。事実から先の真実を読みとることが、大切なのだ。
ALL REVIEWSをフォローする