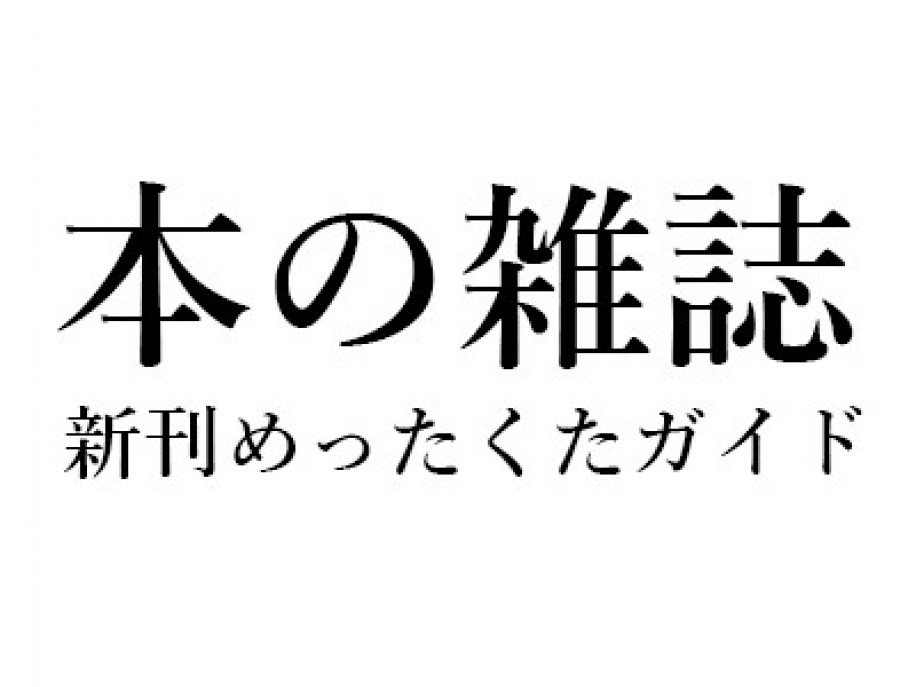書評
『マンガ狂につける薬』(リクルート ダヴィンチ編集部)
古い話でナンですが……私が高校生の時にマンガ雑誌『ガロ』が創刊された。従来の子どもマンガとも大人マンガとも違う独創的なマンガ雑誌の登場に、私は興奮した。「これだこれだ、こういう雑誌を待っていたのだ」と思った。
『ガロ』――とりわけ白土三平『カムイ伝』の連載はおもに大学生によって熱狂的に迎えられ、マスコミは「大学生がマンガを読む時代」と驚いた。60年代半ばのことである。「マンガを読むと馬鹿になる」という言い草がまだまだ幅を利かせていた時代だったのだ。
それから三十五年近くたった今でも、「活字文化」と「マンガ文化」は対立的なものとして考えられているところがある。実際、昔だったら(具体的に言うと三島由紀夫が亡くなった一九七〇年までだったら)、文学や評論の世界に向かっていただろうと思わせる才能が、マンガの世界へと大量に流出して行ったのは確かなことだと思う。マンガを作る側も読む側も。おかげで「活字文化」界は空洞化し、「マンガ文化」界は隆盛した。「活字文化」の世界だけをみつめて、その上でものを言っていたら、確かにマンガは大敵だったのだ。
しかし、やっぱり『ガロ』という雑誌の出現は画期的だったのだ。馬鹿は岩波文庫を読もうが『少年マガジン』を読もうが馬鹿。「活字文化」「マンガ文化」それ自体にはそれぞれの長所短所があるだけで、馬鹿も利口もないのだ――ということを教えてくれた。
というわけで、『ガロ』育ちの思想家・呉智英の『マンガ狂につける薬』(メディアファクトリー)は、「活字文化」と「マンガ文化」の境界を突破し、縦横無尽に駆けめぐる、実にスリリングな読みものになっている。
例えば、花輪和一『――新今昔物語――鵺(ぬえ)』から岩波文庫の『荘子』を連想し、「醜怪さと美しさが、不気味さと崇高さが、紙一重で接する面白さ」を語る。岩明均『寄生獣』から生命の不思議さを思い、E・シュレーディンガーの『生命とは何か』の「負のエントロピー(ネゲントロピー)」という説を紹介する。『ナニワ金融道』という大ヒットを飛ばした青木雄二の『悲しき友情』から一種のユートピア思想としての共産主義のゆくすえを思い、十九世紀半ばのアメリカの共産主義的共同体オナイダ・コミュニティの歴史を追った倉塚平『ユートピアと性』について論じる。
おのずから、この『マンガ狂につける薬』という本はユニークなブックガイドになっている。「マンガ文化」にどっぷりの人びとには「活字文化」への通路を、「活字文化」にどっぷりの人びとには「マンガ文化」への通路を指し示してくれる。それぞれの必読文献がよくわかる。
マンガ狂にして活字狂の著者にしかできなかった仕事ではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
『ガロ』――とりわけ白土三平『カムイ伝』の連載はおもに大学生によって熱狂的に迎えられ、マスコミは「大学生がマンガを読む時代」と驚いた。60年代半ばのことである。「マンガを読むと馬鹿になる」という言い草がまだまだ幅を利かせていた時代だったのだ。
それから三十五年近くたった今でも、「活字文化」と「マンガ文化」は対立的なものとして考えられているところがある。実際、昔だったら(具体的に言うと三島由紀夫が亡くなった一九七〇年までだったら)、文学や評論の世界に向かっていただろうと思わせる才能が、マンガの世界へと大量に流出して行ったのは確かなことだと思う。マンガを作る側も読む側も。おかげで「活字文化」界は空洞化し、「マンガ文化」界は隆盛した。「活字文化」の世界だけをみつめて、その上でものを言っていたら、確かにマンガは大敵だったのだ。
しかし、やっぱり『ガロ』という雑誌の出現は画期的だったのだ。馬鹿は岩波文庫を読もうが『少年マガジン』を読もうが馬鹿。「活字文化」「マンガ文化」それ自体にはそれぞれの長所短所があるだけで、馬鹿も利口もないのだ――ということを教えてくれた。
というわけで、『ガロ』育ちの思想家・呉智英の『マンガ狂につける薬』(メディアファクトリー)は、「活字文化」と「マンガ文化」の境界を突破し、縦横無尽に駆けめぐる、実にスリリングな読みものになっている。
例えば、花輪和一『――新今昔物語――鵺(ぬえ)』から岩波文庫の『荘子』を連想し、「醜怪さと美しさが、不気味さと崇高さが、紙一重で接する面白さ」を語る。岩明均『寄生獣』から生命の不思議さを思い、E・シュレーディンガーの『生命とは何か』の「負のエントロピー(ネゲントロピー)」という説を紹介する。『ナニワ金融道』という大ヒットを飛ばした青木雄二の『悲しき友情』から一種のユートピア思想としての共産主義のゆくすえを思い、十九世紀半ばのアメリカの共産主義的共同体オナイダ・コミュニティの歴史を追った倉塚平『ユートピアと性』について論じる。
おのずから、この『マンガ狂につける薬』という本はユニークなブックガイドになっている。「マンガ文化」にどっぷりの人びとには「活字文化」への通路を、「活字文化」にどっぷりの人びとには「マンガ文化」への通路を指し示してくれる。それぞれの必読文献がよくわかる。
マンガ狂にして活字狂の著者にしかできなかった仕事ではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
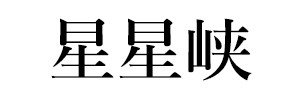
星星峡 1998年6月
ALL REVIEWSをフォローする