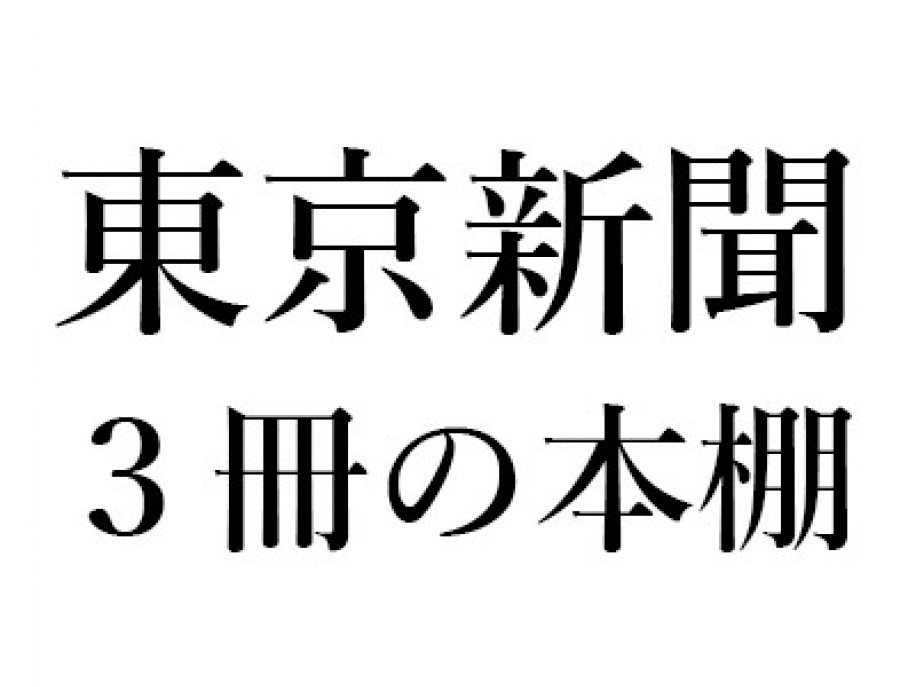書評
『新編 風の又三郎』(新潮社)
宮沢賢治には興味がなかった。
宮沢賢治といったら、何といったって「ミソとショーユの人」である。中学時代だったか教科書に「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」の文章が載っていた(実は、ショーユは出て来ないのだが、私はいつのまにか「ミソとショーユ」と思っていたのだ)。私はビンボくさくて地味くさくて嫌だなぁと思った。背中にタキギを背負いながらもしぶとく勉強していたという二宮金次郎を連想した。「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」は観光地のミヤゲ物屋で売られているノレンなどに染め抜かれていがちな感じもした。
そもそも私は、子ども向きに書かれた子どもの本というのにあんまり興味がなかった。マンガのほうが大好きで、活字のほうまで読む意欲もゆとりもなかったのだ。時どき父の本棚に、古いボロボロの表紙の『千夜一夜物語』を、三島由紀夫や石川達三の新刊を発見し、わけもわからないのに(「接吻」という字が読めずに祖父に聞いた記憶あり)、面白がって読んでいた。だから有名な『風の又三郎』も『セロ弾きのゴーシュ』も『銀河鉄道の夜』も知らなかった。初めて読んだのは大人になってから、二十代半ばのころだった。
驚いた。それまで勝手に思い込んでいた二宮金次郎的な、ミヤゲ物屋のノレン的な道徳性とはまったく無縁だったことに驚いた。一番好きなのは『風の又三郎』で、冒頭の九月一日の田舎の小学校の場面、馬を追う牧場の場面、嵐の朝に一郎が学校に急ぐ場面……すべてにありありと風を感じる。さまざまな風を体験する。こんなにも風が主役の、ほとんど風そのものを活字で描き出してしまった小説があっただろうか。
大人になってだんだんにわかって来たことなのだが、私は自分を風とか煙のように感じるし、「今、自分はここに生きている!」という、生の実感っていうやつでしょうか、そういう感覚は一陣の風によってもたらされることが多い。風というものに過剰に反応してしまう。『風の又三郎』を読んだときの一番の驚きは、私よりもっともっと風に執着している人がいたということだったと思う。それは「ミソとショーユの人」としての宮沢賢治とはすぐには結びつかないものだった。
『風の又三郎』の舞台は北のほうの田舎の小学校で、田舎といえば土の色を連想し、「ミソとショーユの人」というイメージはそれにぴったりだったのだが、『風の又三郎』一編から受ける印象は土の色ではなく、空の色である、風の色である、透明なひんやりとした青い色である。そこが私には非常に不思議で、惹かれたのだった。
『銀河鉄道の夜』を読むと、たびたび「青」という言葉が出て来る。それは水底の青であったり、りんどうの花の青であったり、街燈の青であったり、アスパラガスの葉の青であったりする。さまざまなニュアンスの青である。私は子どものころ好きだった、パウル・クレーが色見本帳のようにさまざまなニュアンスの青を使った絵を思い出す。
二年ほど前に伊藤俊也監督が『風の又三郎』を映画化した。私は見る前にこう思った。「私はあまりにも原作を愛してしまっているので、映画化に関しては成功か失敗か、そのどちらかしかないな。成功か失敗かの基準は、この小説の“風”に注目しているかどうかだ。それしかない」
いざ見てみたら、いくらかの不満(最大の不満は舞台をスイスかどこかみたいな洋風仕立てにしていたことだ)もあったが、カメラはまさに(あざといくらいに)一陣の風と化していて、「成功」と思った(しかし、戦前の島耕二監督の『風の又三郎』にはやっぱり負ける。又三郎を亡霊のごとく撮っていたのがすごい)。
宮沢賢治の大きさというのは、たぶん、空を見る人であると同時に、土を見る人でもあったことだろう。空のかなたに憑(つ)かれ、風にあこがれる人であると同時に、鈍重なまでに土くさい生き方にあるとうとさを感じ、「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」とノートに記さずにはいられない人でもあったことだろう。
『風の又三郎』の次に心に残ったのは『土神ときつね』という短い話だ。
北のはずれの野原に立つ一本の、きれいな女の樺(かば)の木をめぐる、荒々しい土神と繊細なきつねの物語。樺の木を愛し、自分には決定的に欠けているスマートさやお酒落っぽさを持ったきつねにたいする土神の心の動きが、せつないったらない。きつねと土神は、男の二つの典型とも思えるし、知識人と大衆を、あるいは精神性と肉体性を象徴しているようにも思える。ラストシーンもすごい。土神は感情を爆発させて、きつねを叩きのめしてしまう。そのあとで、土神はきつねの悲しい秘密を知ってしまう。「途方もない声で」泣き出す土神。空虚な心。「その泪(なみだ)は雨のやうに狐に降り狐はいよいよ首をぐんにゃりとしてうすら笑ったやうになって死んで居たのです」。
この最後の一行がこわい。このきつねのうすら笑いは何なんだろう。土神への非暴力的な復讐か、それとも「みんな同じように悲しいんだよ」という生ある者への慈悲のような気持か。
こんなすごい話を、宮沢賢治は子どもにも読める平明な(しかも非常に洗練された感覚的な)言葉で、しゃあしゃあと書いている。まいってしまう。
二十代の半ばころ、私はそれまで頭の中に詰め込んだいろんな言葉の城がガタガタに崩れていて、何もしたくない何も考えたくないという気分で過ごしていたけれど、『宮沢賢治童話集』を気まぐれに読んで、しばらくは「これだけ読んでいればいい。これだけでいい」という気持になった。ぼんやりと息苦しかった私の心に、なんだか思いがけないところから気持のいい風が吹いて来たように思ったのだった。
【初出】文春文庫ビジュアル版『宮沢賢治への旅』
【この書評が収録されている書籍】
宮沢賢治といったら、何といったって「ミソとショーユの人」である。中学時代だったか教科書に「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」の文章が載っていた(実は、ショーユは出て来ないのだが、私はいつのまにか「ミソとショーユ」と思っていたのだ)。私はビンボくさくて地味くさくて嫌だなぁと思った。背中にタキギを背負いながらもしぶとく勉強していたという二宮金次郎を連想した。「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」は観光地のミヤゲ物屋で売られているノレンなどに染め抜かれていがちな感じもした。
そもそも私は、子ども向きに書かれた子どもの本というのにあんまり興味がなかった。マンガのほうが大好きで、活字のほうまで読む意欲もゆとりもなかったのだ。時どき父の本棚に、古いボロボロの表紙の『千夜一夜物語』を、三島由紀夫や石川達三の新刊を発見し、わけもわからないのに(「接吻」という字が読めずに祖父に聞いた記憶あり)、面白がって読んでいた。だから有名な『風の又三郎』も『セロ弾きのゴーシュ』も『銀河鉄道の夜』も知らなかった。初めて読んだのは大人になってから、二十代半ばのころだった。
驚いた。それまで勝手に思い込んでいた二宮金次郎的な、ミヤゲ物屋のノレン的な道徳性とはまったく無縁だったことに驚いた。一番好きなのは『風の又三郎』で、冒頭の九月一日の田舎の小学校の場面、馬を追う牧場の場面、嵐の朝に一郎が学校に急ぐ場面……すべてにありありと風を感じる。さまざまな風を体験する。こんなにも風が主役の、ほとんど風そのものを活字で描き出してしまった小説があっただろうか。
大人になってだんだんにわかって来たことなのだが、私は自分を風とか煙のように感じるし、「今、自分はここに生きている!」という、生の実感っていうやつでしょうか、そういう感覚は一陣の風によってもたらされることが多い。風というものに過剰に反応してしまう。『風の又三郎』を読んだときの一番の驚きは、私よりもっともっと風に執着している人がいたということだったと思う。それは「ミソとショーユの人」としての宮沢賢治とはすぐには結びつかないものだった。
『風の又三郎』の舞台は北のほうの田舎の小学校で、田舎といえば土の色を連想し、「ミソとショーユの人」というイメージはそれにぴったりだったのだが、『風の又三郎』一編から受ける印象は土の色ではなく、空の色である、風の色である、透明なひんやりとした青い色である。そこが私には非常に不思議で、惹かれたのだった。
『銀河鉄道の夜』を読むと、たびたび「青」という言葉が出て来る。それは水底の青であったり、りんどうの花の青であったり、街燈の青であったり、アスパラガスの葉の青であったりする。さまざまなニュアンスの青である。私は子どものころ好きだった、パウル・クレーが色見本帳のようにさまざまなニュアンスの青を使った絵を思い出す。
二年ほど前に伊藤俊也監督が『風の又三郎』を映画化した。私は見る前にこう思った。「私はあまりにも原作を愛してしまっているので、映画化に関しては成功か失敗か、そのどちらかしかないな。成功か失敗かの基準は、この小説の“風”に注目しているかどうかだ。それしかない」
いざ見てみたら、いくらかの不満(最大の不満は舞台をスイスかどこかみたいな洋風仕立てにしていたことだ)もあったが、カメラはまさに(あざといくらいに)一陣の風と化していて、「成功」と思った(しかし、戦前の島耕二監督の『風の又三郎』にはやっぱり負ける。又三郎を亡霊のごとく撮っていたのがすごい)。
宮沢賢治の大きさというのは、たぶん、空を見る人であると同時に、土を見る人でもあったことだろう。空のかなたに憑(つ)かれ、風にあこがれる人であると同時に、鈍重なまでに土くさい生き方にあるとうとさを感じ、「雨ニモマケズ 風ニモマケズ」とノートに記さずにはいられない人でもあったことだろう。
『風の又三郎』の次に心に残ったのは『土神ときつね』という短い話だ。
北のはずれの野原に立つ一本の、きれいな女の樺(かば)の木をめぐる、荒々しい土神と繊細なきつねの物語。樺の木を愛し、自分には決定的に欠けているスマートさやお酒落っぽさを持ったきつねにたいする土神の心の動きが、せつないったらない。きつねと土神は、男の二つの典型とも思えるし、知識人と大衆を、あるいは精神性と肉体性を象徴しているようにも思える。ラストシーンもすごい。土神は感情を爆発させて、きつねを叩きのめしてしまう。そのあとで、土神はきつねの悲しい秘密を知ってしまう。「途方もない声で」泣き出す土神。空虚な心。「その泪(なみだ)は雨のやうに狐に降り狐はいよいよ首をぐんにゃりとしてうすら笑ったやうになって死んで居たのです」。
この最後の一行がこわい。このきつねのうすら笑いは何なんだろう。土神への非暴力的な復讐か、それとも「みんな同じように悲しいんだよ」という生ある者への慈悲のような気持か。
こんなすごい話を、宮沢賢治は子どもにも読める平明な(しかも非常に洗練された感覚的な)言葉で、しゃあしゃあと書いている。まいってしまう。
二十代の半ばころ、私はそれまで頭の中に詰め込んだいろんな言葉の城がガタガタに崩れていて、何もしたくない何も考えたくないという気分で過ごしていたけれど、『宮沢賢治童話集』を気まぐれに読んで、しばらくは「これだけ読んでいればいい。これだけでいい」という気持になった。ぼんやりと息苦しかった私の心に、なんだか思いがけないところから気持のいい風が吹いて来たように思ったのだった。
【初出】文春文庫ビジュアル版『宮沢賢治への旅』
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする