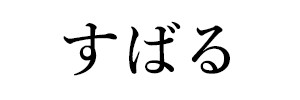書評
『第七官界彷徨・琉璃玉の耳輪 他四篇』(岩波書店)
尾崎翠『第七官界彷徨』
『第七官界彷徨』という不思議なタイトルの小説と出会ったのは、昭和四十四年のことだ。學藝書林というところから「現代文学の発見」というシリーズもののアンソロジーが出ていて、その第六巻に収録されていた。この本を私はいまだに捨てられずに持っているのだが、その本の奥付けを見ると昭和四十四年一月十日第一刷発行となっている。確か私は本が出版されてすぐに買ったから、この日にちとあまりズレていないある日に、初めて『第七官界彷徨』を読んだということになる。よほど遠い過去のこと、秋から冬にかけての短い期間を、私は、変な家庭の一員としてすごした。そしてそのあいだに私はひとつの恋をしたようである。
という書き出しで始まるこの小説に、私はたちまちぐんぐんと引きずり込まれた。小説を読むことの喜びのひとつは、「ここにもう一人、私と同じ感じ方をしている人間がいる。私と同じ事柄に立ち止まり、こだわって、それを言葉にしている人がいる。私は一人じゃないんだ。孤独じゃないんだ」という喜びであって、若いころはとくにそういう種類の、小説の中に同族を求めたがる気持が強かったような気がする。
『第七官界彷徨』は小野町子という若い女の子が、その兄である小野一助と小野二助、それからいとこである佐田三五郎との、古ぼけた一軒家での共同生活の日々をつづった形をとっている。小野町子は彼らの身のまわりの世話をしながら、ひそかに詩人をめざしている。彼女は「人間の第七官にひびくような詩」を書きたいと思っている。精神科医をしている一助の研究書で「分裂心理学」について知った彼女は、第七官というのは、人間の意識の識閾上と識閾下の間の、「広びろとした霧のかかった心理界」なのではないかと思う。
また、農学部学生である二助が研究のために使っているこやしの臭気と、音大受験生の三五郎がひき鳴らす調子の狂ったピアノの音の中で、「第七官というのは、二つ以上の感覚がかさなってよびおこすこの哀感ではないか」と発見したりする。
やがて、町子は三五郎にクセのある頭髪を裁ちばさみで切られながら自分の第七官界をさまようことになる。
睡りに陥りそうになると私は深い呼吸をした。こみ入った空気を鼻から深く吸いいれることによってすこしのあいだ醒め、ふたたび深い息を吸った。そうしてるうちに、私は、霧のようなひとつの世界に住んでいたのである。そこでは私の感官がばらばらにはたらいたり、一つに溶けあったり、またほぐれたりして、とりとめのない機能をつづけた。
土鍋の液が、ふす、ふす、と次第に濃く煮えてゆく音は、祖母がおはぎのあんこを煮る音と変らなかったので、私は六つか七つの子供にかえり、私は祖母のたもとにつかまって鍋のなかのあんこをみつめていた。
この小説の中で最も鮮やかで印象的な部分である。
私はこの小説を読んだときは大学生で、ずうっと「文学少女」というものを軽べつしていたのだが、いかなる風の吹き回しか男友だち二人と共同で詩集を作ったりしていた。三人が三人とも初めて詩というものを書いた、そういうつたない詩集である。私が詩を書きたいという衝動にとり憑かれたのは、やっぱり自分の心の中に、もやもやとした何か、ひとつらなりの言葉としてカタチになることを待ち望んでいる何か――があって、それが気になってたまらなくなったからだ。『第七官界彷徨』を読んで、私はその何かは第七官界というものだったと気がついた。
登場人物の名前からしてどことなくトボケているが、この小説全編に漂う滑稽にも大いに惹かれた。それから、文中に二助の「荒野山裾野の土壌利用法に就いて」という論文や、「肥料の熱度による植物の恋情の変化」という論文を引用してみせる酒落っ気にもうなった(私はこういう、文体上の仕掛けのある小説が大好きである)。
明治生まれの、宮本百合子などと同世代の女性で、こんなに鋭く激しく、理知と抒情が同居している文章を書ける人がいたとは。こんなにじかに私の胸の中に飛び込んで来る小説を作ってしまう人がいたとは。
二年後の一九七一年(これも本の奥付けでそれとわかるのだが)、薔薇十字社というところから『アップルパイの午後』という尾崎翠の作品集が出たとき、私はわざわざ一番町の出版社まで買いに行った。一九七九年、創樹社から一巻全集が出たときは興奮した。今、フト気がついたのだが、私がそんなふうにして一人の女性作家をしつこく追いかけて読むということをしたのは、尾崎翠と森茉莉、この二人だけだ。そして二人とも、なぜか明治時代に生まれた人なのだった。
私は、映画『ストレンジャー・ザン・パラダイス』を見たとき、吉本ばななさんの『キッチン』を読んだとき、それから村田喜代子さんの『鍋の中』を読んだとき、フッと尾崎翠の匂いを感じた。
けれど、若いころに自分にとって「決定的な一冊!」と思えるような本に出会ってしまうというのも困りものだ。尾崎翠の小説は、いわゆる「透明な感性」という言葉でくくられるような、近頃ハヤリの小説を先取りしているようなものだが、何を読んでも「やっぱり尾崎翠ほどの切実さはない。物足りない」と思ってしまうのだ。尾崎翠は悲壮さをむきだしにはしないで、トボケたり、文章で遊んでいたりするけれど、読み終わったときに何か、むきだしのハダカで荒野に立っているような、素肌でじかに風を感じているような、切実な(としか言いようがない)印象に胸をしめつけられるのだが、近ごろの「透明な感性」もんの小説は、その「透明な感性」というもので身をおおい、ぬくもって、自足している感じがしてならないのだ。
この二十年、私は『第七官界彷徨』以上のショックを体験していない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする