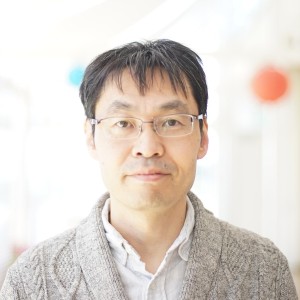書評
『サリンジャー ――生涯91年の真実』(晶文社)
我々はサリンジャーの何を知っていたのだろうか。2010年に彼が91歳で亡くなってから初めて刊行された伝記である本書を読むと、そう自分に問いかけざるをえない。なにしろ、今まで見たことのないサリンジャーの姿がふんだんに登場するのだから。
入手困難な単行本未収録作品や未発表原稿、手紙、関係者の証言、政府の資料などを突き合わせながら、著者は今までのサリンジャー像を丁寧に書き換えていく。圧巻なのはサリンジャーの戦争体験の部分だ。諜報(ちょうほう)部隊にいた彼はノルマンディー上陸作戦に参加し、部下を指揮しながら激戦をくぐり抜け、ダッハウの強制収容所を解放する。そこで彼が見たものは、多くの痩せ衰えたユダヤ人たちだった。「焼ける人肉のにおいは、一生かかっても鼻からはなれない」というサリンジャーの言葉からは、ただの素晴らしい青春小説にも思える彼の作品が、どれほどの闇を抱えているかがよくわかる。
戦後、彼は過去に数年を過ごしたウィーンに行き、恋した少女だけでなく、当時知り合ったほぼ全員がナチスに殺されていたことを知る。フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』で第1次世界大戦から帰ってきた主人公は、すべてを戦争前のままに戻してやる、という狂気の中にいた。その作品を愛したサリンジャーは同じ狂気を実際に生きることになる。代表作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』における、無垢(むく)で壊れやすいものを守りたいという欲望も、仲間と敵を峻別(しゅんべつ)する潔癖さも、あるいは50年代以降、彼自身がコーニッシュの村に引きこもったという事実も、すべて彼が生き延びるためには必要だったのだろう。
一人の傷ついた人物の言葉が世界に響き渡ることで、ヴォネガットやアップダイクなど彼に影響を受けた作家たちが生まれ、大人に反抗する若者文化が台頭し、インドの宗教哲学や禅などへの関心が高まった。要するにサリンジャーは、たった数冊で現代のアメリカ文化そのものを作りあげたのである。本書を読むとそのことがよくわかる。何より、また彼の本を読みたくなるところが素晴らしい。
入手困難な単行本未収録作品や未発表原稿、手紙、関係者の証言、政府の資料などを突き合わせながら、著者は今までのサリンジャー像を丁寧に書き換えていく。圧巻なのはサリンジャーの戦争体験の部分だ。諜報(ちょうほう)部隊にいた彼はノルマンディー上陸作戦に参加し、部下を指揮しながら激戦をくぐり抜け、ダッハウの強制収容所を解放する。そこで彼が見たものは、多くの痩せ衰えたユダヤ人たちだった。「焼ける人肉のにおいは、一生かかっても鼻からはなれない」というサリンジャーの言葉からは、ただの素晴らしい青春小説にも思える彼の作品が、どれほどの闇を抱えているかがよくわかる。
戦後、彼は過去に数年を過ごしたウィーンに行き、恋した少女だけでなく、当時知り合ったほぼ全員がナチスに殺されていたことを知る。フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』で第1次世界大戦から帰ってきた主人公は、すべてを戦争前のままに戻してやる、という狂気の中にいた。その作品を愛したサリンジャーは同じ狂気を実際に生きることになる。代表作『キャッチャー・イン・ザ・ライ』における、無垢(むく)で壊れやすいものを守りたいという欲望も、仲間と敵を峻別(しゅんべつ)する潔癖さも、あるいは50年代以降、彼自身がコーニッシュの村に引きこもったという事実も、すべて彼が生き延びるためには必要だったのだろう。
一人の傷ついた人物の言葉が世界に響き渡ることで、ヴォネガットやアップダイクなど彼に影響を受けた作家たちが生まれ、大人に反抗する若者文化が台頭し、インドの宗教哲学や禅などへの関心が高まった。要するにサリンジャーは、たった数冊で現代のアメリカ文化そのものを作りあげたのである。本書を読むとそのことがよくわかる。何より、また彼の本を読みたくなるところが素晴らしい。
ALL REVIEWSをフォローする