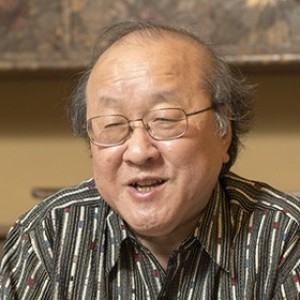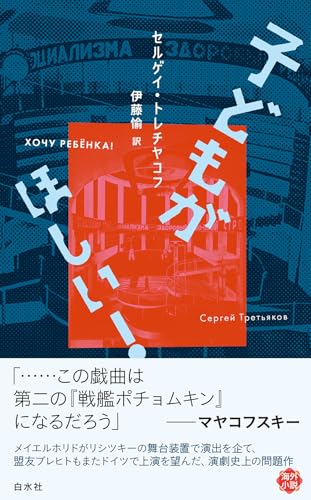書評
『プラヴィエクとそのほかの時代』(松籟社)
断片積み重ね「宇宙」描く
今年ノーベル文学賞を受賞した(実際には発表が延期された昨年の分の受賞だが)、ポーランドの作家、オルガ・トカルチュクの長編である。彼女の小説はすでに『昼の家、夜の家』『逃亡派』の二冊が翻訳されていて(どちらも小椋彩(ひかる)訳、白水社)、これが邦訳の三冊目となるが、じつはこの本が一番早く、原著は一九九六年に刊行されていた。しかし、決して古びてはおらず、むしろトカルチュクの原石といえるような魅力の詰まった作品である。舞台となるのは南西ポーランドの、ドイツとの国境から遠くないプラヴィエクという架空の村。ちなみに「プラヴィエク」とはポーランド語で元来「太古の時代」を意味する名詞である。それが村の名前になっているのが、象徴的だ。
一九一四年の第一次世界大戦勃発から、ドイツによる占領と近隣でのユダヤ人虐殺、戦後の共産党支配の確立、さらに自主労組「連帯」運動を経て現代にいたる激動のポーランド現代史を背景として、村人たちの年代記が繰り広げられる。しかし単線的に進行していく時間の流れはここにはなく、そもそも外部の世界の出来事は――それが戦争であれ、体制の転換であれ――この村にとっては遠くのこだまのようなものに過ぎない。小説の冒頭で宣言されている通り、この村は「宇宙の中心」なのだ。
確かに若い男女は結ばれ、子供が生まれ、世代が移り変わっていくものの、生と死の繰り返しを通して、村全体が永遠の時間の中にたゆたっているような印象を受ける。登場するのは、夫の出征中にユダヤの若者に道ならぬ恋をする人妻から、一生の大部分を屋敷の屋根のうえで過ごした老人、気がふれて月を呪う孤独な老女、ユダヤ人のラビに贈られた不思議なゲームのとりこになってしまう領主まで(そのゲームにはなんと八つの世界が含まれ、それぞれ異なった神がいる)。エキセントリックな人々も平凡な人々も、みなこの村の住民として、そして一時的に村を占拠するドイツ兵も、ロシア兵も、ほとんど差別されることなく描かれる。
さらに、登場するのは人間だけではない。犬も、ヘビも、木も、キノコも、「水霊」も、天使さえも、人間と同じ権利をもった存在として交錯する。これらの多彩な登場人物たちが織り成す村は、確かに一つの宇宙になっているが、その全体に目配りをしながら語るのは、緊密なプロット展開が求められる西洋近代小説の技法では難しい。そこでトカルチュクが採用したのは、数多くの断片(フラグメント)に分け、一つ一つの断片で登場人物の誰かに焦点を当てながら、断片を組み合わせ、積み重ねていく手法である。断片こそは、「より多くを、より複雑に、より多次元的に描写できる星座を創り出す」と、トカルチュク自身、一二月七日にストックホルムで行われたノーベル賞受賞記念講演で述べている。
この講演の内容は感動的なものだった。トカルチュクはここで、フェイクニュースやヘイトスピーチ、暴力があふれる現代世界を憂えながら、それに対抗する真実としてのフィクションの力への信念を表明し、「優しい語り手」の役割を強調する。「この世界が、絶えず私たちの目の前で生成していく一つの生き物であり、私たちはその世界の小さいけれども強力な一部であるかのように、私は語らなければならないと信じている」という、講演を締めくくる言葉は、この作品にもよく当てはまる。ここには、すべてを包み込むような「優しい語り手」が遍在しているからだ。
ALL REVIEWSをフォローする