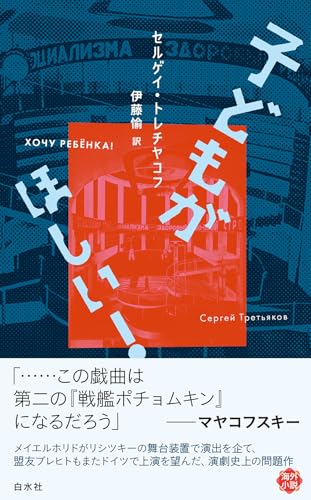書評
『逃亡派』(白水社)
新たにノーベル文学賞を受賞したトカルチュクの代表作と呼べるのが『逃亡派』です。2007年に発売された本書は、ポーランドの最も権威ある文学賞である「ニレ賞」を受賞。2018年には英訳版が「ブッカー国際賞」を受賞しています。2014年発売の日本語版も各方面から高く評価されました。今回はその中から蜂飼耳さんによる書評をご紹介いたします。
現実の土地としてのポーランドやクロアチアへは行ったことがなく、繰り返し描かれる解剖標本のことやスピノザについても、詳しいことはなにも知らない。それなのに、この作品にたまらなく懐かしさを感じる。現代そのものに対する懐かしさ、といってもいい。見えるもの、見えないもの、過去・現在・未来、原因と結果。人間は、物事を理解し、納得し、解決するために因果関係や理由を求める。歴史を求める。だが、いくらそれらを語っても、実際には語りきれない。立場と見方によって、物事の構図は変わるからだ。
この小説が選んだ断章のかたちは、語りきれない現実の手ざわりを伝える。なぜ、と問うよりもすばやく、ある断章の次に別の断章が配置される。それによって「なぜ」というよりも「そうなんだ」と思わされる構成が重ねられていく。いったんそこに身をゆだねることが出来れば、読者は、この作品が織り成す時間・空間と自分自身が生きる時間・空間の共鳴を体験することになるだろう。
クロアチアのある島へ旅行に出かけた一家。行き先で、妻子が失踪し、夫のクニツキは探しまわる。捜索のヘリコプターが出る。いったい、どこへ。この断章を受けて、あいだにいくつもの別の断章を挟んで、つづきが展開される。何事もなかったように戻ってくる妻と子。どこにいたのか、どんな秘密があるのか。クニツキは、知りたいという願望にさいなまれる。詳細は明かされない。読んでいるうちに、むしろクニツキのほうがバランスを失っているようにも見えてくる書き方になっている。そんなところにも作者の試みが顔をのぞかせる。人の行動や行為の原因と結果、その全貌を見ることは不可能だ、ということなのだ。
アキレス腱の発見者である十七世紀の解剖学者、フィリップ・フェルヘイエンは、ふとした怪我が原因となって左脚を切除する。オランダの哲学者、スピノザを尊敬するこの人物は、やがて解剖学者となる。あるとき、もう存在しない左脚に、痛みを感じるようになる。この解剖学者について、弟子の目を通して描いた章もあり、ひとりの人物の生涯と功績、継承されていく事柄などが別の角度からも捉えられている。そうした方法にも、もちろん、作者の企みが見てとれる。
本書のタイトルとも繋がる「逃亡派」は、ロシア正教のあるセクトを指す。作者は、逃亡と移動のすがたを、モスクワに暮らすアンヌシュカという女性を通して描き出す。彼女は難病の息子を抱えているが、週に一度、姑が息子の世話をしてくれるあいだ、所用を済ませるために外出することができる。あるとき、教会からの帰り道、地下鉄の出口で彼女は奇妙ないでたちの女性と出会う。足踏みを続けながら、何かつぶやいている女性。アンヌシュカがこの女性を見過ごすことができないのは、自分と通じるものを感じ取ったからだろう。声を掛け、しばらく行動をともにすることになる。日常に生じる裂け目。そこから始まる不穏な時間に、心を揺さぶられる。旅と移動のテーマがここにも登場する。
この小説には、たえまない移動を表す次のような言葉が出てくる。「いつだって、動いているなにかは、止まっているなにかよりもすばらしい。変化は恒常よりも高潔だ」。「このとき、私には、人間の天職というものがありありと見えた。つまり、重大、肝要なものをまったく含まない秘密を探して、ほこりにまみれて歩くこと、これだ」。人体と地図が重なり、望遠鏡的な視点と顕微鏡的な視点が重なる。読むことそのものが濃密な体験となっていく作品だ。
116の断章が織りなす旅と移動の物語
挑戦的な小説だ。ポーランドの作家、オルガ・トカルチュクが生み出した本書は、116の断章で構成されている。断章、断片が寄り集まって、ひとつの大きな旅を浮かび上がらせる。これは現代だからこそ出現した小説のすがただ。現実の土地としてのポーランドやクロアチアへは行ったことがなく、繰り返し描かれる解剖標本のことやスピノザについても、詳しいことはなにも知らない。それなのに、この作品にたまらなく懐かしさを感じる。現代そのものに対する懐かしさ、といってもいい。見えるもの、見えないもの、過去・現在・未来、原因と結果。人間は、物事を理解し、納得し、解決するために因果関係や理由を求める。歴史を求める。だが、いくらそれらを語っても、実際には語りきれない。立場と見方によって、物事の構図は変わるからだ。
この小説が選んだ断章のかたちは、語りきれない現実の手ざわりを伝える。なぜ、と問うよりもすばやく、ある断章の次に別の断章が配置される。それによって「なぜ」というよりも「そうなんだ」と思わされる構成が重ねられていく。いったんそこに身をゆだねることが出来れば、読者は、この作品が織り成す時間・空間と自分自身が生きる時間・空間の共鳴を体験することになるだろう。
クロアチアのある島へ旅行に出かけた一家。行き先で、妻子が失踪し、夫のクニツキは探しまわる。捜索のヘリコプターが出る。いったい、どこへ。この断章を受けて、あいだにいくつもの別の断章を挟んで、つづきが展開される。何事もなかったように戻ってくる妻と子。どこにいたのか、どんな秘密があるのか。クニツキは、知りたいという願望にさいなまれる。詳細は明かされない。読んでいるうちに、むしろクニツキのほうがバランスを失っているようにも見えてくる書き方になっている。そんなところにも作者の試みが顔をのぞかせる。人の行動や行為の原因と結果、その全貌を見ることは不可能だ、ということなのだ。
アキレス腱の発見者である十七世紀の解剖学者、フィリップ・フェルヘイエンは、ふとした怪我が原因となって左脚を切除する。オランダの哲学者、スピノザを尊敬するこの人物は、やがて解剖学者となる。あるとき、もう存在しない左脚に、痛みを感じるようになる。この解剖学者について、弟子の目を通して描いた章もあり、ひとりの人物の生涯と功績、継承されていく事柄などが別の角度からも捉えられている。そうした方法にも、もちろん、作者の企みが見てとれる。
本書のタイトルとも繋がる「逃亡派」は、ロシア正教のあるセクトを指す。作者は、逃亡と移動のすがたを、モスクワに暮らすアンヌシュカという女性を通して描き出す。彼女は難病の息子を抱えているが、週に一度、姑が息子の世話をしてくれるあいだ、所用を済ませるために外出することができる。あるとき、教会からの帰り道、地下鉄の出口で彼女は奇妙ないでたちの女性と出会う。足踏みを続けながら、何かつぶやいている女性。アンヌシュカがこの女性を見過ごすことができないのは、自分と通じるものを感じ取ったからだろう。声を掛け、しばらく行動をともにすることになる。日常に生じる裂け目。そこから始まる不穏な時間に、心を揺さぶられる。旅と移動のテーマがここにも登場する。
この小説には、たえまない移動を表す次のような言葉が出てくる。「いつだって、動いているなにかは、止まっているなにかよりもすばらしい。変化は恒常よりも高潔だ」。「このとき、私には、人間の天職というものがありありと見えた。つまり、重大、肝要なものをまったく含まない秘密を探して、ほこりにまみれて歩くこと、これだ」。人体と地図が重なり、望遠鏡的な視点と顕微鏡的な視点が重なる。読むことそのものが濃密な体験となっていく作品だ。
ALL REVIEWSをフォローする