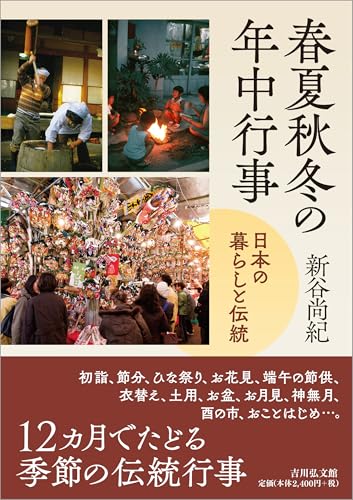書評
『レールの向こう』(集英社)
人生の足元、確かめ拡がる世界
沖縄の歴史や文化を主題として執筆を続け、戦後の沖縄文学を牽引(けんいん)してきた大城立裕の作品集。表題作は、八十九歳の作家が綴(つづ)る私小説。妻が脳梗塞(こうそく)を患って那覇の病院に入院する。記憶障害とリハビリの日々。衣替えの時期が来ても、「私」は秋に着られるシャツがどこにしまってあるのか見当がつかない。「私はお前に訊(き)くのを諦めて、しばらく薄着で我慢することにした」。思いついて箪笥(たんす)から引っ張り出したのは、五十年も前にハワイで買った厚手のアロハシャツ。
ある日、雑誌から、急逝した真謝志津夫(まじゃしづお)への追悼文を依頼される。追悼を書く余裕はない状態の中、よみがえるのは、真謝が手掛けた一連の船舶小説のこと。「ただメカの説明が詳しすぎて、ときにそればかりを書いているように見えた」。船舶に拘(こだわ)り続けた真謝の姿勢や面影が「私」の脳裡(のうり)を往来する。死者との距離感を測りかねているような人物の立ち位置は、じつは誰にとっても親しいものではないか、と思う。
「病棟の窓」という一編は、「私」の病気を描く。病院は思いがけない再会の場ともなる。「あの可愛らしかった娘も、もうそういう歳(とし)なのだ!」と、廊下で五十年前の旧知に呼び止められて感慨を抱く。体の動きが不自由になって、行動に制限が生じても、目に映る景色はむしろ新鮮なくらいだ。日常を淡々と綴る筆致は、思い出に変わっていく瞬間を書きとめる。
他の四編は、家族と沖縄の葬制、ハワイへの移民一世と子孫のこと、見えない世界に通じる巫女(ゆた)と那覇市新都心の空虚感などを描き出す。いずれも沖縄の風土に根ざす作品だが、そうした地域性の濃さによるある種の限定が作風を狭めはしないことを、この小説集は力強く告げる。観察は掘り下げられ、拡(ひろ)がる。どこに生きているのか。その足元を、繰り返し確かめながらかたちを成していく世界だ。
朝日新聞 2015年10月11日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする