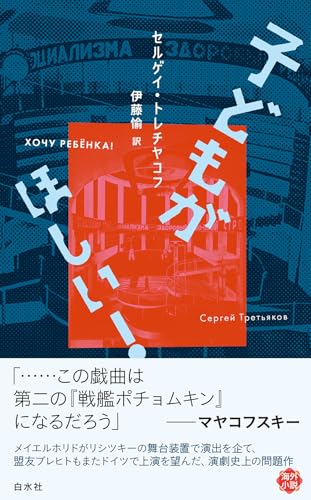書評
『ヴァイゼル・ダヴィデク』(松籟社)
占領、戦争、破壊の記憶 3少年が見たのは
一二歳前後の少年三人が過ごした、ある夏休みの物語。舞台はポーランド北部、バルト海に面した港町グダンスクとその周辺。この土地特有の濃密な気配、野蛮な体罰や飲んだくれの喧嘩が珍しくない荒っぽい日常生活でありながら、少年の目を通して描き出される情景の新鮮さ、時の流れの中を行きつ戻りつして過去を掘り起こす語り手の心の揺れに密着した文体――こういったものがあいまって、ちょっと類例のない独自の雰囲気のある作品世界を作っている。そして何よりも、読者を惹きつけ、読後もたゆたい続けるのは、この物語に仕掛けられ、結局最後まで解き明かされることのない謎だ。時は一九五七年。戦後ポーランドが社会主義国として復興に取り組んでいたころだ。この年の夏、三人の少年たちの前にダヴィデクという同級生が、突然、大きな存在として立ち現れる。ダヴィデクは両親のいないユダヤ人の孤児で、年老いた偏屈な祖父と暮らしている。しかし彼の出自は本当のところはよく分からない。いずれにせよ彼もその祖父も、第二次世界大戦中の大量虐殺(ホロコースト)の犠牲になることなく、戦後グダンスクに住み着いた。カトリック教徒が圧倒的多数を占めるポーランド社会では、ダヴィデクのようなユダヤ人少年は――しかも猫背気味で貧相な体格だ――いじめられそうなものだが、彼には不思議な力があって、一人の少女をいつも従え、さらに少年たちのカリスマとなっていく。
ダヴィデクには、空中浮遊の能力まで備わっているらしい。ある夜、レンガ工場の地下室で恍惚(こうこつ)として踊った後、床から高く浮かび上がる姿を少年たちに目撃される。彼はまた、ドイツ軍が置き去りにした銃を隠し持ち、爆薬まで見つけて、何度も爆発の実験を行って少年たちを驚かせる。しかも、その爆発は美しい色のついた一種芸術的なもので、最初は「まるで青色の雲が頭上で渦巻き、視界から消えるまで変形しながらどんどん高みへ上昇していくようだった」。そしてその次の「爆発の後空中に漂う雲はくっきり二色に染め分けられており、下の部分は陽の光の中で紫色を帯び、渦巻く円柱の頭は赤い飾り玉となった」。このユダヤ少年は超能力者なのか? それとも催眠術師、手品師なのか?
グダンスクの町には複雑な歴史がある。ドイツ人の勢力圏との接点にあったこの町は、ドイツ語でダンツィヒと呼ばれ、二十世紀の前半自由都市の地位を獲得してはいたが、人口の大部分はドイツ人が占めていた。ドイツの作家ギュンター・グラスもじつはこの町の出身で、彼の代表作『ブリキの太鼓』や『猫と鼠』はここを舞台としている。
パヴェウ・ヒュレは一九八七年に本作で鮮烈なデビューを果たした現代ポーランドを代表する小説家の一人だが、ダンツィヒ=グダンスク文学の系譜上、グラスを受け継ぐ存在と言えるだろう。第二次世界大戦の勃発とともにこの町はナチス・ドイツに占領されるが、戦後はポーランドに復帰した。戦争中に町の大半が破壊され、戦後も長いこと戦闘の生々しい爪痕が町の至るところに残っていた。
グダンスクはその後、一九七〇年に造船所でのストライキを発端に、政権側との衝突が起こって多くの犠牲者を出した。さらに十年後、この町の造船所は、一九八〇年に自主管理労働組合「連帯」の運動の発祥地となり、やがてそれが東欧革命へのうねりとつながっていった。この小説の語り手は、こういった事後の出来事も経た視点から、第二次世界大戦と戦後ポーランドの動乱にはさまれた少年時代を振り返る。そして華麗な爆発を何度も披露したあと、突然跡形もなく消えたダヴィデクとはいったい何者だったのかと、自問し続ける。
決して牧歌的とは呼べない少年時代だった。「旱魃(かんばつ)が畑を荒廃させ」、海では魚が大量死したため「悪臭を放つスープが湾にたまり」「人々が馬の頭の形をした彗星を目撃した」夏だった。三人の少年たちは、ダヴィデクの失踪事件の直後に学校に呼びだされ、延々と真夜中まで拷問に近い取り調べを受けるのだが、決して口を割ろうとしない――いったい、ダヴィデクと、彼といっしょにいた少女の身に何が起こったのか?
しかし読者の目の前には、尋問の進行と並行して、錯綜した記憶のなかから事件の全体像がぼんやりと浮かび上がってくる。このように想起と語りのプロセスそのものが小説の素地を織り成していくような手法からすると、ヒュレはナボコフやゼーバルトといった現代世界文学の旗手たちと並べて読まれるべき作家でもあるだろう。ちなみに一九五七年は著者の生年であり、ダヴィデクの誕生日とされる九月十日は著者の誕生日に一致している。
複雑な歴史的背景と緻密な意識の流れと情景描写が入り組んでいるだけに翻訳は容易ではないが、訳文は原文の呼吸に寄り添い、日本語作品として読ませる見事な文体になっている。訳者解説も専門的学識を踏まえ、作品の特質や現代ポーランド文学の中での位置づけを明らかにし、意を尽くしている。
ALL REVIEWSをフォローする