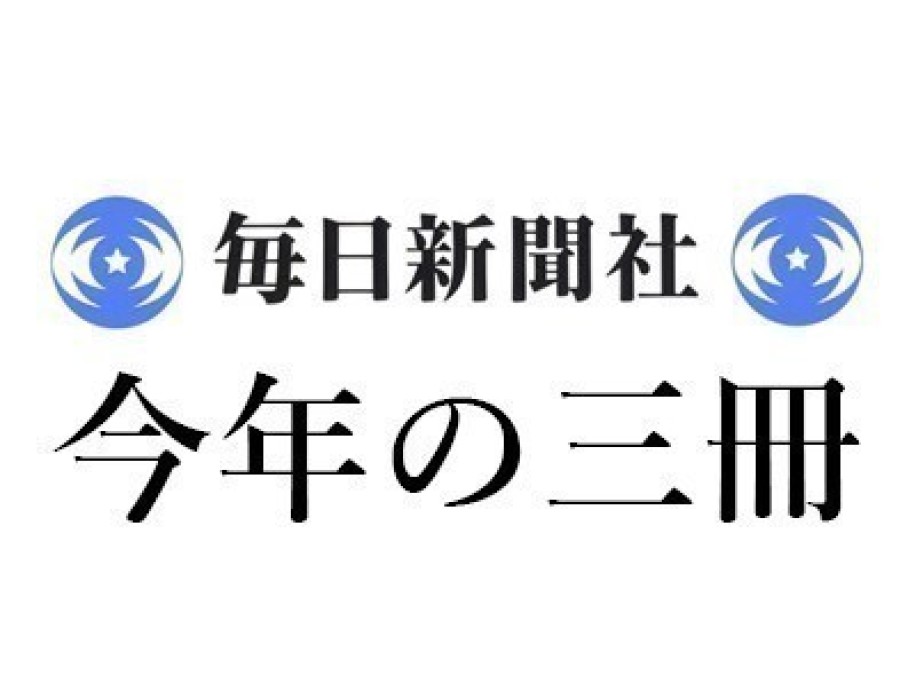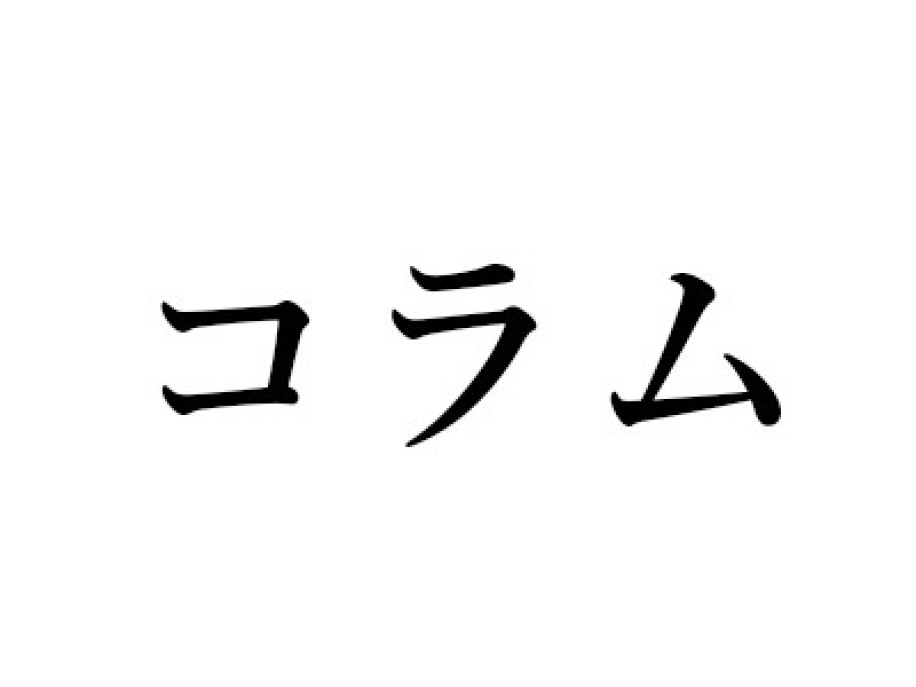書評
『不道徳教育講座』(角川書店)
何年ぶりだろう。二十五年か三十年ぶりに(!)三島由紀夫の『不道徳教育講座』を読み直してみた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。
オウム真理教に惹かれていった若い人たち、いわゆる“いじめ”に遭って自殺する子どもたち、それから日頃接触する若い人たちから漂う妙にもろい気配……というのがずうっと気になっていた。どこがどうとハッキリと言えないのだが、私の目には彼らは共通して真面目すぎる、いい子すぎる、真面目ということに対するトレーニングが不足している、真面目さ(純粋さとか善良さと言いかえてもいい)の表現が単調すぎる……というふうに見える。
そんなふうに思っていて、フト、「そう言えば三島由紀夫は、それと同じようなことをもっとうまく面白く書いていたなぁ」と思い出したのだ。
『不道徳教育講座』は一九五八年(昭和三十三年)、三島由紀夫三十三歳から三十四歳にかけて書かれたものである。その時代――『金閣寺』や『永すぎた春』の昭和三十一年から『鏡子の家』が世に出る昭和三十四年まで――は三島由紀夫にとって公私ともに順風満帆の時期であった。小説は評論家たちに絶讃され、売れゆきもよく、肉体コンプレックスも英会話コンプレックスも実際的努力(ボディビル、英会話レッスン)で克服し、あえて型通りのお見合いで結婚もした。自分の人生の舵はうまく取ってみせるという自信にあふれていた時期である。その自信といきおいがこの『不道徳教育講座』にはストレートに出ている。
三十章から成るエッセー集である。「教師を内心バカにすべし」「大いにウソをつくべし」「人に迷惑をかけて死ぬべし」「友人を裏切るべし」「弱い者をいじめるべし」「流行に従うべし」「人の恩は忘れるべし」「人の不幸を喜ぶべし」……など挑発的なタイトルをつけたエッセー集で、大衆向きに平易なこなれた言葉を使っていて、本人も気楽に楽しみながら書いている感じが伝わってくるが、それでも大衆に媚(こ)びたところは全然ない。「精神」と「肉体」、「美徳」と「悪徳」、「芸術」と「実生活」についてのいかにも三島由紀夫らしい考察が、この三十章の中に張りめぐらされている。大衆向けの軽いエッセーであっても、さすがに、通俗にして低俗にあらず。
さて。私が冒頭に書いた「それと同じようなことを三島はもっとうまく面白く書いていたなぁ」と思った、その部分は「沢山の悪徳を持て」と題された章の中にあった。
三島は「純情青年がアバズレ女に打ち込んで、金に困って友達の預り物を売り飛ばし、それでも足りなくなって、押込強盗を働らくというような話はよくききますが、この青年がほかに二三人女をもっていたら、決してこんなことにはならなかったにちがいない」という、下世話なわかりやすい例をあげ、こう言う。
オウム真理教に入信した人たちの大半は、マスコミが(私から見ると必要以上に)弁護している通り、いい人たちに違いないと思う。しかし、「グル」の意向通りに多くの人びとを無差別に殺したのも、そのいい人たちの、悪徳からではなくてまさに美徳(純粋さ、従順さ、忠誠心、克己心)からなのだ。三島がここで言っている「悪のバランスを取ること」「悪に慣れること」というのは、逆説とか皮肉とかではなく、そのまんまの正論だと思う。
いかんせん約四十年前に書かれたものであるから、引き合いに出される世相のエピソード(ロカビリー・ブーム、太陽族、石原裕次郎……)は今ではピンと来ないものになってしまったし、「道徳」という言葉がまだ厳然として生きていたあの時代ほどには挑発的な面白味は迫ってこない(当時の三島としては逆説的表現の中に真実をこめたつもりだったと思うが、今ではストレートな正論に読めてしまうのだ)。しかし、世の中も人間も基本的には変わっていないのである。三島由紀夫の目はその変わらない部分にまで届いているから、今読んでも、一章に必ず一カ所は、ハッとさせられるところがある。
――ああ、なんと、たくましく陽性の道徳論なのだろう。太宰治のように自分の弱さにすなおに居直れなかった三島由紀夫の、涙ぐましいまでの頑張り。上等の虚勢。小説『鏡子の家』で失敗しなければ、三島由紀夫はあと十年くらいはこんなふうに強気で調子に乗っていられたのかもしれない。私は、調子に乗っていてほしかったと思う。
【この書評が収録されている書籍】
オウム真理教に惹かれていった若い人たち、いわゆる“いじめ”に遭って自殺する子どもたち、それから日頃接触する若い人たちから漂う妙にもろい気配……というのがずうっと気になっていた。どこがどうとハッキリと言えないのだが、私の目には彼らは共通して真面目すぎる、いい子すぎる、真面目ということに対するトレーニングが不足している、真面目さ(純粋さとか善良さと言いかえてもいい)の表現が単調すぎる……というふうに見える。
そんなふうに思っていて、フト、「そう言えば三島由紀夫は、それと同じようなことをもっとうまく面白く書いていたなぁ」と思い出したのだ。
『不道徳教育講座』は一九五八年(昭和三十三年)、三島由紀夫三十三歳から三十四歳にかけて書かれたものである。その時代――『金閣寺』や『永すぎた春』の昭和三十一年から『鏡子の家』が世に出る昭和三十四年まで――は三島由紀夫にとって公私ともに順風満帆の時期であった。小説は評論家たちに絶讃され、売れゆきもよく、肉体コンプレックスも英会話コンプレックスも実際的努力(ボディビル、英会話レッスン)で克服し、あえて型通りのお見合いで結婚もした。自分の人生の舵はうまく取ってみせるという自信にあふれていた時期である。その自信といきおいがこの『不道徳教育講座』にはストレートに出ている。
三十章から成るエッセー集である。「教師を内心バカにすべし」「大いにウソをつくべし」「人に迷惑をかけて死ぬべし」「友人を裏切るべし」「弱い者をいじめるべし」「流行に従うべし」「人の恩は忘れるべし」「人の不幸を喜ぶべし」……など挑発的なタイトルをつけたエッセー集で、大衆向きに平易なこなれた言葉を使っていて、本人も気楽に楽しみながら書いている感じが伝わってくるが、それでも大衆に媚(こ)びたところは全然ない。「精神」と「肉体」、「美徳」と「悪徳」、「芸術」と「実生活」についてのいかにも三島由紀夫らしい考察が、この三十章の中に張りめぐらされている。大衆向けの軽いエッセーであっても、さすがに、通俗にして低俗にあらず。
さて。私が冒頭に書いた「それと同じようなことを三島はもっとうまく面白く書いていたなぁ」と思った、その部分は「沢山の悪徳を持て」と題された章の中にあった。
三島は「純情青年がアバズレ女に打ち込んで、金に困って友達の預り物を売り飛ばし、それでも足りなくなって、押込強盗を働らくというような話はよくききますが、この青年がほかに二三人女をもっていたら、決してこんなことにはならなかったにちがいない」という、下世話なわかりやすい例をあげ、こう言う。
私の皆さんに忠告したいことは、不道徳を一つだけ持ってると危ない、できるだけ 沢山持って、その間(かん)のバランスをとるようにすべきだ、ということです。
九十九パーセント道徳的、一パーセント不道徳的、これがもっとも危険な爆発的状態なのであります。七十パーセント道徳的、三十パーセント不道徳的、ここらが最も無難な社会人の基準でありましょう。このパーセンテージは、なかなか数学的に行かないのであって、一パーセント不道徳氏のほうが、三十パーセント不道徳氏よりも、 ずっと犯罪の近くにいることが多い。
人を悪徳に誘惑しようと思う者は、大ていその人の善いほうの性質を百パーセント利用しようとします。善い性質をなるたけ少なくすることが、誘惑に陥らぬ秘訣であります。
オウム真理教に入信した人たちの大半は、マスコミが(私から見ると必要以上に)弁護している通り、いい人たちに違いないと思う。しかし、「グル」の意向通りに多くの人びとを無差別に殺したのも、そのいい人たちの、悪徳からではなくてまさに美徳(純粋さ、従順さ、忠誠心、克己心)からなのだ。三島がここで言っている「悪のバランスを取ること」「悪に慣れること」というのは、逆説とか皮肉とかではなく、そのまんまの正論だと思う。
いかんせん約四十年前に書かれたものであるから、引き合いに出される世相のエピソード(ロカビリー・ブーム、太陽族、石原裕次郎……)は今ではピンと来ないものになってしまったし、「道徳」という言葉がまだ厳然として生きていたあの時代ほどには挑発的な面白味は迫ってこない(当時の三島としては逆説的表現の中に真実をこめたつもりだったと思うが、今ではストレートな正論に読めてしまうのだ)。しかし、世の中も人間も基本的には変わっていないのである。三島由紀夫の目はその変わらない部分にまで届いているから、今読んでも、一章に必ず一カ所は、ハッとさせられるところがある。
●大人というものは、ただむやみに若さにあこがれているわけではなく、大人の目から見ると、若さの哀れさもよくわかるのです。
●先生という種族は、諸君の逢うあらゆる大人のなかで、一等手強(てごわ)くない大人なのです。
●今、道徳教育などとえらい先生が言ってるが、私は、善のルールを建て直す前に、悪のルールを建て直したほうがいいという考えです。
●優雅という言葉は、本質的には、性的熟練という意味だと考えてよいのであります。
●女はあやふやなものに敏感です。あやふやなものを嗅ぎつけると、すぐバカにしてかかります。
●弱者を笑うというのは、もっとも健康な精神です。
●流行は無邪気なほどよく、「考えない」流行ほど本当の流行なのです。白痴的、痴呆的流行ほど、あとになって、その時代の、美しい色彩となって残るのである。
●爛熟した文化というものは、究極的には、女性的表現をとるのです。
●人に恩を施すときは、小川に花を流すように施すべきで、施されたほうも、淡々と忘れるべきである。これこそ君子(くんし)の交わりというものだ。
●健康な人間とは、本質的に不道徳な人間なのであります。
――ああ、なんと、たくましく陽性の道徳論なのだろう。太宰治のように自分の弱さにすなおに居直れなかった三島由紀夫の、涙ぐましいまでの頑張り。上等の虚勢。小説『鏡子の家』で失敗しなければ、三島由紀夫はあと十年くらいはこんなふうに強気で調子に乗っていられたのかもしれない。私は、調子に乗っていてほしかったと思う。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
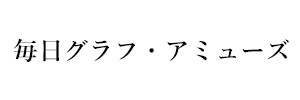
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする