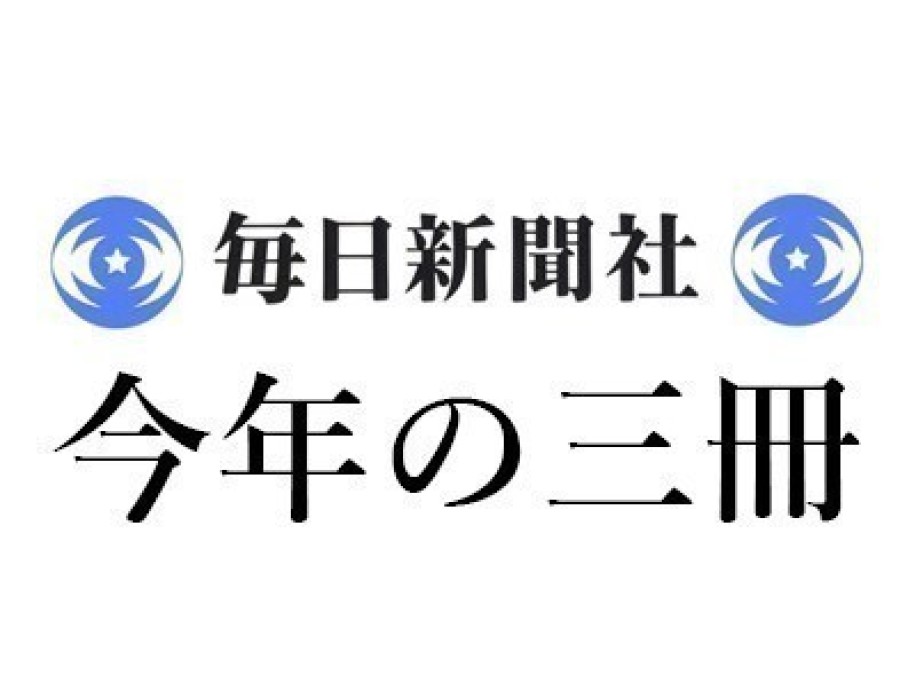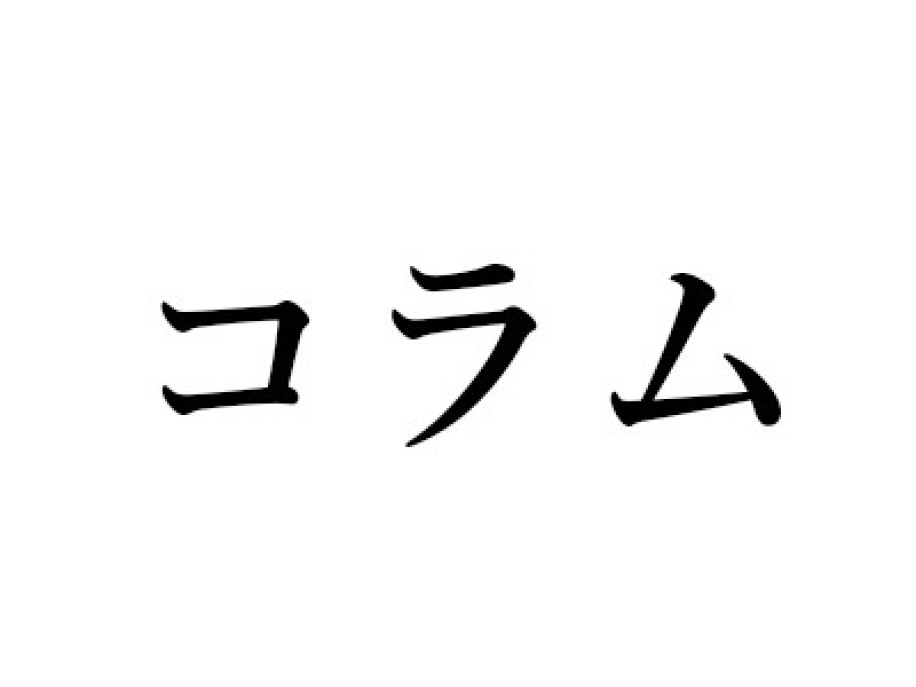書評
『偉大な姉妹』(新潮社)
『偉大な姉妹』(『ラディゲの死』(新潮社)収録)
あれから二十五年もたってしまったのかと、あらためて驚く(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。一九七〇年十一月二十五日。三島由紀夫が楯の会の人たちと市ヶ谷の自衛隊に乱入し、割腹自殺した日のことは忘れられない。「本気だったんだ。冗談じゃあなかったんだ」と、ただもうその言葉ばかり頭の中でつぶやくことしかできなかった。それまで私の頭の中にあった三島由紀夫像が根本からくつがえされたように思った。私は三島のやっていることはすべて一種の冗談とか挑発的パフォーマンスで、ずうっとトリックスターを演じ続けていく人というふうに見ていたのだった。亡くなってから、たびたび三島由紀夫のことを考えた。世の中にいろいろな事件(とくに天皇制に関する事件)が起こる。そのたびに自然と「三島だったらどう見ただろうか。どうコメントしただろうか」と考えてしまい、そして、それにたいして私は頭の中で反論し、「それじゃあ私はこう考える」という形で、自分の考えをかためていく。そういうところがあった。
私は三島由紀夫の小説の熱心なファンではないが、しかし、評論家・批評家・コラムニスト・コメンテーターとしての三島由紀夫には思いのほか影響を受けたと思う。若い頃の軽いコラム集ではあるが、『不道徳教育講座』などは私の無意識の領分にまでしみ込んでいると思う。野坂昭如や深沢七郎の才能をいち早く見抜いた三島由紀夫が、今も生きて文壇でにらみを利かせていてくれたら……と思うことも多い。
三島の小説では、私は長編よりも短編、しかも女性雑誌などに掲載された、通俗ロマンスが好きである。『夜会服』とか『につぽん製』とか『夏子の冒険』とか。『百万円煎餅』なんていうのも面白かったな。
恋愛ものではないが、長い間「私は案外、これが一番好きだ」と思ってきたのが、『偉大な姉妹』という短編だ。
ふたごのおばあさんの話である。明治の時代に「金力でなく智力で偉大になつた」唐沢将軍のふたごの娘の浅子と槙子(六十八歳)の話である。
唐沢将軍のたくさんの息子たち(つまり浅子・槙子の兄たち)は、一度は官界財界にいちおうの名を成し、「偉大」のミニチュア画を描きあげながら、それからいっせいに転落し、淋しい諦観のうちに老後を生きている。兄たちが小柄であるのに反して、この姉妹は大柄である。「唐沢一族の偉大の名残は、この二人の巨軀だけに在つて、よそにはなかつた」。
老姉妹の巨体の描写もおかしいが、次のようなくだりにはわくわくしてしまう。
「おあねえさまは今御不自由はないこと?」と浅子がきいた。
「実はね」
「二千円ほどでよございますか。ここのところちと不如意だもんだから」
「まあいつもいつもおそれいります」と姉は妹にむかつて鄭重に頭を下げた。
「ここへ来るのにもお花一つ持つて上れなかつたのよ」
「そんならさう仰言(おっしゃ)ればよろしいのに。水くさいおあねえさま」
浅子は帯の間から蓑虫細工の財布を出して千円札を二枚繰り出すと、槙子の座蒲団の 下へ素速く押し込んだ。槙子はしばらくそしらぬ顔であたりを見廻はしてから、二枚 の紙幣を袂に繰り込んで、その袂を押しいただくやうにした。姉妹の一挙一動は諸事 芝居がかつてゐたが、明治時代の東京の家庭ではかうしたわざとらしさが生活に抑揚 を与へ、感情にお祭のやうな郷愁的な賑はひを加へたものなのだ。あまつさへ槙子は その袖口で眼頭を拭つた。
――芝居がかったそのしぐさが目に見えるようだ。そういう「わざとらしさ」=演技性が、日常生活にめりはりをつけるという見方も面白い。
この老姉妹がいっしょに歌舞伎を見に行く場面も、面白い。老姉妹は、役者たちの顔が変わったことに憤慨する。
「だめだ、だめだ、羽子板にはならない顔だ」
「どつちもモダンな丸顔では、トマトと野球のボールの顔合せだわ。役者の顔はもつ と長くて大きくなくちや」「ほんたう。もう永生きしたつて仕様がない。こんな狂言をやれる役者がゐなくなつ た世の中だもの。ああ、みんな小粒になつた。舞台の大きい役者は死んでしまつた」
老姉妹の悪口に、三島はいかにも三島らしい歌舞伎論をつけ加えている。
歌舞伎役者の顔こそ偉大でなければならない。大首物(おほくびもの)の役者絵 は、悉く奇怪な偉大さを持つた顔を描いてゐる。その偉大さには一種の不均衡と過剰 がある。拡大された感情、誇張された悲哀を包むその輪廓は、均斉を保たうがために この悲哀や歓喜の内容に戦ひを挑んでゐる。美の伝達力として重んぜられたこの偉大 さは、歌舞伎が考へたやうな美の必然的な形式なのである。そこでは美と偉大の結婚 は世にも自然であつた。美が一個の犠牲の観念であり、偉大が一個の宗教的観念とな ることによつて、この婚姻が成立つた。大首物の錦絵の顔は、偉大に蝕まれた美のあ らはな病患を語つてゐる。
やけに生硬で大仰な文章で、わかりづらいが、「奇怪な偉大さ」という言葉が強く印象に残る。この歌舞伎論をじっくりとかみしめると、三島由紀夫のあの異様な死に方の筋道がわかるような気がする。「同志」の介錯(かいしゃく)ではねられた三島の首は、はたして錦絵の大首物のごとく「奇怪な偉大さ」を示していただろうか。
浅子とその十七歳の孫の関係も面白い。孫の興造は手帳に「みんなくたばれ、みんな死ね、宇宙の塵になり果てろ」と書きつけている少年で、祖母の浅子は孫のそういう、いまにも爆発しそうな「不満」を愛し、「興ちやんはいつかえらくなります」「興ちやんもわるいお父つあんを持つたね」「興ちやんはああならないでおくれよ」と言う、アナーキーなばあさんなのだ。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
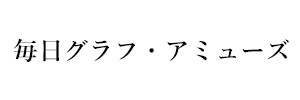
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする