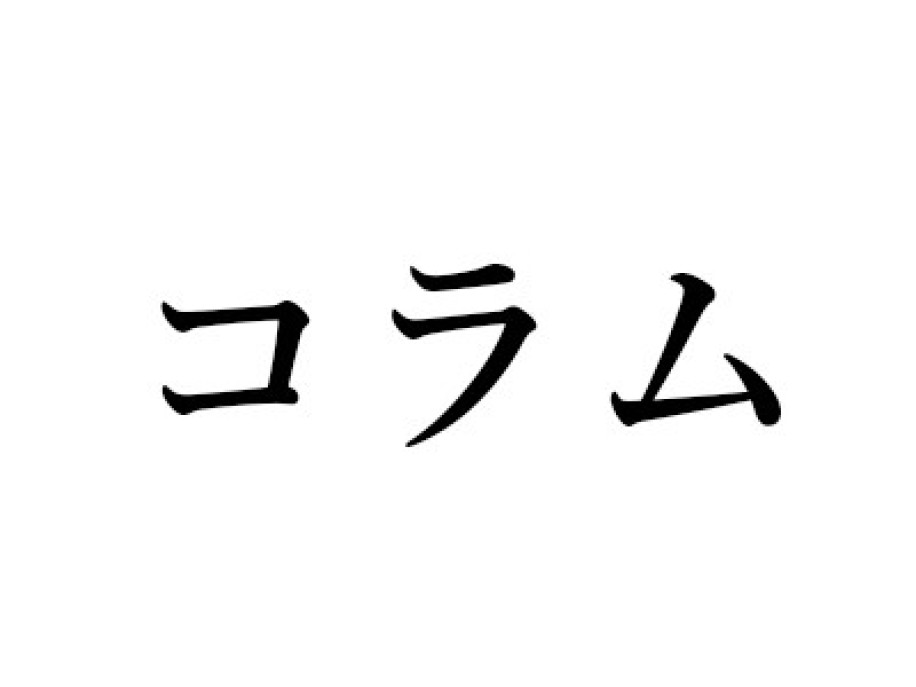書評
『無限抱擁』(青林堂書店)
日常に潜むチェルノブイリ
カメラマンと同行取材するとき、私のペンという道具はまだまだカメラに比べ暴力的ではないなとホッとしたり、その分、対象に対して甘いのではないかとも疑う。本橋成一さんに『上野駅の幕間』(現代書館)で出会ったとき、じつによく〈人間〉が写っているので、これは相当、瞬間を狙ってバシャバシャやったのだろうと思った。だがそれは錯覚だった。一、二度仕事をともにしたが、彼はなかなかシャッターを押さない。手に隠れる小さなカメラ一つである。最初は話を聞くだけだ。次に行くと家族写真を撮る。それを届けにいって喜ばれる……というふうに徐々に町に入っていく。
チェルノブイリ原発事故は人類が直面した最大のアポリアである。「繁栄」や「技術」の果てが緩慢な大量死、さらにいのちの「絶滅」をもたらすかもしれないことを示した事故である。
しかしこの写真集『無限抱擁』(リトル・モア)で、本橋成一は血気にかられて事故に立ち向かってはいない。
五年目のチェルノブイリ。冒頭の何枚かの写真では茫然と立ちつくすしかない感じだ。巨大な「石棺」、動かない観覧車、教材の散乱する学校、椅子のある道。かつて人のいたはずの風景……。二度と来るところではない。
しかし、この写真集はその後、一転して、チェルノブイリから百七十キロの町、チェチェルスクの人びとの暮らしを追う。三年半に七回通ったという。
春の花嫁。木は茂り花は咲く。川魚のフライに塩豚に黒パンに手作りのウオツカ。花嫁を泣いて祝福する祖母、レースのカーテンの窓に植えられたトマトの苗、盛大な洗濯物、雪解けのソージ川、厳寒の森で狩りをする男たち……。
ここには当たり前の、つつましいが豊かな生活がある。文字通り大地の恵みを手で受けるような、私たち都市の日本人には失われた暮らしである。
しかし風下の町チェチェルスクも汚染されていた。洗濯物に測定器を当てれば針ははね上がり、しとめた鹿は保健所の検査を受けなければ食べられない。川の汚染は通常値の二十倍だ。
「スラーバは七日前に十歳で死んだの。だけど、スラーバが川で泳いだり、森で遊ぶのをやめさせることはできなかったわ」(三十歳の母親)
彼ら居住禁止区域に戻って住む人をサマショール(わがままな人々)という。しかし老人たちにとって汚染されていようといまいと、「彼らの大地」にはちがいないのだ。
「そりゃ不安さ。いつでも喉や胸のあたりのことが気になってしょうがないよ。でもね、どうせここで生きるなら、楽しく生きなきゃソンだと思わんか?」
成田の農民、水俣の漁民、東京下町を地上げで追われた老人たちと同じひびきの言葉である。
本橋成一はここでも略奪的に写真をとってはいない。ロシアの人びととサウナに入り、汚染されたパンや肉を共に食らいながら、家族を写し、人間の愚かしさを許してふたたび芽ぶく大地に向かって静かにシャッターを押した。だから一枚一枚がとても楽しく、美しい。
【旧版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする