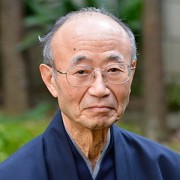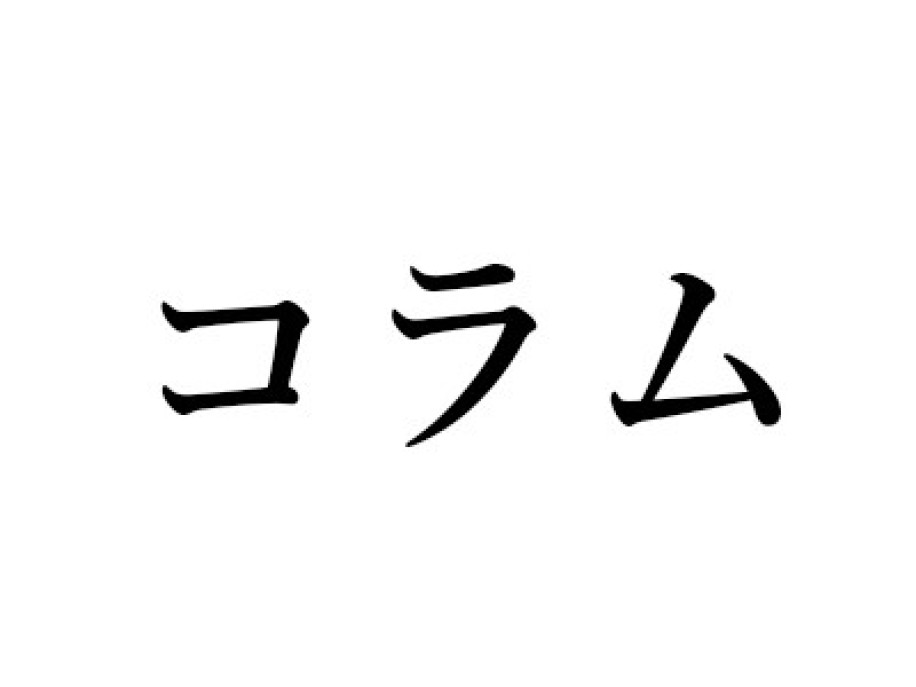書評
『蓮如―われ深き淵より』(中央公論新社)
悲哀と苦悩の自立描く戯曲
蓮如がついに芝居の主人公になった。蓮如は本願寺中興の祖といわれ、親鸞から数えて八代目の後裔(こうえい)にあたる。ときは十五世紀、応仁の乱で知られる激動のまっただなかを生きぬいた人物だ。足利将軍家とよしみを通じ、地方豪族を懐柔しただけではない。近畿の先進地域を拠点にして、念仏の運動をまたたくまに民衆のあいだにひろめた。
生涯に五夫人をめとり、二十七人の子女をつくったことでも知られる。教団を組織化することに敏腕をふるったが、その布教態度は平等の感覚につらぬかれていた。かれは八十五歳の天寿を全うしたが、ドラマは三十九歳から五十七歳までの苦難にみちた自立の時期を切りとり、四幕仕立てで構成されている。
四十すぎまで父と継母の下風にあって部屋住みの生活を強いられていた蓮如の姿が、まず舞台に浮かびあがる。荒涼たる鳥辺野の葬地を背景に、座頭や辻(つじ)の女を配した時代の闇(やみ)が地をはうような民衆の声とともに再現されていく。
やがて、法主職をついだかれの精力的な活動で教団は勢力をひろげていったが、旧仏教を代表する天台宗延暦寺がその前面に立ちはだかり、京都・大谷にあった本願寺を焼き討ちにしてしまう。一時的な休戦を決意した蓮如は一門一族とともに近江にのがれ、さらに北陸の吉崎をさして落ちていく。
親鸞の思想を大衆の心に響かせようと苦心惨憺(さんたん)する蓮如、そして夫人と子女をつぎつぎに失って悲哀の底に打ちひしがれる蓮如の姿が大映しにされていく。かれの作と伝えられる京の子守唄が効果的に使われているのも新趣向だ。最終場面で、はかなくなった妻のからだを抱きしめ、静かな無常感をたたえる「白骨のふみ」を書き写すシーンがでてくる。演出上の効果もさることながら、勘どころをおさえた工夫である。
蓮如の時代がやってきたのかもしれない。今日、宗教の意味を考えるうえでも示唆的な作品になっているといえるだろう。
ALL REVIEWSをフォローする