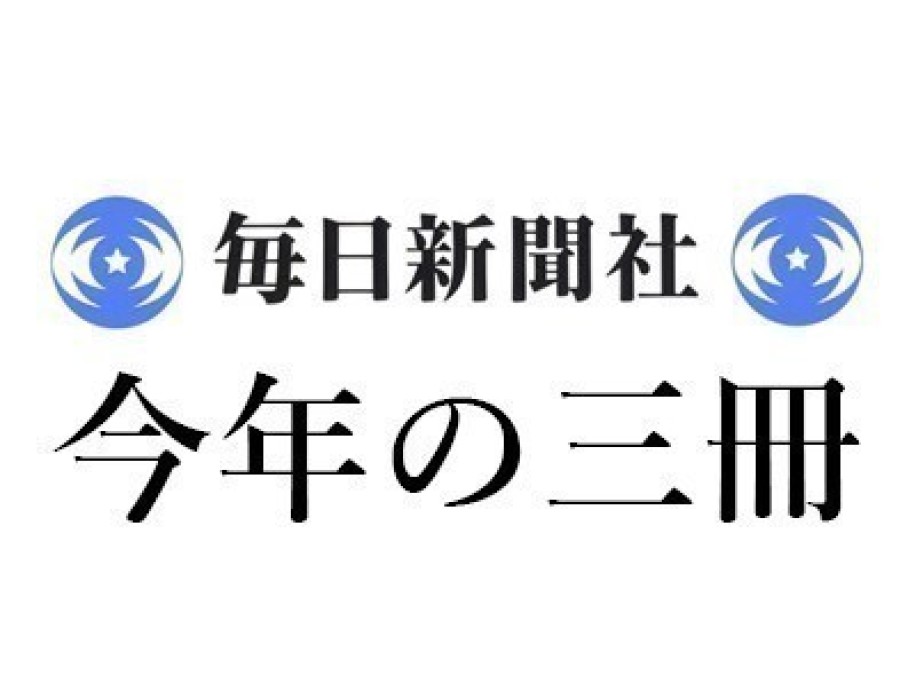書評
『即興詩人』(岩波書店)
我は身を彼(かの)水上の柩(ひつぎ)に托(たく)して、水の衢(ちまた)に入りぬ。樓屋軒をならべて石階の裾は直ちに水面に達し、復(ま)た犬ばしり程の土をだに着けず。家々の穹窿門(きゆうりゆうもん)は水に架して橋梁の如く、中庭は大(おほい)なる井(ゐど)の如し。この中庭には舟に帆掛けて入るべけれど、舳艫(ぢくろ)を旋(めぐ)らさんことは難かるべし。海水はその緑なる苔皮をして、高く石壁に攀(よ)ぢ登らしめ、巍魏々(ぎぎ)たる大理石の宮殿も、これが為に水中に沈まんと欲する状(さま)をなし、人をして危殆の念(おもひ)を生ぜしむ。
勧められて『即興詩人』を読みはじめたのは、今年の五月のこと(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1993年)。毎日ちびちび読んでいたら、最後のページにたどりつくまでニカ月かかってしまった。右に引用したのは、ベニスを描写した一節である。水上の柩とは、ゴンドラのことをたとえた言葉。
ぱっと読んですらすら頭に入ってくる、という文章ではない。けれど、繰り返し読んでいるうちに、じわーっとわかってくる。その「じわーっ」の中身がつまらないものだったら、苦労して読む必要はないのだけれど、『即興詩人』は病みつきになってしまう美しさだった。
普通なら「病みつきになってしまうおもしろさ」となるところかもしれない。が、この本の場合、筋や内容がおもしろくて読む、というのとはちょっと違う。鷗外の文章の美しさを、味わいたくて読む。その美しさは、女性にたとえるなら、若いアイドルのような誰にでも受け入れられるわかりやすい美しさではなく、人生を深く生きてきた熟年の女性の、にじみでるような美しさだ。
「読んでいる時間がきれい」――これが、終始抱いた感想だった。疲れて乗る電車のなかで、仕事のあいまに机の上で、眠りにつく前のベッドの上で。『即興詩人』の一ページ一ページを私は、古いオルゴールをそっと開いて、その音色に耳を傾けるような気持ちでめくっていた。
「わかりにくい」には、いろいろなわかりにくさがある。鷗外の場合は、旧仮名、文語体が、若い世代には壁になってしまっているようで残念だ。けれど、そのよさは、やはり旧仮名、文語体でないと伝わってこない。ちょっとこらえて、慣れることが必要だろう。さすがに『源氏物語』や『平家物語』ほど時がたっていないので、根気よく接しさえすれば、意は自ずから通じてくる。
口あたりのいい、スナック菓子のような文章ばかり読んでいると、言葉をかみくだく顎の力が弱ってしまう。『即興詩人』に出会って、たまには骨のある、わかりにくい文章を読むことも大切だと思った。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
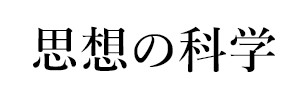
思想の科学(終刊) 1993年11月号
ALL REVIEWSをフォローする