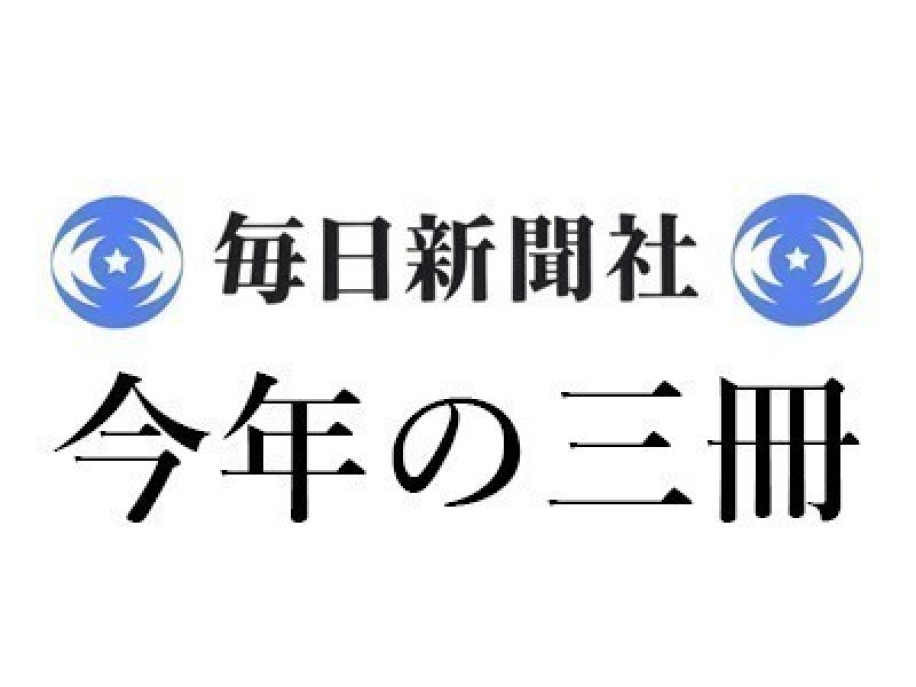書評
『久生十蘭傑作選II 黄金遁走曲』(社会思想社)
『久生十蘭傑作選』
大学時代に年下のちょっと生意気な男の子が「凄い本ですよ」と言って、夢野久作の『ドグラ・マグラ』を貸してくれた。三一書房から『夢野久作全集』全七巻が出る二年ほど前のことで、確かハヤカワ・ポケット・ミステリ版だったと思う。それまで私は夢野久作の名前は全然知らなかった。『ドグラ・マグラ』は確かに凄い本だった。脳天を直撃された。私の頭は、腕のいいバーテンダーの手にかかったカクテルのシェーカーになったようだった。国語の教科書にも文学史関係の本にも全然出て来ない夢野久作という作家が、こんなにも「読むことの喜び」を与えてくれるというのが不思議だった。
だから、『夢野久作全集』は待ってましたとばかり読みふけった。夢野久作がおもな発表の場としていたのは昭和初期の雑誌『新青年』で、おりしも立風書房から『新青年傑作選』全五巻が出版されたので、やっぱりこれも嬉々として読んだ。それは、大げさではなく「宝庫」のようだった。宝の山にザクザクと踏みこんだようだった。私好みの“読みもの”がこんなところにいっぱいかくされていた!! と思った。教科書とも文学史の本ともほとんど無縁のこんなところに。そこは、日本の文学の世界ではどうも「異端」と呼ばれているところらしかった。
久生十蘭の名前を知ったのもそのころのことだった。そのころ――一九七〇年代前半には、夢野久作、久生十蘭、小栗虫太郎、牧逸馬といった「異端作家」を評価する動きがあって、久生十蘭は気になっていたのだが、何しろ私は夢野久作でそっち方向(=「異端」好みの志向)の精力を使い果たした気分になって、やがてスーッと、より軽妙な海外モノのほうへと惹き寄せられてしまった(具体的に言うと、早川書房の『異色作家短篇集』のシリーズ。ジャック・フィニイとかジェイムズ・サーバーとかジョン・コリアとか。あと、このシリーズには入っていないがデイモン・ラニアンとか)。
平成元年の暮れに出た『モダン都市文学II モダンガールの誘惑』というアンソロジーでも久生十蘭の「心理の谷」が面白かったり(関係ないが、村松ちゑ子という人の「篠山しか子の一姿態」という短編の奇怪滑稽な味に驚いた)、作家の橋本治に「中野さんみたいな女は久生十蘭の小説の中にもうちゃんと描かれていたんだよ」などと言われたり、エルンスト・ルビッチ監督の一九三二年のすばらしくかっこいいコメディ映画『極楽特急』を最近見て「私好みのコメディの原点にして頂点の映画を見た!」と大興奮していたら、翻訳家の芝山幹郎が「ルビッチからまっさきに類推するのは久生十蘭だ」と書いていたり……なんだか、いろんなことが私を久生十蘭のほうへと押しやっている感じがするのだ。
というわけで、ついに社会思想社の現代教養文庫から出ている『久生十蘭傑作選』全五巻を買いこんだ。まず『久生十蘭傑作選II 黄金遁走曲』から読んでみる(この中には「ノンシャラン道中記」「黄金遁走曲」「花束町一番地」「モンテカルロの下着」の四編が収録されている)。
うーん……まいった。面白い。確かにルビッチだ。
その魅力をランボーにひとことで言ってしまうならば、「お洒落」と「笑い」がしっかりと手を結んでいるところだ。これは案外に難しく、そして私の一番瞳れのセンである。
十蘭は一九二九年から三三年までの四年間をパリで過ごし、レンズ光学と演劇を学んだという人だ。「ノンシャラン道中記」は、パリに留学する一組の男女(コン吉とタヌ子)が南ヨーロッパを旅行する話で、冒頭からずうっと、「油漬鰯(サルディン)」「寄席(キャヴァレ)の口上役(コムメエル)」「一立(アン・リットル)ずつ」……とフランス語のルビつきで、おのずから軽妙優美な「お仏蘭西(フランス)の香り」がたちこめるわけで、それ一本槍で固めたら、まさにイヤミ(赤塚不二夫『おそ松くん』の、あの西洋カブレ知識人の戯画的キャラクター)だが、十蘭はそこに平然と、歌舞伎調の、あるいは江戸の戯作調の文体を突っ込んだり、たとえば「みっちゃんやァ!」「あいよゥ(ヴォアラァ)!」などという日本の俗臭にみちたセリフをちりばめたりしてしまう。そういうセリフを突っ込んでも、お洒落な世界はいっこうにこわれない。
少したとえはズレるかもしれないが……私はつねづね、「全身シャネルでかためるのがお洒落だなんて思わない。たとえ、それがピタッと決まってもお洒落の中級。シャネルと、そこらのスーパーで買ったようなものや昔からの愛着の品なんかをゴチャまぜに組み合わせて、それがピタッと決まってこそお洒落の上級者。しかも、ファッションで人を威圧するのではなく、人をほほえませるようなユーモアやズッコケが入っていたらさらに上級」と確信する者であるが、「ノンシャラン道中記」には、それと似た上級お洒落を感じる。
時どき冗談が上滑りして空疎な感じがするところもあるが、冒頭の「八人の小悪魔」など完璧じゃないだろうか。こんな上級娯楽を生んだ一九三〇年代とは、やっぱり世界的に特殊な時代だったような気がする。
――なあんて。ああ、言いたいことの十分の一も言えてない。ついつい前置きが長くなったのが失敗だった。ごめんなさい、次回でこの続きを。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

月刊Asahi(終刊) 1993年6月号
ALL REVIEWSをフォローする



![極楽特急 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41TBe%2Bp9UML.jpg)