書評
『旧聞日本橋』(岩波書店)
明治幻燈記
田山花袋『東京の三十年』、馬場孤蝶『明治の東京』、内田魯庵『思ひ出す人々』、そしてこの長谷川時雨『旧聞日本橋』(岩波文庫)は“文庫で読める東京”のなかでもとりわけなつかしい。時雨は本名をやすといい、日本橋の代言人の総領娘に生まれ育った。“あんぽんたん”と愛称される夢見がちでおっとりしたところを持ち、気が良く、切り離れのいい彼女の語りからは、明治の町がまざまざと目に見えるようだ。商家の急な勾配の黒い瓦屋根がつづく町。家のま向かいには終日(いちにち)塩せんべいを焼いている婆さんがいる。井戸の水は玉川上水。べっこう細工、俥宿(くるまやど)、運送店、八百屋、化粧品問屋が並ぶ。その夕方の風景。
「夏の下町の風情は大川から、夕風が上潮と一緒に押上げてくる。洗髪(あらいがみ)、素足、盆提灯、涼台、桜湯――お邸(やしき)方や大店(おおだな)の歴々には味わえない町つづきの、星空の下での懇親会だ」
おかみさんは肌ぬぎ、お父さんは褌(ふんどし)一つで渋団扇(しぶうちわ)をバタバタしながら更けるほどに話ははずむ。怪談ばなし。新内がくる。義太夫がくる。煙草の火をもらって話してゆくのもある。なんという自由の天地だろう。
身内の人びとが愛情深く語られる。父方の祖母は小りんといって、文化生まれのすがやかな老女。黒しゅすの細い帯を前に結んでいた。年をとってもあわれっぽくなく、自分の生活様式をくずさない。八十八の春に死ぬまで、小伝馬町の大和田の鰻の中串を二ツ食べるのと、日髪日風呂を習慣にしていた。
「おしゃれではないたしなみだ、おれは美女だと己惚(うぬぼ)れるならおやめ」
このおばあさん、身近でも助けるべきものは助けるが、決して同情の安売りはしなかった。伊勢の五十鈴川の庄屋の生まれである。従兄という九十のじいさんが訪ねてきたら、その人には赤とんぼくらいのチョンマゲがついていた。人生五十年以上逢わなかった二人はしきりになつかしがり、血引き(血縁というくらいの意味か)のおたけを呼んで、人混ぜしないで御酒を飲む。
「やがておじいさんが太鼓をたたき、女のひとが三味線を弾いて、祖母が踊りはじめました」
二人の老人が浮かれて伊勢音頭を踊るかげが障子にうつる。階段下でのぞいた子どもの目に映ったまぼろし……。
一方、母方のおじいさんは湯川金左エ門といって「木魚の顔」である。背の低い醜い人で、旧幕臣の流れのせいか、ご維新後は「ピッタリと、ものに廻(めぐ)りあわぬ」人であった。四十すぎてから硫黄に夢中になって小笠原に行ったりしたが、世界の動きについて行けず「自己流の工夫」しかできないで終わった。死ぬとき「老爺(おじい)さん、硫黄鉱山(やま)が売れましたよ」と孫のやすがささやくと、「ほ」といって満足そうに瞑目した。
この木魚の祖父のたった一人の妹「勝川花菊の一生」も実にいい話である。維新後、芸者になった旧幕臣の娘は多いがその一人で、佐兵衛という旦那を持ってぜいたくの限りをつくしたが、その人が身代を無くしても別れられず、もう一人「お角力(すもう)」というよく働く男もいた。要するに三角関係だった。花菊は陋居(ろうきょ)に、お角力の膝を枕にして、やさしく撫でられながら生涯を終えた。そしてお角力は一人で通夜をし、すたこら棺桶を一人で火葬場(やきば)にかついでいく。
「だが、私の目には笑えない、生涯のそりとした、そのくせ誠実な大男が、愛した女の亡骸(なきがら)を入れた桶をしょって、尻はしょりで、暗い門から露路(ろじ)裏を出てゆく後姿をかなしく思いうかべられた」
こういう人がかつて生きていた、というだけで涙が出る。「幻燈」というのは幻の向こうに燈火を見ることなのだな、と気づく。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
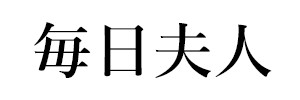
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする




































