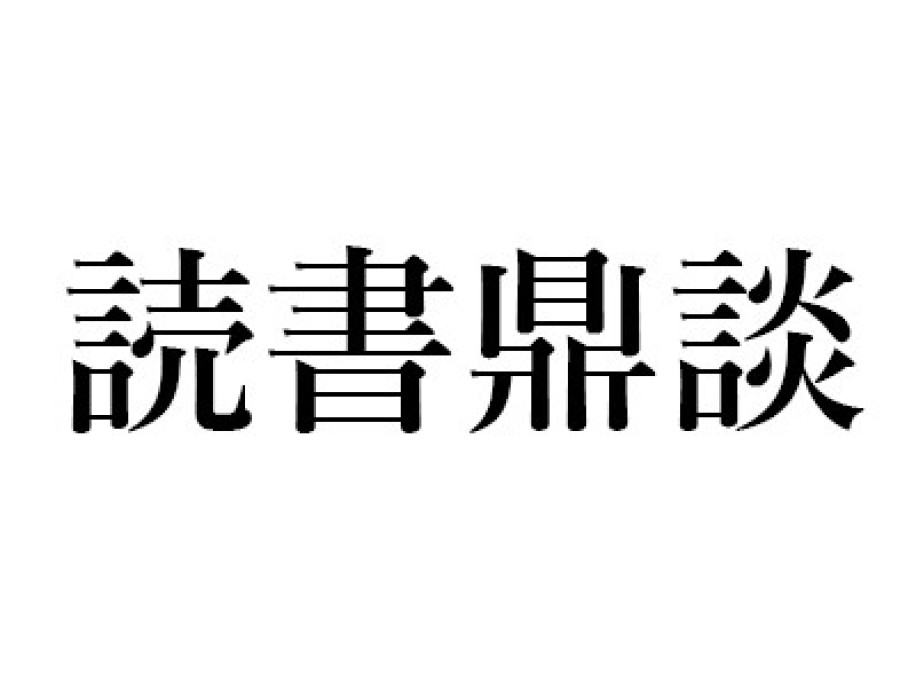書評
『如何様』(朝日新聞出版)
真贋・自他の境界線かき乱す
『如何様』の表題作を読みながら時おり思い浮かべていたのは、昨年末の「紅白歌合戦」に登場した“AIで復元した美空ひばり”だった。これには否定的な声もあがった。しかし、その人工の声に歌姫の神髄を感じて涙するファンに、「模造品に感動するなんて」などと言う気には、私はなれない。「如何様」は、真贋とはなにか、人や物の同一性とはなにか、自己と他者の境界はどこにあるか、人はなにをもってその個人になるのかといった存在論的、イデア論的な問いを真正面から投げかける野心作である。
物語の舞台は、爆撃の記憶もいまだあせない戦後の東京。語り手の女性は記者兼探偵として、画家「平泉貫一」の自宅を訪ねる。ある美術編集者から、この画家が平泉貫一本人なのか調べてほしいという奇妙な依頼を受けてのことだった。貫一は戦前、そこそこ名の知られた水彩画家だったが、復員時には以前とは似ても似つかぬ容貌になり、性格も一変していた。
とはいえ、身分証となる書類一式を携えており、帰還を待ちわびていた両親はこの男を一人息子として受け入れ、欣喜(きんき)する。本作後半には、夫を丸呑みにした蛇を夫とみなして共に暮らす妻子の例も出てくるが、そこにこの夫の“夫性”があると思うなら、だれにも否定できないだろう。
そのうち、貫一はふらっと出奔してしまったという。
語り手は、戦前の貫一の顔をろくに知らない妻「タエ」のほか、貫一の妾、画廊主、軍の部隊長、軍医、分隊長、分隊長補佐と、聴き取りを進めていく。この人々は各々の観点から、平泉貫一の真贋を判断する(あるいは、しない)。美術鑑定でいえば確固たる証明書となるのは来歴であり、貫一はその点では完璧な“真作”である。また、真作だけが纏(まと)うとベンヤミンの言った“アウラ”や、画家としての技術、資質を論拠として挙げる者もいる。
やがてわかったのは、貫一が抜群の贋作技術を生かして軍の仕事をしていたことだ。彼は偽造の行程を楽しみ、贋作にかかるときは、元の画家の生活スタイルまで模倣し、その「性格にしつこいほど自分を寄り添わせ」たという。平泉貫一とは、レプリカの連続体のようなものなのか?
本作で、真贋や自他などの二者を分かつものの象徴となるのは、坂である。タエは自宅近くにある坂を「だまし絵」みたいと評する。あるいは、語り手は「昼が夕方になるように、この世が坂道であの世に変わるように徐々に変化していったとしたら、その切り替わり点はどこに存在するのか」と自問する。
人やものはいつ「自」/「真」であることをやめ、「他」/「贋」になるのか? 「本物が消え去って、あるいはそれぞれに部分的な本物があり、それの寄せ集めが完成品だとして、その本物という性質はどこに存在するのだろうか」という語り手の問いかけには、「テセウスの船のパラドックス」が鮮やかに刻印されている。
昨今、川上弘美『某』や、平野啓一郎『ある男』など、人のアイデンティティの根幹を揺さぶり、見つめ直す小説の刊行が続いているのは、偶然ではないだろう。自分が現実世界に実在しているのを疑いたくなることばかり起きるのだから。
それにしても、語り手は最後まで名前も来し方も風貌もわからず、ほぼ声だけになってこの物語を伝える。人々がときに驚き、違和感を抱く語り手さん、あなたは何者ですか? 真に存在するのですか? 私にはそれが如何様(いかよう)にも気になりましたよ。とくにダンスの場面で。
ALL REVIEWSをフォローする