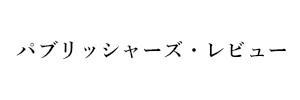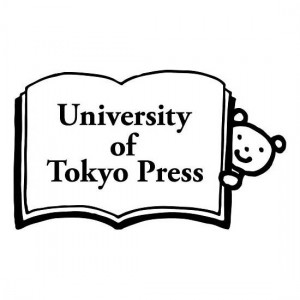自著解説
『不戦条約: 戦後日本の原点』(東京大学出版会)
「国策手段としての戦争を放棄する」――1928年、世界史上はじめて国家間の戦争が否定された。論争の絶えない「戦争放棄」問題に歴史的側面から迫った注目の書、『不戦条約』。その著者、牧野雅彦広島大学教授によるエッセイを特別公開します。
1 今日の憲法改正論議の焦点となっている自衛権をめぐる問題は、国際連盟の集団安全保障の原則をめぐるアメリカ合衆国とフランスの対立のうちにその原型が出されていた。日本国憲法第九条の思想的源泉としてしばしば引き合いに出されるサーモン・O・レヴィンソンの「戦争違法化」論の果たした役割も、アメリカ・フランス両国の外交的駆け引きと、そこに示されている国際紛争の解決方法に対する両国のアプローチの相違を背景にすることによって明確なものとなる。
2 第二次大戦後に国際連合を主導することを求められた時に、アメリカは不戦条約締結当時に拒否していた集団安全保障の原則の受容の方向に一歩踏み出すことになった。そこで行われた決断の意味、国際紛争の平和的解決のための機構としての国際連盟と国際連合の相違も、両大戦間のアメリカの立場を踏まえてはじめて理解することができる。アメリカの占領下におかれた日本の選択の意味もそうした文脈で検討されなければならない。
3 不戦条約の締結によって国際連盟とアメリカ合衆国、ヴェルサイユ体制とワシントン体制とは緩やかな形で連結することになるが、これは東アジアにおいて権益を有する日本にとって重要な意味をもっていた。当時の外相・首相であった田中義一は不戦条約の調印のために派遣した内田康哉を通じて欧米主要国との調整に努めている。その意味において不戦条約が締結されたこの時期は、満州事変を発端として国際連盟脱退に至る日本外交の起点であると同時に、第二次大戦後の東アジアをめぐる国際環境の原型を提示するものでもあった。中国に新たな統一政権が誕生して国際社会のなかで自己主張をはじめ、その中国とロシア、日本の間で朝鮮もまた民族の自立を求めていく。まさにそうした構図に日米両国がどう取り組むのかがそこでは問われていたのである。
4 そうした観点から振り返るならば、不戦条約の文言「人民の名において」をめぐる論争もたんに国内政局の文脈でなされた不毛な解釈論に止まらない意味をもっている。アジアの中で唯一近代化に成功して一等国となった日本にとって、西洋の国家原理を受容するとはどういうことか、国家の基本原則としての憲法とその運用はどのようにあるべきか、そうした問題を「人民の名において」をめぐる論争はあらためて突きつけていたのである。論争の争点の一つとなった美濃部達吉の「天皇機関説」に代表される国家学説も、そうした文明史的な観点から再検討することが必要であろう。
[書き手]牧野雅彦 (広島大学教授)
戦後日本の原点としての不戦条約とは?
二月に刊行された『不戦条約』の副題「戦後日本の原点」は、出版社の要請で宣伝のためにつけたものではない。 不戦条約締結時に日本が置かれた国際環境に、象徴天皇制と憲法第九条の戦争放棄を軸とする戦後日本の政治体制の前提となる一連の諸問題がほぼ出そろっているからである。1 今日の憲法改正論議の焦点となっている自衛権をめぐる問題は、国際連盟の集団安全保障の原則をめぐるアメリカ合衆国とフランスの対立のうちにその原型が出されていた。日本国憲法第九条の思想的源泉としてしばしば引き合いに出されるサーモン・O・レヴィンソンの「戦争違法化」論の果たした役割も、アメリカ・フランス両国の外交的駆け引きと、そこに示されている国際紛争の解決方法に対する両国のアプローチの相違を背景にすることによって明確なものとなる。
2 第二次大戦後に国際連合を主導することを求められた時に、アメリカは不戦条約締結当時に拒否していた集団安全保障の原則の受容の方向に一歩踏み出すことになった。そこで行われた決断の意味、国際紛争の平和的解決のための機構としての国際連盟と国際連合の相違も、両大戦間のアメリカの立場を踏まえてはじめて理解することができる。アメリカの占領下におかれた日本の選択の意味もそうした文脈で検討されなければならない。
3 不戦条約の締結によって国際連盟とアメリカ合衆国、ヴェルサイユ体制とワシントン体制とは緩やかな形で連結することになるが、これは東アジアにおいて権益を有する日本にとって重要な意味をもっていた。当時の外相・首相であった田中義一は不戦条約の調印のために派遣した内田康哉を通じて欧米主要国との調整に努めている。その意味において不戦条約が締結されたこの時期は、満州事変を発端として国際連盟脱退に至る日本外交の起点であると同時に、第二次大戦後の東アジアをめぐる国際環境の原型を提示するものでもあった。中国に新たな統一政権が誕生して国際社会のなかで自己主張をはじめ、その中国とロシア、日本の間で朝鮮もまた民族の自立を求めていく。まさにそうした構図に日米両国がどう取り組むのかがそこでは問われていたのである。
4 そうした観点から振り返るならば、不戦条約の文言「人民の名において」をめぐる論争もたんに国内政局の文脈でなされた不毛な解釈論に止まらない意味をもっている。アジアの中で唯一近代化に成功して一等国となった日本にとって、西洋の国家原理を受容するとはどういうことか、国家の基本原則としての憲法とその運用はどのようにあるべきか、そうした問題を「人民の名において」をめぐる論争はあらためて突きつけていたのである。論争の争点の一つとなった美濃部達吉の「天皇機関説」に代表される国家学説も、そうした文明史的な観点から再検討することが必要であろう。
[書き手]牧野雅彦 (広島大学教授)
パブリッシャーズ・レビュー 2020年春号
「パブリッシャーズ・レビュー」は、東京大学出版会(5・11月)、白水社(1・4・7・10月)、みすず書房(3・6・9・12月)の三社が、各月15日に発行するタブロイド版出版情報紙(無料)です。
ALL REVIEWSをフォローする