書評
『難民たちの日中戦争: 戦火に奪われた日常』(吉川弘文館)
欠落してきた側面 初の本格叙述
本書は、「従来の日中戦争の叙述ではほとんどかえりみられることのなかった」戦争難民(プロローグ)について、「難民にとっての日中戦争は、・・・平和な日常生活が、あるとき突然奪われ、難民化せざるを得ないという事実がすべてであった」(エピローグ)ことを、日本で初めて本格的に叙述した歴史書である。本書は、日中全面戦争における主要な作戦において生じた戦争難民の実相を時系列的に整理したうえで、利用できる統計資料を提示しながら、数千万人におよんだ戦争難民の被害と犠牲の全体像を叙述している。
日本人の日中戦争の記憶や認識において、戦争難民の問題が大きく欠落してきた最大の原因は、戦場がすべて中国大陸であり、戦時中の日本国民は、悲惨な戦争難民の実態を目撃することがなかったからである。戦場の日本軍兵士も、難民は軍の作戦の前後にその周辺地域で発生した問題であり、直接目撃することはまれだった。日本軍の目の届かない地域に避難した難民が居住地に戻れたとしても、その時日本軍は他地域に移動してしまい、家を破壊され、焼却され、家族を失い、地域社会を破壊された難民たちの悲惨を目撃することはまれだった。
本書は難民の視点からとらえなおした日中戦争史である。膨大な戦争難民をつくりだした日本軍の侵略、加害の実相について、作戦地域ごとに事例をあげて、丁寧に記述している。難民にとっての日本軍は、都市・村落の破壊、放火、住民の殺害・使役、性暴力、略奪等々を禁止した戦時国際法を全く無視した不法、無法の軍隊であった。
評者は『日中戦争全史(上・下)』(高文研)を書いたが、日本軍の作戦展開を中心にした記述になった。本書は拙著に欠落した大切な側面を叙述した日中戦争史であり、現在の国際問題化した難民問題の理解へも通ずる。多くの人に読んでほしい待望の書である。
[書き手] 笠原 十九司(かさはら とくし・都留文科大学名誉教授)1944年、群馬県生まれ。主な著書に『日本軍の治安戦』岩波書店・2010年、『海軍の日中戦争-アジア太平洋戦争への自滅のシナリオ』平凡社・2015年、『日中戦争全史(上・下)』高文研・2017年など多数。
初出メディア
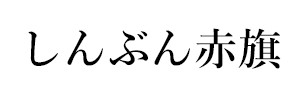
しんぶん赤旗 2020年12月13日
ALL REVIEWSをフォローする





































