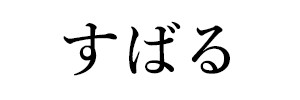書評
『真ん中の子どもたち』(集英社)
世界標準の子どもたち
二〇一一年以来の、温又柔待望の大きな新作中篇小説である。この間、温は、長編エッセイ『台湾生まれ 日本語育ち』などの数々のエッセイ、小さな物語、歌詞、詩など、多彩な形の文章で自身の文学を深化させてきた。けれど、やはり小説でこそ、温文学は最大の真価を発揮すると私は思う。なぜなら、小説は「私」の声から始まって、「私」ではない声を引き寄せ、紡ぎあげていくものだから(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2017年)。実際、本作は、最初の作品集『来福の家』をダイナミックに変奏し始めている。
「好去好来歌」「来福の家」の主人公たちは台湾人の両親を持つ、温自身や温の家族と思しき人物に限りなく近い存在だったが、『真ん中の子どもたち』のミーミーこと天原琴子は、温の境遇と似ていながら、父親が日本人であり琴子も日本国籍を持つ、という点で決定的に異なる。
それだけでない。留学先の上海で琴子とともに中国語を学ぶ、リンリンこと呉嘉玲は父が台湾人、母が日本人で、本人は台湾籍。同じく留学生の龍舜哉は、両親とも日本国籍を持つ、元中国人である。日本育ちで日本語ネイティブであるこの二十歳前後の三人が、上海でのひと月の間に、カテゴライズの粗暴さに直面しながら、自分たちのあり方を肯定していく過程が描かれる。
人を線引きする暴力は、思わぬところから襲ってくる。片言の中国語を操れるミーミーは、留学先のクラスで褒められるが、母親が台湾人だとわかったとたん、中国人学生から「それなら、どうしてその程度の中国語しか話せないの?」と問われて、傷つく。また、厳格な中国語の教師から発音について、台湾人特有の南方訛りという悪い癖は直すよう指摘され、さらに、スピーチの時間に母の話す言葉が「中国语」であると述べると、「中国语」ではなく「普通话」だ、と訂正される。行きずりの男性からは、母親が日本人ではないのなら日本人と名のるべきではない、と言われる。ミーミーは次第に自信を失い、自分を見失っていく。
片親が台湾人であるミーミーと自分は特別な存在だ、と誇りをいつも口にするリンリンも、知り合った中国人の男から、リンリンの父親は台湾人などではない、台湾人など存在しない、南方訛りの中国語を話す中国人だ、と言い放たれ、心を粉砕される。中国内を旅行するのに、台湾のパスポートなので疑われ、南方人として侮蔑的な扱いを受けたりする。
こういった事例は、その立場にない者からすると、些細な軋轢にしか見えないかもしれない。けれど、その立場に置かれた者には、逃れようのない決めつけであり、文字どおり心に傷を負う出来事なのだ。
ミーミーたちを追い詰めているのは、言語と国籍と血がすべてイコールで結ばれる単一民族国家幻想である。すなわち、日本人の親を持ち、日本国籍を持ち、正しい日本語を母語として話すのが、純粋な日本人、というアイデンティティのあり方である。このカテゴライズからはみ出す要素を持つ三人は、その線引きを突きつけられるたびに、アイデンティティの危機に突き落とされる。しかも、留学先の中国でも、幾重にも正統性を否定される羽目に陥る。
ミーミーの目を通して丁寧に描かれる三人のよるべなさに触れるたび、私が感じるのは、そのようなカテゴライズ、アイデンティティの作り方はもはや世界の現実に合っておらず、失効しているということである。なぜなら、世界中にミーミーたちみたいな人たちは増え続けていて、「普通」の存在となっていることは、世界の文学を読めばわかることだから。その意味で私には『真ん中の子どもたち』は世界標準の文学であり、今、まず世界で読まれてほしい日本語文学の筆頭だ。
言語、国籍、血が三位一体となった強固な幻想に対し、龍舜哉はそれを無効にする言葉で対抗する。
「どっちか、じゃなくて、どっちも、なんだよ」「どっちにもなれるってやつなんだから」
「(自分たちは)偽の、日本人」
「ナニジンだから何語を喋らなきゃならないとか、縛られる必要はない。両親が日本人じゃなくても日本語を喋っていいし、母親が台湾人だけれど中国語を喋らなきゃいけないってこともない。言語と個人の関係は、もっと自由なはずなんだよ」
言葉で放たれる暴力は、言葉によって解体することができる。舜哉の言葉によって次第に暴力から解放されていった三人は、現実には廃墟と化している純粋幻想を決定的に無意味にする、新しいアイデンティティの言葉を発見する。
それは植民地時代に日本からもたらされ台湾の言葉と化した、「アイノコ」という言葉だ。差別的な歴史と意味を含んだ日本語の「合いの子」ではなく、日本と台湾の間に生まれた子を指す、別の歴史と意味を含んだ、日本語起源の台湾の表現としての「アイノコ」。それをミーミーはさらに自分たち三人の個人的言語へと翻訳し、「愛の子」と言い換える。
この強烈なカウンターの意識と、限りなく肯定的で温かく柔らかいプライドのあり方! この「愛」の深度は、青春小説としての本作品を支えてもいる。社会の日常に潜む、ともすると見えなくなりそうな排除の力関係を、すべて言葉の姿として捉え、組み替えてみせる温文学の真骨頂だ。そして、すべてを言葉の様態に変換して描けるからこそ、温の真価が発揮されるのは小説なのだ。この時、三人の背後には、同じ境遇の世界中の「愛の子」たちが、ほの見えている。
最終章では、留学から戻って以降のミーミーの物語が叙述されるが、その展開を読みながら、温文学はもっと巨大な展開とフェミニズムをも含む広がりを持つ大長編に育ちうるだろうと、確信した。
なお、温文学の署名のような水餃子は、この作品でも美味しさを添えている。
ALL REVIEWSをフォローする