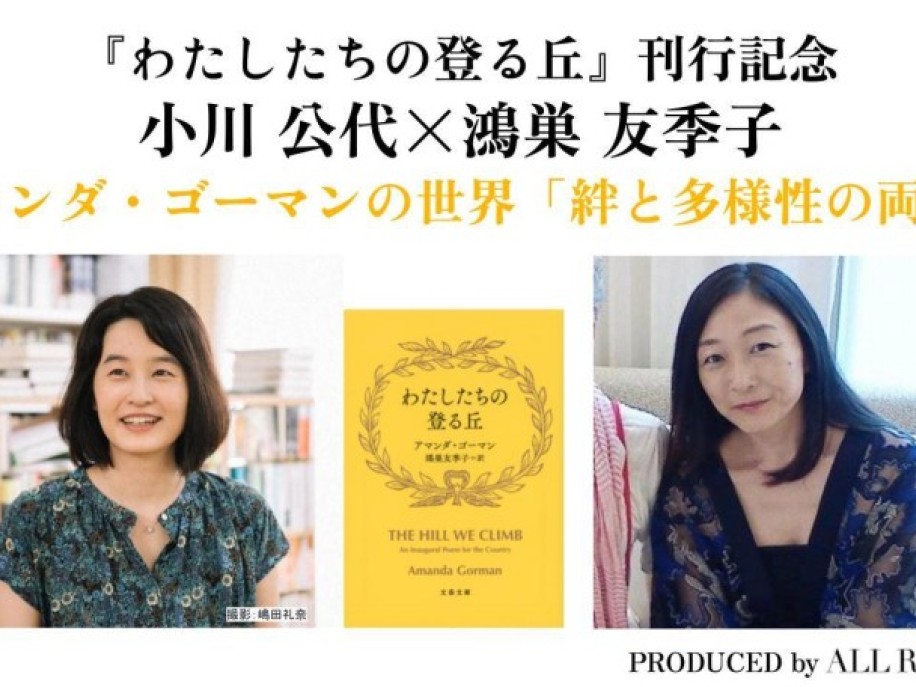書評
『明治大正 翻訳ワンダーランド』(新潮社)
名作を生み日本語を変えた創意工夫
故河盛好蔵氏は、常々「女性は翻訳に向いている、だから、私は女性の翻訳家を育てたい」とおっしゃっていたが、たしかに最近は翻訳学校などで学んだ女性の進出が著しく、しかも、みな、うまい。なぜそうなったのかといえば、それは翻訳は苦労の勘所が共通しているので、ある程度、技術の伝達が可能だからである。では、その翻訳の勘所はいつ頃から意識されるようになったのか?明治の翻訳者で有名なのは『噫(ああ)無情』『巌窟王』の黒岩涙香だが、涙香の『鉄仮面』を新訳と参照した著者はぶったまげてしまう。なんと、新訳では、最後、鉄仮面の遺体の仮面が剥がされると「それはモリスにまちがいなかった」となっているではないか!
ええーっ、鉄仮面が死んでいた!? スリリングな脱獄劇はどうした? すり替えのトリックは? 恋人とのドラマチックな再会は?
つまり、涙香は翻案どころか、原作にない筋を創って勝手に波瀾万丈の物語に仕立てていたのだ。涙香は原文の内容を頭にたたき込んだあとは、一切原文を見ないことを自慢したばかりか、盗作と言われるので強いて訳と称したが、自分では翻訳者だなどとは思っていないと堂々と嘯いていたのである。
涙香の豪傑訳に比べると、坪内逍遥から「英文如来」とも崇められた『周密文体』の創始者森田思軒(しけん)ははるかに現代的である。彼の翻訳姿勢はこうだ。「……もし能ふべくば、其の言葉の姿の西洋と東洋と違ツて居るのを、違ツて居るまゝ幾分か見せたいといふのが最初の考なのです」。この言葉に、著者は「翻訳者って、百年以上も前からおなじことを考えていたんだなあ」と深く頷く。翻訳は異なる文化の衝突なのだから、そのときの軋みを消し取ってしまっていいのかという問題である。森田思軒は、軋みを生かした適訳を日本語に探して七転八倒し、結果的に、その新しい翻訳文体で日本語も変えたのである。
この「日本語を変えた翻訳文体」ということで著者が注目するのが若松賤子(しずこ)訳の『小公子』。若松賤子は「女学雑誌」の発行人だった夫巌本善治(いわもとよしはる)の勧めでバーネットの翻訳に手を染め、「小公子」という絶妙なタイトルを考え出したが、刮目すべきは、むしろ、森田思軒を始めとする識者を驚嘆させたその文体。著者によれば、若松賤子の自然な訳文の特徴は、全知の神の視点で描かれた英文の三人称小説を、途中で主語と動詞を工夫して一人称にすり替えてしまう点にあるという。
三人称で書きだしながら、つぎの一文 He began to see に移るさいに主語を省いて、「何うやら不思議なことが、実際あつたのだといふことは」と原文の目的語を主部におきかえてスタートし、だが「呑込めては来ました」と、いったん主体の動詞を入れこんでギャップをならすようにしてから、その直後にlooked at(見た)という動詞を「眼の前」にと訳していよいよ言語主体を暖昧にし、パッと視点を切り替えてしまう。
この分析から著者が引き出した結論はこうである。
英語と日本語の三人称の本質的な違いを、この訳者は身体感覚でつかんだうえで日本語らしい文体に生まれ変わらせたのだと感じた。
このほか、無名の原作が日本で名作となった謎を解明する『フランダースの犬』など、明治の翻訳にまつわる創意工夫が、闊達な語りで明かされていく。
翻訳の文章が変わった。すると日本語も変わった。そして日本文学が変わった。
ALL REVIEWSをフォローする