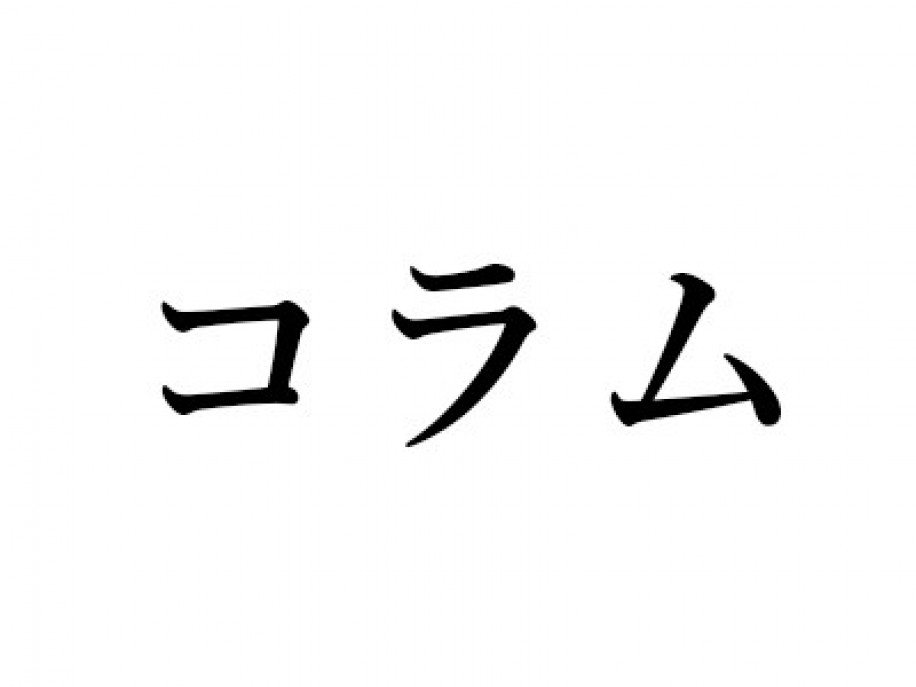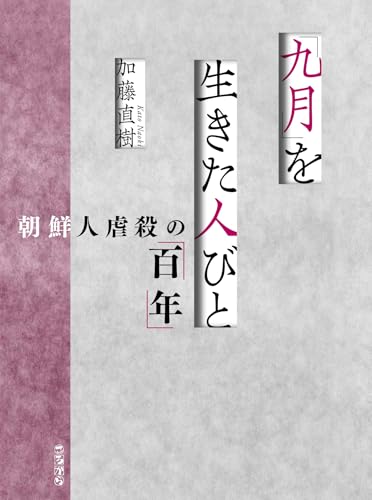書評
『誓願』(早川書房)
知を奪われた女性の戦いと希望
『侍女の物語』続編、独裁神権国家、ギレアデ共和国の「その後」の物語だ。侍女オブフレッドが、記憶と現在を手繰り寄せながら暗闇を進むように語る前作とは違い、三人の異なる話者が登場する。
一人は前作にも登場するリディア小母(おば)で、十五年を経て彼女は、権力の中枢に近づいている。女たちの館アルドゥア・ホールの奥深く、焚書(ふんしょ)の時代を免れて生き残った数少ない図書館の一つがあり、ほとんどの者が立ち入ることを許されない聖なる場所で、リディア小母は来し方を振り返る手記を綴(つづ)っている。
あとの二人は若い女性で、一人はギレアデ共和国の「司令官」の娘、「妻」となるため大切に育てられているアグネス、もう一人は隣国カナダで古着屋の娘として育っているデイジーだ。
オブフレッドの物語を読んでいれば、ギレアデ共和国が崩壊すると知っているし、そうでなくても、物語の鍵になる「幼子ニコール」をはじめ、謎の種は、比較的早い段階でわかる。にもかかわらず、次の展開が知りたくて、ページを繰る手は止まらなくなる。圧倒的におもしろい物語を味わいながら、秋の長い夜を過ごすに相応(ふさわ)しい一冊だ。
アグネスの物語は、ギレアデ版「小公女」といった趣がある。すさまじい腐臭が入り混じった少女小説のような感じ。デイジーのストーリーは、現代の延長線上にあるカナダのティーンエイジャーが、ノンストップで語るサスペンスドラマだ。しかし三つの語りの中、異彩を放つのはやはりリディア小母だろう。
ギレアデがアメリカ合衆国だったころには裁判官だった知的な女性が、逮捕され、強制収容に遭い、過酷な体験で人間性を奪われて、鋼の神経を持つ非情な「小母」に成り上がり、ギレアデの女としては頂点に上り詰める顚末が綴られる。産む道具でしかない女「侍女」階級を作るなど、徹底した男尊女卑による社会構造を持つキリスト教原理主義ディストピア、ギレアデ共和国がどのようにして出来上がったのかがあらわになる。
魅力の一つは彼女の文体で、<世界文学禁書>を「わたしだけの本棚」に隠し持ち、内心の自由を死守してきた彼女の文章には、ミルトンやロバート・フロストやマーガレット・ミッチェルやジョナサン・サフラン・フォアなどまで引用される。そのほかにも、ことわざや慣用句が多用され、鉄のような外見に隠されたリディア小母の内面の豊かさを感じさせる。
ギレアデは女性から人権を剥奪したが、その最たるものは文字を奪ったことだ。結婚をあきらめ、修道女のような生き方を選ぶ「小母」見習い(「誓願者」と呼ばれる)にならなければ、女は読み書きを学ぶことができない。言論統制はディストピアの定番だが、『誓願』は奪われた知を取り戻す戦いの物語だ。
そして、希望とシスターフッドの物語でもある。差別を公然と口にするドナルド・トランプが米国大統領になり、一方で#MeTooの波が世界を席捲する中で出版された本書に、八十歳の著者は女性たちへのエールを込めたに違いない。国家が文化や芸術、学術を攻撃し、排除する怖さを身につまされつつ読んだ。二〇一九年ブッカー賞受賞。
ALL REVIEWSをフォローする