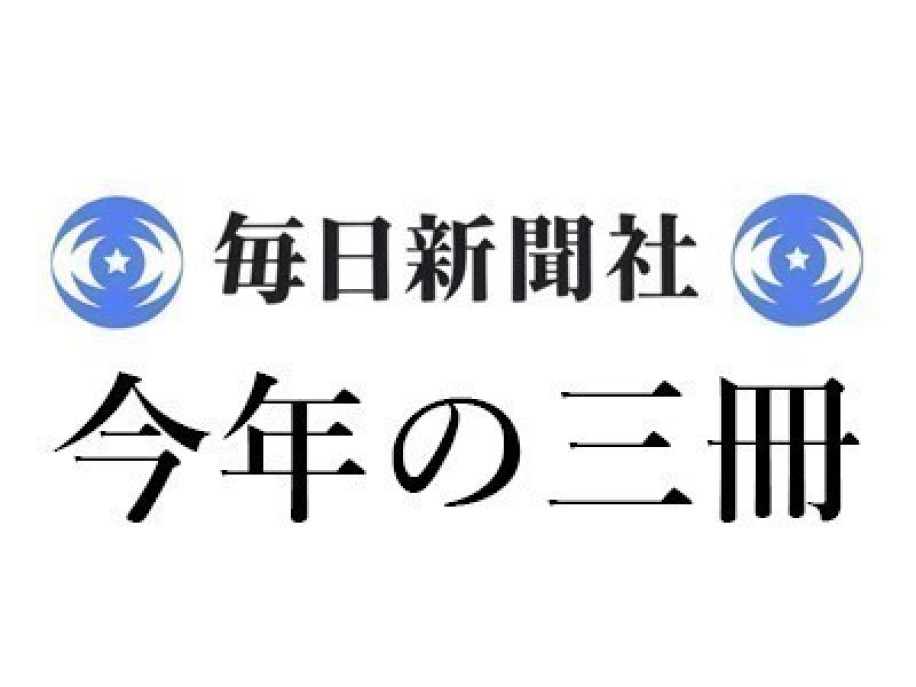書評
『装幀談義』(筑摩書房)
第一歌集『サラダ記念日』の装幀を初めて見た時には、正直言ってびっくりした。
「写真が使ってあります」ということは、事前に編集の人から聞いていたのだが、ソデのところか、後ろの著者紹介とかいうところだとばっかり思っていた。それが、表紙に、どんと自分の顔である。ひええっ。
装幀をしてくださったのは、菊地信義さん。私もその頃、生まれて初めての本が出版されることになって、俄か勉強であれこれと装幀の本を読んだりしていた。中で一番おもしろく心に残ったのが、菊地さんの『装幀談義』という本である。
心を落ちつけて、もう一度『サラダ記念日』の表紙を見る。その時、『装幀談義』の中のこんな言葉が思い出された。
私が勝手に、何となく思い描いていたパステル調の表紙というのは、まさにこの歌集の「イラスト」だった。菊地さんは、この歌集の「構造」を、モノクロームの私一人の写真で表現されたわけである。こわい。考えてみると、思いあたることが、いくつかあった。
短歌は、「一人称の文学」と言われる。何も書いていなければ、主語は「われ」だ。
歌集のあとがきに、私はこう書いた。「原作・脚色・主演・演出=俵万智、のひとり芝居――それがこの歌集かと思う。」
それから、歌集の最後にはこんな歌を置いた。
愛された記憶はどこか透明でいつでも一人いつだって一人
一人称・一人芝居・いつだって一人――。菊地さんは、この歌集のそういったところを摑まえてこられたのではないだろうか。
ちなみに、表紙に使われた写真は、私にとってまことに思い出ぶかい一枚だ。作家の小林恭二さんがホストをなさっていた連載インタビューの、第一回のゲストとして招いていただいた時のものである。短歌の新人賞をもらったばかりで、マスコミにそういった形で紹介されるのは初めてのことだった。
そのインタビューを読んで電話をくれたのが、河出書房新社の編集の人である。そこから歌集出版の幸運に恵まれた。『サラダ記念日』が生まれる一つのきっかけにもなった写真なのである。菊地さんがそこまでご存知だったかどうかは、確かめてはいないけれど。
【この書評が収録されている書籍】
「写真が使ってあります」ということは、事前に編集の人から聞いていたのだが、ソデのところか、後ろの著者紹介とかいうところだとばっかり思っていた。それが、表紙に、どんと自分の顔である。ひええっ。
装幀をしてくださったのは、菊地信義さん。私もその頃、生まれて初めての本が出版されることになって、俄か勉強であれこれと装幀の本を読んだりしていた。中で一番おもしろく心に残ったのが、菊地さんの『装幀談義』という本である。
心を落ちつけて、もう一度『サラダ記念日』の表紙を見る。その時、『装幀談義』の中のこんな言葉が思い出された。
ぼくはずっと一貫していることなんですが本の装幀というのは、そのテキストに対するイラストレーションや解説でありたくないと思っているわけです。つまりそのテキストの構造でありたいと思っているんですね。
私が勝手に、何となく思い描いていたパステル調の表紙というのは、まさにこの歌集の「イラスト」だった。菊地さんは、この歌集の「構造」を、モノクロームの私一人の写真で表現されたわけである。こわい。考えてみると、思いあたることが、いくつかあった。
短歌は、「一人称の文学」と言われる。何も書いていなければ、主語は「われ」だ。
歌集のあとがきに、私はこう書いた。「原作・脚色・主演・演出=俵万智、のひとり芝居――それがこの歌集かと思う。」
それから、歌集の最後にはこんな歌を置いた。
愛された記憶はどこか透明でいつでも一人いつだって一人
一人称・一人芝居・いつだって一人――。菊地さんは、この歌集のそういったところを摑まえてこられたのではないだろうか。
ちなみに、表紙に使われた写真は、私にとってまことに思い出ぶかい一枚だ。作家の小林恭二さんがホストをなさっていた連載インタビューの、第一回のゲストとして招いていただいた時のものである。短歌の新人賞をもらったばかりで、マスコミにそういった形で紹介されるのは初めてのことだった。
そのインタビューを読んで電話をくれたのが、河出書房新社の編集の人である。そこから歌集出版の幸運に恵まれた。『サラダ記念日』が生まれる一つのきっかけにもなった写真なのである。菊地さんがそこまでご存知だったかどうかは、確かめてはいないけれど。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
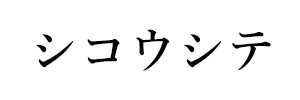
シコウシテ(終刊) 1990年9月号(22号)
ALL REVIEWSをフォローする