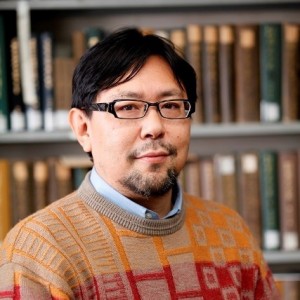書評
『商う狼: 江戸商人 杉本茂十郎』(新潮社)
世間に疎まれ揶揄され突き進む反骨の改革者
近江商人は「三方よし」を信条として商いに励んだという。「買い手よし 売り手よし 世間よし」。購買者は満足、販売者も得を取る。もう一つ。世間すなわち社会に対して貢献しよう。それでこそ商売は安定する、というのが近江商人の考え方であり、心意気でもあった。古く、商人は世界各地で不当に低い評価を受けた。自分は何も生み出さず、右のものを左に動かすだけで利益とする。それは神の御心に背く、というわけだ。日本でも商人は長く正当な評価を受けなかった。逆風の中で、彼らは自身の存在意義を求め続けた。本書も言及する「三方よし」はその精華といえる。
文化4(1807)年、富岡八幡宮の祭礼に江戸中から多くの人が集まった。深川へ向かう彼らが渡ろうとしたとき、老朽化していた永代橋が重みに耐えきれず崩落した。後ろから押し寄せる群衆が雪崩を打って転落して大惨事となり、死傷者は1400人を超えたという。
甲斐出身の一介の奉公人から身を興した大坂屋茂兵衛は、この事故で妻と幼い男児を失った。彼は世のため人のため、まさに「世間よし」を実現しようと、橋の再建に邁進する。その優れた経営手腕は幕府の認めるところとなり、短期間に江戸の財界をまとめあげた彼は名も杉本茂十郎と改め、日本全体の経済にまで視野を拡大していく。
「金は刀より強い」。それを理念として商人の道を突き進む彼であったが、彼が何より大切にしていた世間の側は次第にその豪腕を嫌うようになり、茂十郎をもじって「毛充狼」なる獣として揶揄するまでになる。はたして武士の世は彼をどう遇したのか。茂十郎の挑戦の行方は。手に汗握る雄渾(ゆうこん)な物語である。歴史事実の調査もお見事。ずしりと読み応えのある一冊。
ALL REVIEWSをフォローする