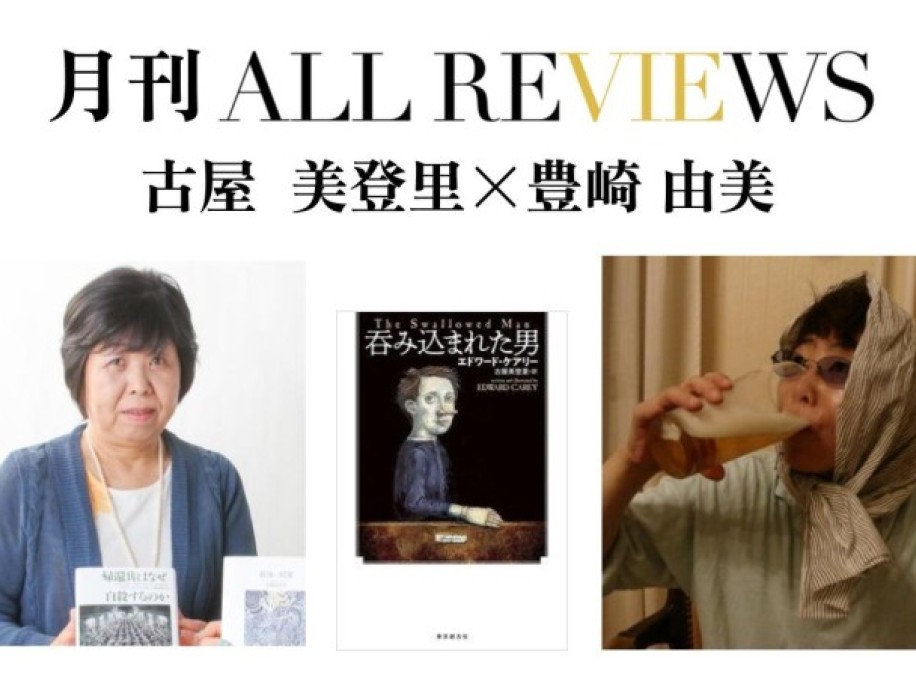書評
『望楼館追想』(文藝春秋)
奇人変人が好きだ。彼らは、慣習という囲いに風穴をあけてくれる。今・此処(ここ)とは違うシステムで成立している世界、その存在の可能性を垣間見せてくれる。つまり、退屈な日常を打ち破ってくれる、ありがた~い方々なのだ。
だから我は愛す、エドワード・ケアリーの『望楼館追想』を。だって、奇人変人見本市小説なんだもの。舞台はヨーロッパのとある国の小さな町に建つ古い館。白い手袋を決してはずさず、他人が愛したものを盗み蒐集している語り手のフランシスをはじめ、この館の住人たちの奇矯な個性をまずは堪能してほしい。部屋から一歩も出ず、テレビを見続け、虚構の中に生きる老女。全身から汗と涙を流し続ける体毛のない元教師。人語を一切介さない犬女。「シッ」「あっちへいってろ」しか話さない門番。生ける屍のようなフランシスの父。そんな面々が、外界とはほとんど交わらず、時間が停止したような崩壊寸前の館で幸せに暮らしている。
ところが、新しい住人アンナの登場によって、死んでいた館の時間が動き始めてしまう。老女はテレビを消し、犬女は言葉を思い出す。寝たきりだったフランシスの母が目覚め、父が立ち上がり、望楼館の歴史を語り出す。そうしたこと全てが気にくわないフランシスだけは最後まで抵抗するのだが――。
『ブリキの太鼓』のオスカルを彷彿させる反社会的な性格を持つ奇人フランシスの語りがまとうグロテスクなユーモア。彼が蒐集する品々に関する寓話的エピソードの妙。その中でもとりわけ気味の悪いコレクションにまつわる謎。館を舞台にしていながら、ゴシックというよりはバロック。歪んだ感性が魅力の一冊なのだ。奇妙な味系小説が好きな方に熱烈推薦したい珍品中の珍品だ。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
だから我は愛す、エドワード・ケアリーの『望楼館追想』を。だって、奇人変人見本市小説なんだもの。舞台はヨーロッパのとある国の小さな町に建つ古い館。白い手袋を決してはずさず、他人が愛したものを盗み蒐集している語り手のフランシスをはじめ、この館の住人たちの奇矯な個性をまずは堪能してほしい。部屋から一歩も出ず、テレビを見続け、虚構の中に生きる老女。全身から汗と涙を流し続ける体毛のない元教師。人語を一切介さない犬女。「シッ」「あっちへいってろ」しか話さない門番。生ける屍のようなフランシスの父。そんな面々が、外界とはほとんど交わらず、時間が停止したような崩壊寸前の館で幸せに暮らしている。
ところが、新しい住人アンナの登場によって、死んでいた館の時間が動き始めてしまう。老女はテレビを消し、犬女は言葉を思い出す。寝たきりだったフランシスの母が目覚め、父が立ち上がり、望楼館の歴史を語り出す。そうしたこと全てが気にくわないフランシスだけは最後まで抵抗するのだが――。
『ブリキの太鼓』のオスカルを彷彿させる反社会的な性格を持つ奇人フランシスの語りがまとうグロテスクなユーモア。彼が蒐集する品々に関する寓話的エピソードの妙。その中でもとりわけ気味の悪いコレクションにまつわる謎。館を舞台にしていながら、ゴシックというよりはバロック。歪んだ感性が魅力の一冊なのだ。奇妙な味系小説が好きな方に熱烈推薦したい珍品中の珍品だ。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする