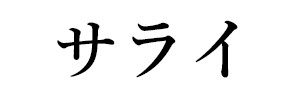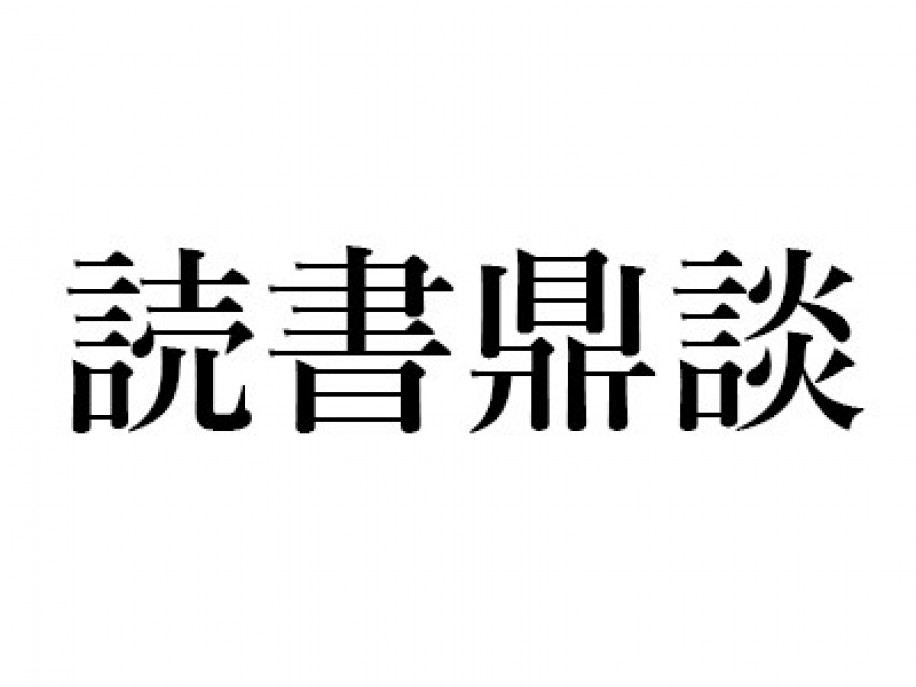書評
『坂の上の雲』(文藝春秋)
いじらしい明治の青春像と近代国家の孕(はら)む矛盾
司馬遼太郎さんの作家としての一番の関心事は、明治以降の国民国家としての日本というものだったと思います。その明治という時代の青春期を描いてベストセラーとなったのが『坂の上の雲』(文春文庫)です。近代日本への入口となる明治維新は、実は不思議なトリックによって成立しています。当初、幕府を倒して近代国家をつくろうとした志士たちは、口をそろえて「尊王攘夷(そうのうじょうい)」と言っていた。が、政権がとれて近代政府ができると、あっという間に「尊王開国」に変じた。「攘夷」が抜け落ちてしまったのです。この矛盾を日本人は意識下の深いところでずっと持ち続けていました。何かがあったら、かつての攘夷の怨念を爆発させるという奇妙な行動に出る。日露戦争にもそんな側面がありました。もちろん時代状況から見て、もしあのときロシアに負けていたら、今の日本の独立すら危うかった。ですから、合理的に考えてもロシアとは戦わざるを得なかったけれども、開国以来のもやもやした気分を一掃するという意味でも、日本人には日露戦争が受け入れられやすいところがあったと思います。
司馬さんは日本の近代化について賛成で、肯定的な立場をとっています。『坂の上の雲』の主人公である秋山好古や真之、さらには正岡子規にしても、それぞれの分野で近代化、合理化を進めた人です。日露戦争の話にしても、日本軍が、時には命懸けで無茶もしますが、まだ合理的でかなりきちっと考えて戦争をしたということを作品の中で強調されていますね。
一方、この戦いは、単なる近代合理的なものではなく、情緒的で非合理な愛国心や国粋主義的な風潮も含んでいた。それには、司馬さんは批判的です。だから、司馬さんにとっては日露戦争それ自体が矛盾を孕(はら)んだぎりぎりの題材だったと思う。二度目の「攘夷」戦争ともいえる太平洋戦争となると、彼はもう全面的に反対です。が、両者は底の底では繋がっている。
彼はいろいろ悩んで、結局自分が本当に愛しうるものは、日本国家ではなくて、日本の中の村や町だということに気づいたんじゃないでしょうか。愛国心でなく愛郷心。彼に言わせると、あらゆる谷あいに日本人にとってのふるさとがある。『坂の上の雲』でいえば松山です。松山からたまたま陸軍と海軍と、そして文学という異なる分野で活躍する三人の若者が出てきた。司馬さんは、その松山を書きたかったのだと思います。
司馬さんは最初、秋山兄弟と子規をずっと並行させるような形で書いていこうと意図していたのではないでしょうか。
もちろん子規は早く死にますけど、高浜虚子とか河東碧梧桐(へきごとう)とか、松山出身の子規の弟子が近代俳句を育てていくし、一方で漱石とも深いつきあいがあって、近代文学というものにいろいろな形で功績を残していますからね。
ところが、この小説が発表されたときは、折しも高度経済成長の真っ盛り。第二次大戦の失意の中から立ち上がってきた人たちが、工場や商社で猛烈に働き、日本の経済がどんどん上がっている時期です。新聞連載がはじまると読者のほうが舞い上がったのではないでしょうか。日露戦争で日本が勝っていくところを司馬さんの名文で読むと、そこに自分たちの姿が重なって気分が高揚する。これは私の推察ですが、司馬さんはそんな読者の熱気を受け、無意識に日露戦争、とくに日本海海戦の場面に力が入り過ぎたのかもしれない、という印象があるのです。
近代国家というものは、成長して大きくなり、強くなっていくと、それ自体の力で矛盾を生じてくる。合理主義を貫徹するより、愛国心のような非合理なもののほうが国家の推進力になる。
今この作品を読み直す読者の皆さんも、きっといじらしい明治の青春像に惹かれることでしょう。しかし、彼らが築き上げた近代国家という非常に精妙な仕掛けも、一歩間違えたら情緒的愛国心であっという間に燃え上がってしまう、そんな危うさを孕んでいることも隠れたメッセージとして、読み取ってほしいですね。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする