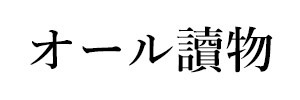選評
『花まんま』(文藝春秋)
直木三十五賞(第133回)
受賞作=朱川湊人「花まんま」/他の候補作=絲山秋子「逃亡くそたわけ」、恩田陸「ユージニア」、古川日出男「ベルカ、吠えないのか?」、三浦しをん「むかしのはなし」、三崎亜記「となり町戦争」、森絵都「いつかパラソルの下で」/他の選考委員=阿刀田高、五木寛之、北方謙三、津本陽、林真理子、平岩弓枝、宮城谷昌光、渡辺淳一/主催=日本文学振興会/発表=「オール讀物」二〇〇五年九月号作者の知恵
短篇を七つ収めた『むかしのはなし』(三浦しをん)は、巻頭の「ラブレス」がいい。緊迫感あふれる傑作である。展開と表現に小気味のよい速度と機知があって、いたるところに作者の才能が輝いていた。この調子で行ってくれと祈りながら読みつぐうちに、口惜しいことに次第に調子が落ちて行った。各篇の冒頭に掲げられた日本昔話と本体とのつながり具合がよくわからないし、各篇を貫く〈隕石の接近〉という仕掛けも、それほどうまくは活用されていない。また、「隕石、地球に衝突」という全地球的大事件が、三ヵ月前までわからないなど、とても信じられない。各篇が「ラブレス」のような出来栄えであったら、作者も読者もしあわせだったのだが。十七人毒殺という陰惨な事件の核心へ、語り手をくるくる替えながらじりじりと接近して行く『ユージニア』(恩田陸)は、前半が飛び切りの秀作である。語り手が変われば語り口も変って、このあたりの小説技術は一級品だ。しかし核心に近づくにつれて、その核心そのものがぼやけてしまうのは、どうしてなのだろう。韜晦(とうかい)が高じて、なにがなんだかわからなくなり、前半の貯金を後半で一気に吐きだしてしまった。
父の一周忌までの、あとに取り残された家族の境遇の変化と心理の陰影を、軽快な会話を駆使して描いた『いつかパラソルの下で』(森絵都)は、「父の不在は、じつは父の実在である」という切実な主題を扱っている。父はどんな人間だったのか。家族がそれを探っているうちに、父の像が、聖人君子の鑑(かがみ)から肉欲に溺れた絶倫男へ、そしてただの平凡人へと三転し、それにつれて家族各員の生き方にも微妙な変化が生まれてくるという流れは、巧いといっただけでは収まらないような、目覚ましい才筆である。ただし、父の像探しの佐渡旅行で、それまで文章に込められていた気合いのようなものが呆気(あっけ)なく抜けて、ただの平凡な旅行記になってしまったのは意外だった。作品はここでそれまでの貫目(かんめ)を失った。
『逃亡くそたわけ』(絲山秋子)は、福岡の精神病院から南をさして、ただひたすら逃げて行く二人の精神病者の道中記で、なかなかおもしろい。一人は語り手のわたし、幻覚と幻聴に悩む二十一歳。彼女の連れは鬱から回復しつつある二十四歳のエリート社員。二人とも日常からずれているから交わす対話も珍妙で、ときおり飛んでもない哲学的省察にまで高まる。こうして読者は絲山節(ぶし)を堪能するのだが、しかし二人を追い詰めているはずの「日常」や「常識」が、まったく書き込まれていない。わたしの語り口に「狂った誠実さ」が欠けていて、すべてがあんまりあっさりしすぎている。当然、仕上がりも軽くなり、そこから「精神病を道具に使っているのではないか」という疑問が生まれてきた。
このようなわけで、評者は右(ALL REVIEWS事務局注:上)の四作に△印をつけた。○印は以下の三作品で、○印は、このうちのどれが受賞作になっても賞の歴史を辱めることはないにちがいない、という評者の気持を示している。
戦争を公共事業として捉えた『となり町戦争』(三崎亜記)は、その視点の新鮮さに打たれた。この視点に立てば、たとえばイラクで行なわれている戦争の正体も見えてくる。「あれは民間戦争会社による公共事業だよ」というふうに。この視点を発見しただけでも、作者の手柄は大きい。作中に、「公務によるラブシーン」が現れるが、この場面の透徹した美しさは、作者のすぐれた資質を証し立てている。
『ベルカ、吠えないのか?』(古川日出男)は、戦後のアジア史そして世界史を丸ごと、軍用犬の眼から描くという離れ業、そこに作者の逞しい文学的腕力があらわれている。たしかに欠点がないでもないが、全編にみなぎる「小説は言葉で創るものだ」という気合いに、この作者の豊かな未来を視たようにおもう。作者が「ベルカ、吠えないのか?」と問いかけるたびに犬の物語になるところなどは、ごくごく上質の諧謔(かいぎゃく)である。
過ぎ去った幼い日々の、その日常の中に、さりげなく超自然現象を置くというのが『花まんま』(朱川湊人)に収められた六篇に共通する仕立てである。怖い話(たとえば「妖精生物」)があれば、切ない話(たとえば「凍蝶」)があり、またおかしな話(たとえば「送りん婆(ばあ)」)もあって、いろとりどりだが、大切なのは六篇とも佳品であること、一篇の無駄打ちもないところに値打ちがある。
中でも感心したのは「送りん婆」である。死の床で苦しむ病者をあっさりあの世へ送り出す呪文があって……と、ここまでは評者でも書けるが、驚くのはその呪文そのものを作者がはっきりと書きつけていることだ。では、その呪文を知ったわたしたちが、それを使って病者をあの世送りできるかというと、じつはそうは行かない。そうは行かない理屈が揮(ふる)っていて、そこに作者一流の知恵がある。
最終投票で『花まんま』に入れたのは、この作者の知恵に感心したからである。
【この選評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする