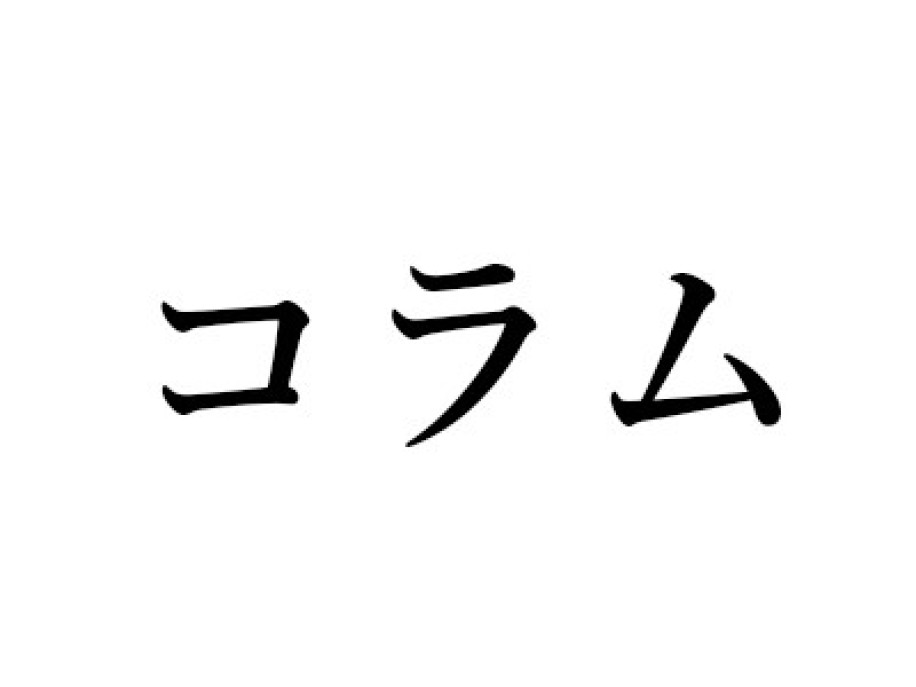後書き
『肉食の終わり:非動物性食品システム実現へのロードマップ』(原書房)
ベジタリアンやビーガンが増えていると言われています。実際、そのような人向けの飲食店をよく見かけるようになりました。また飲食店だけでなく、カレーをはじめとするレトルト食品ほか、食品業界もベジタリアンやビーガンにいま注目しています。日本では「変わった人」と思われることが多かったベジタリアンやビーガンは、少しずつ「少数派」ではなくなってきています。
けれども、「肉食をしない」という食べ方を選択しようとするとき、それは現実の生活、現実の人間関係のなかでは、たったひとりの孤独な戦いになってしまうことが今でも多いはずです。
地球環境への多大な負荷、肥満・糖尿病等の要因、劣悪な環境の畜産「工場」……肉食文化が持つ弊害を指摘する声は多いのですが、実際に「肉食をしない」食べ方はもっぱら「個人的な努力」によってしか実現できない、と多くの人が思っています。
新刊書籍『肉食の終わり』のなかで、ビーガンとしてさまざまな活動を行ってきた著者のジェイシー・リースは、そういった「個人的な努力」という考え方そのものを問題にしています。脱肉食化を「個人的な努力」などではなく「社会全体として実現」できないか、そのためには何をすべきか――。食べることの未来を考える本書の訳者、井上太一による「解題」の一部を公開します。
とりわけ環境問題をめぐる議論では、畜産業が地球温暖化や森林破壊、資源枯渇、等々の大きな原因であると認められ、いまや国連食糧農業機関(FAO)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のような国際機関までが肉食の削減を世界に呼びかけている。
加えて畜産業はインフルエンザをはじめとする動物由来の感染症(人獣共通感染症)の主たる温床であり、抗生物質の濫用によって数々の多剤耐性菌をも生み出してきたことから、保健衛生上の脅威とみなされている。さらに動物性食品が肥満・糖尿病・心疾患・動脈硬化・その他、種々の病気を引き起こすこともよく知られている。
そして何より、現代の畜産業は無数の動物たちを狭い施設に閉じ込め、一切の自由を奪ってひたすら肉・乳・卵の産出に従事させる無慈悲な営みと化しており、深刻な倫理問題を私たちに突き付ける。
もはや物理的にも道徳的にも、今日の食品システムが限界を来していることは隠しようのない事実となった。
食品業界はすでに畜産物を主体とする生産モデルからの転換を図り、植物性の代替食品を開発し始めている。何しろ、日本の大手ハム会社すら大豆ミートの加工品シリーズを発売しだしたほどで、それらは動物成分が入っているためビーガン向けではないにせよ、数年前には考えられなかった展開に違いない。
無論、こうした潮流が形づくられた背景には、動物たちや地球環境の現状を問い、より良い世界のあり方を模索してきた無名の人々の努力がある。消費者・活動家・研究者・事業家、それに非営利団体・企業・研究機関・各国政府が一体となって、世界の脱肉食化を成し遂げることは、今世紀の大きな課題に数えられるだろう。
本書はこのような問題意識をもとに、非動物性食品システムの確立へ向けたロードマップを描く戦略の書である。
著者ジェイシー・リースは社会運動の分析に携わる非営利シンクタンク、情感研究所(Sentience Institute)の共同創設者であり、効果的な利他主義という哲学をもとに、確固たる証拠(エビデンス)と合理的思考に則って人類の道徳拡張をめざす。
本書でもその姿勢は貫かれ、実地調査や統計データ、心理学研究の成果などをふんだんに活かしつつ、食品システムの一新を達成するための最も効果的な戦略が検証される。
従来、日本には肉食の弊害やビーガニズムの意義を説いた情報源こそあれ、畜産物中心の食品システムを改めるための具体的な方法論はほとんど存在しなかった。本書はその欠落を補うものとして貴重な役割を担う。
著者が用いるデータは日本でほとんど知られていないものばかりであり、これらは非動物性食品の普及や開発に努める全ての人々にとって有用な知識となるだろう。
ビーガン関連の事業を始めようとする人々、食や動物に関する啓蒙に携わる人々、社会貢献を望む研究者や技術開発者などは、この本から多くのヒントを得られるに違いない。
[書き手]井上太一(いのうえ・たいち)
翻訳家。人間中心主義を超えた倫理を発展させるべく、関連する海外文献の翻訳に携わる。マイケル・A・スラッシャー『動物実験の闇』(合同出版/2017年)、ディネシュ・J・ワディウェル『現代思想からの動物論』(人文書院/2019年)、エリーズ・ドゥソルニエ『牛乳をめぐる10の神話』(緑風出版/2020年)ほか、訳書多数。ホームページ「ペンと非暴力」を運営。
けれども、「肉食をしない」という食べ方を選択しようとするとき、それは現実の生活、現実の人間関係のなかでは、たったひとりの孤独な戦いになってしまうことが今でも多いはずです。
地球環境への多大な負荷、肥満・糖尿病等の要因、劣悪な環境の畜産「工場」……肉食文化が持つ弊害を指摘する声は多いのですが、実際に「肉食をしない」食べ方はもっぱら「個人的な努力」によってしか実現できない、と多くの人が思っています。
新刊書籍『肉食の終わり』のなかで、ビーガンとしてさまざまな活動を行ってきた著者のジェイシー・リースは、そういった「個人的な努力」という考え方そのものを問題にしています。脱肉食化を「個人的な努力」などではなく「社会全体として実現」できないか、そのためには何をすべきか――。食べることの未来を考える本書の訳者、井上太一による「解題」の一部を公開します。
食べることの「利他」と「未来」へ
肉食文化の問題はつい最近までほとんど顧みられることがなかったが、ここ数年で広く社会の注目を集めるようになった。とりわけ環境問題をめぐる議論では、畜産業が地球温暖化や森林破壊、資源枯渇、等々の大きな原因であると認められ、いまや国連食糧農業機関(FAO)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)のような国際機関までが肉食の削減を世界に呼びかけている。
加えて畜産業はインフルエンザをはじめとする動物由来の感染症(人獣共通感染症)の主たる温床であり、抗生物質の濫用によって数々の多剤耐性菌をも生み出してきたことから、保健衛生上の脅威とみなされている。さらに動物性食品が肥満・糖尿病・心疾患・動脈硬化・その他、種々の病気を引き起こすこともよく知られている。
そして何より、現代の畜産業は無数の動物たちを狭い施設に閉じ込め、一切の自由を奪ってひたすら肉・乳・卵の産出に従事させる無慈悲な営みと化しており、深刻な倫理問題を私たちに突き付ける。
もはや物理的にも道徳的にも、今日の食品システムが限界を来していることは隠しようのない事実となった。
食品業界はすでに畜産物を主体とする生産モデルからの転換を図り、植物性の代替食品を開発し始めている。何しろ、日本の大手ハム会社すら大豆ミートの加工品シリーズを発売しだしたほどで、それらは動物成分が入っているためビーガン向けではないにせよ、数年前には考えられなかった展開に違いない。
無論、こうした潮流が形づくられた背景には、動物たちや地球環境の現状を問い、より良い世界のあり方を模索してきた無名の人々の努力がある。消費者・活動家・研究者・事業家、それに非営利団体・企業・研究機関・各国政府が一体となって、世界の脱肉食化を成し遂げることは、今世紀の大きな課題に数えられるだろう。
本書はこのような問題意識をもとに、非動物性食品システムの確立へ向けたロードマップを描く戦略の書である。
著者ジェイシー・リースは社会運動の分析に携わる非営利シンクタンク、情感研究所(Sentience Institute)の共同創設者であり、効果的な利他主義という哲学をもとに、確固たる証拠(エビデンス)と合理的思考に則って人類の道徳拡張をめざす。
本書でもその姿勢は貫かれ、実地調査や統計データ、心理学研究の成果などをふんだんに活かしつつ、食品システムの一新を達成するための最も効果的な戦略が検証される。
従来、日本には肉食の弊害やビーガニズムの意義を説いた情報源こそあれ、畜産物中心の食品システムを改めるための具体的な方法論はほとんど存在しなかった。本書はその欠落を補うものとして貴重な役割を担う。
著者が用いるデータは日本でほとんど知られていないものばかりであり、これらは非動物性食品の普及や開発に努める全ての人々にとって有用な知識となるだろう。
ビーガン関連の事業を始めようとする人々、食や動物に関する啓蒙に携わる人々、社会貢献を望む研究者や技術開発者などは、この本から多くのヒントを得られるに違いない。
[書き手]井上太一(いのうえ・たいち)
翻訳家。人間中心主義を超えた倫理を発展させるべく、関連する海外文献の翻訳に携わる。マイケル・A・スラッシャー『動物実験の闇』(合同出版/2017年)、ディネシュ・J・ワディウェル『現代思想からの動物論』(人文書院/2019年)、エリーズ・ドゥソルニエ『牛乳をめぐる10の神話』(緑風出版/2020年)ほか、訳書多数。ホームページ「ペンと非暴力」を運営。
ALL REVIEWSをフォローする